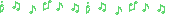
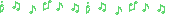
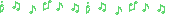
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

オレンジブロッサムは、まだ混雑していないみたいだった。
出迎えてくれた顔見知りのウエイトレスさんに挨拶をして、バックヤードに入る。
店長室の小窓を背伸びして覗いたら、何かを見ながらコーヒーを飲む翡翠さんの頭が見えた。
ノックをすると、気だるそうな声が聞こえてくる。
「入っていいよ。」
ドアを開けると、つまらなそうにこちらを向いた翡翠さんが、にっこりと笑顔になった。
「おや、可愛らしいサンタさんのお出ましだね。」
そう言って、コーヒーカップをソーサーに置く。
デスクを見ると、発注伝票が広げられていた。
「お仕事中に、ごめんなさい・・・」
発注伝票を見ながら言ったら、翡翠さんは微笑みながら立ち上がった。
「他人の都合などお構いなしで忍び込んでくるのが、サンタさんの良いところだよ。」
店長室のドアを閉めて、さりげなく小窓から外を覗く。
ドアノブを持ったままの翡翠さんの手の中で、微かに鍵のかかる音がした。
・・・鍵をかける必要はないと思うんですけど・・・
青くなる私に構わず、翡翠さんはもとの場所に戻って椅子に座った。
「もっと近くにおいで。今夜は一晩、サンタさんを好きにしていいのだろう?」
椅子に座ったまま私の腰を引き寄せて、楽しそうに私の顔を見上げる。
「そ・・・そんなこと誰も言ってません!」
「どうして?私は良い子にしていたじゃないか・・・サンタさんは良い子が一番欲しい物をくれるのではなかったかな?」
「翡翠さんがいつ良い子にしてたんですか?」
私は、唇を尖らせてカバンからプレゼントを出した。
初めて編んだマフラー。
ところどころ編み目がばらついてるから、使ってもらえるか心配だけど。
翡翠さんは、それを受け取って、ほう、と小さく声を上げた。
たたんだままのマフラーに顔をつけて、すうっと息を吸い込む。
それから、満足そうに笑んで、マフラーにほお擦りをしながら、片目だけで私を見た。
「姫君の、匂いがするね。」
私を見つめる片目が妖しい光を放って、プレゼントを渡したらすぐに逃げ出そうとしていた私は固まってしまった。
翡翠さんは神棚に供えるように机の上にマフラーを置くと、言った。
「それにしても、罪作りなサンタさんだ。毎日、この匂いに包まれていたら、私は姫君が恋しくて狂ってしまうかもしれない。」
「・・・もう、嘘ばっかり・・・」
「嘘かどうか、今に分かるよ。」
翡翠さんはそう言いながら、スーツの胸ポケットを探ると、私の手首に何かをはめた。
ビーズ?・・・にしては大きい白くて丸い石のブレスレット。
ワンポイントで小さな花の形に彫られた白い石と、小さな葉の形に彫られた緑の石がついている。
最近の雑貨屋さんに増えてきたような、ちょっとオリエンタルな雰囲気。
「すごく可愛いです!」
翡翠さんはにっこりと笑って言った。
「何の石だか分かるかな?」
「え・・・もしかして・・・ヒスイ?」
「そう。私だよ。」
そう言った翡翠さんの目は、すごく強い光を放っていた。
笑顔はいつもと同じなのに、なんだろう・・・心臓が・・・
私が思わず目を逸らすと、翡翠さんの少し茶化すような声が聞こえた。
「他の男にうつつを抜かしたら手首が締まるように呪いを掛けてあるからね。」
私は、その声を聞いて気付いた。
私の負担にならないように、冗談めかして言ってくれるけど・・・
いつも、瞳が本気だと語っているんだということ。
私が照れて、その瞳を真っ直ぐに見つめられない間も、翡翠さんの瞳は、私を見つめてる。
本気だという光を放って。
私がその瞳を見つめ返せる日を、待ってくれている。
私は、もう一度、ブレスレットを見つめた。
・・・うん。
本気を全部受け止めきれない私を、許して、見守ってくれている、翡翠さんの思い。
受け取りました。
「ありがとうございます。」
翡翠さんは優しく微笑むと、口を開いた。
「喜んでいただけたようなので、もう一つ、クリスマスプレゼントをあげよう。」
「え?私一つしか用意し・・・」
そう言って慌てた私の腰を翡翠さんはいきなりつかんだ。
ひょいっと私を持ち上げて、私の両足の間に膝を割り込ませると、そのまま馬乗りにさせた。
足が大きく開いて、すごく恥ずかしい格好。
「やっ?!こんな・・・んっ!」
大きな声を出す私の唇を、翡翠さんの唇が塞ぐ。
「・・・皆に覗かれたくはないだろう?」
唇を離すと、翡翠さんはそう言って、再び私の唇を塞いだ。
それから・・・翡翠さんのキスに翻弄されていた私は、気付かなかった。
翡翠さんの手がパンティーの中に入ってきていた事に。
あとは・・・その・・・恥ずかしくて言えないけど、とにかく気持ち良くって、身体がおかしくなっちゃって・・・
正気に戻った時には、私はぐったりと翡翠さんに縋っていて、翡翠さんはニコニコして指を舐めていた。
私が恥ずかしくて泣きそうになったら、翡翠さんは私をぎゅっと抱きしめて、可愛かったよって言ってくれた。
不思議。
それだけで、あんなにおかしくなってしまった自分の身体が、恥ずかしくなくなる。
それでいいのかもって思ってしまう。
翡翠さんがいいならいいやって思ってしまう。
・・・すごく気持ちよかったし・・・
頭の中身を全て翡翠さんに預けて、私はそのまましばらく翡翠さんの胸の中でボーっとしていた。