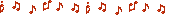
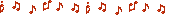
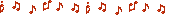
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

小学校の正門から鎖を跨いで前庭に入った。
前を行くイサト君の息が白く流れてくる。
イサト君は、暗い中庭を迷いもなく進んで、外灯の明かりが差す学童のプレハブの前に腰を下ろした。
「さみぃけど、ここならゆっくり話せるからな。」
イサト君は、そう言って私を手招きした。
「うん。」
イサト君が首を縮めているので、私はカバンからプレゼントを出して、首にかけてあげた。
初めて編んだマフラー。
ところどころ編み目がばらついてるから、使ってもらえるか心配だけど。
イサト君は、目を丸くしてマフラーを見つめた後、にっこりと笑ってくれた。
「ありがとな、花梨。」
でも、私が隣に座ると、それを外して私の首にぐるぐると巻いてしまった。
「今は、とりあえずお前がしとけ。」
ぶっきらぼうなイサト君の優しさが温かい。
見ると、イサト君は、ポケットの中から小さな袋を出していた。
「お前、こういうの好きか?」
心配そうに差し出したので、私は、受け取ってすぐに開けてみた。
袋の中には、ピンクのスワロフスキーがチャームっぽく何個もあしらわれている、甘い感じのブレスレットが入っていた。
「うん!好き!可愛い!」
私が手首にはめながら言うと、イサト君はホッと息をついた。
「女の好みは分かんねぇけど・・・それ、なんかお前に似てる感じがしたから。」
イサト君が私のことをこんな可愛い感じに思ってるなんて、すごく嬉しい。
「ありがと。」
私はブレスレットを手首にはめて、外灯にかざした。
それを眺めていたら、イサト君の少し真面目な声がした。
「花梨、俺、決めたから。」
「何?」
「大学。」
「えっ?どこにするの?」
「勝真と同じ一条大。初等教育学科があるんだ。」
「しょとう・・・?」
「小学校の先生になれる学科。」
「いいね!似合うよ、イサト君!」
「そうか?」
イサト君がへらりと笑う。
「うん!やっぱりイサト君は子供と一緒に居るのが一番いいよ!」
「俺、成績わりぃから、今から頑張らねぇと一条大入れねぇんだ。ホントは、冬休みにお前といろんなとこ行きてぇと思ってたんだけど・・・明後日から予備校の冬期授業に行く。だから、冬休みはあんまり会えねぇ。」
「いいよ、イサト君が頑張ってるなら、会えなくても我慢できるよ。」
「ゴメンな。」
「ううん、イサト君が一生懸命生きてる方が、嬉しい。」
「それってお前のおかげだぜ。まだ先生になれるか分かんねぇし、一条大に入れるかどうかも分かんねぇけど、この前お前に言った気持ちは、変わんねぇから。」
「・・・うん。」
イサト君の視線が、すごく強くて、私は思わず目を逸らしてしまった。
「もしかして、迷惑か?」
イサト君が不安そうな声を出す。
私は慌てて首を振った。
「じゃあ、こっち見ろよ。」
イサト君が、私の肩をつかんで、自分の方を向かせる。
私は、ドキドキするのを我慢して、イサト君の目をしっかりと見た。
自分でそうさせたくせに、イサト君は、ギクッとした顔をして、目を逸らす。
イサト君は、しばらくその姿勢のまま、あちこちに視線をさまよわせていたけど、チラッと私を見て言った。
「目。」
「え?」
「目ぇつぶれよ。」
そう言って、イサト君が横を向く。
私は、意味が分からなくてポカンとしていたのだけど、イサト君の横顔がみるみる赤くなっていくのを見て、やっと理解した。
もう一度、イサト君が、目だけでチラッと私を見る。
「・・・早く。」
怒ったような声で急かされて、私は慌てて目を閉じた。
それから、すごく長い間、私はイサト君を待った。
目を閉じてたから、イサト君が何をしてたのか分からないし、もしかしたら、私がドキドキしすぎて長い間だと錯覚したのかもしれないけど。
薄目を開けて見ちゃおうかな、と思った時に、唇に温かい息がかかって、柔らかいものが唇全体を塞いだ。
それから、また長い間、イサト君はキスしたままだった。
苦しいかったけど、イサト君の唇が鼻の近くまで塞いでいて、息ができなくて。
心の中でどうしよう、って思っていると、イサト君の唇が離れた。
息を吐いて、吸う。
落ち着いてから見上げると、イサト君も、少し苦しそうに荒い息を吐いていた。
「花梨・・・」
そう呟いて、私の肩をつかんでいた手をゆっくりと胸のほうにずらす。
私が、何だろう、とその手を見たら、イサト君は、ばっ、と勢いよく手を離していきなり立ち上がった。
天を仰いで両手で顔を覆うと呟く。
「何やってんだ、俺・・・」
そう言ったように聞こえたけど、小さな声だったし、くぐもってたから、よく分からない。
イサト君はパン、と両手で自分のほっぺたを叩いてから、私の方を見て言った。
「帰ろうぜ。送ってく。」
「どうかしたの?」
「なんでもねぇよ!」
イサト君は怒ったような声を出して、真っ赤な顔のままどんどん先に歩いて言ってしまった。
・・・ヘンなの。
次の日、イサト君は会うなり駆け寄ってきて、言った。
「なあ、もしかしてこのマフラー、お前が編んだとか?」
私が頷くと、イサト君はすごく慌てた。
「わりぃ、気付かなくて・・・昨日帰ってから、兄貴に言われてさ・・・ホント、ゴメン。」
私は、イサト君の慌てぶりが可笑しくて、思わず吹き出してしまった。