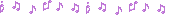
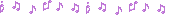
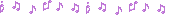
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

私は、泉水さんの家にお呼ばれしていた。
とは言っても、恵先生は毎年恒例のクリスマスコンサートに出演するから留守なんだって。
泉水さんがいつも独りでクリスマスを過ごしていたって知って、私は驚いてしまった。
「そういうものだと思っていましたから・・・」
泉水さんは、そう言いながら、フライドチキンの箱を丁寧に畳んだ。
毎年、泉水さんは、こうして買ってきたものを独りで食べてるらしい。
泉水さんが立ち上がって、冷蔵庫からケーキを出してきた。
「毎年母が作って置いて行ってくれるのです。」
そう言ってナイフを入れる。
手作りにしては手の込んだケーキに、私は、恵先生の泉水さんに対する気持ちを感じた。
そばに居なくても、こうして伝わる気持ちが、泉水さんを優しい男の人にしたのかもしれない。
母の愛には適わないなあ、と思っていると、チャイムが鳴った。
「あ、来ましたね。」
泉水さんが嬉しそうに微笑む。
「貴女をお呼びしたのは、これを一緒に聴いていただきたかったからなのです。」
そう言った泉水さんに手を引かれて玄関に出る。
泉水さんがドアを開けると、白い服を着た子供達が、広い玄関に元気よく雪崩れ込んできた。
「メリークリスマス!」
可愛い声で揃って叫ぶと、きれいに賛美歌を歌い始める。
「わあ・・・」
私が歓声をあげると、隣にいた泉水さんが、私の手を取った。
「一緒に歌いましょう。」
頷いて、泉水さんと一緒に口ずさむと、子供達も嬉しそうにのびのびと歌い始める。
知らなかった。
ただ、一緒に歌うだけで、こんなに子供達がのびのびとするなんて。
歌が上手かどうかなんて関係ない。
一緒に歌ってあげる事が、それだけが子供達の心を開かせる。
私は、子供たちと一緒に歌いながら、そのことを教えてくれた泉水さんの手を、強く握り返した。
子供達は、3曲ほど歌うと、また元気よく出て行った。
泉水さんとそれを見送って、玄関のドアを閉める。
「可愛かったあ!」
私が言うと、泉水さんがにっこりと笑った。
「近くの児童養護施設に寄付をすると、お礼に聖歌隊が来てくれるのですよ。」
「へえ・・・」
「きっと貴女に喜んでいただけると思って・・・」
私は、その言葉を聞いて、思わず泉水さんに飛びついていた。
「はい!泉水さんのおかげで、大切な事が分かりました!」
「・・・か、花梨さん・・・」
泉水さんの恥ずかしそうな声が聞こえて、私は泉水さんが男であることを思い出す。
慌てて離れると、泉水さんが真面目な顔で私を見ていた。
いつも思うけど、泉水さんのこういう顔はすごく男っぽい。
私がドキッとして固まると、泉水さんは私を優しく抱きしめて、おでこにキスしてくれた。
くすぐったくて目を閉じる。
すぐに、私の唇に、泉水さんの唇が軽く触れる感触がした。
驚いて目を開くと、泉水さんは、頬を染めて私から離れた。
「あ、あの・・・プレゼントをお持ちしますので、リビングでお待ちください。」
そう言って二階への階段を駆け上がる。
私も、赤くなった顔を手で冷ましながら、リビングへ戻った。
カバンからプレゼントを出す。
初めて編んだマフラー。
ところどころ編み目がばらついてるから、使ってもらえるか心配だけど。
泉水さんが小さな袋を持ってリビングに戻ってきた。
ソファーに座った私の隣に腰を下ろす。
「メリークリスマス。」
そう言って袋からブレスレットを出すと、私の手首につけてくれた。
淡水パールとウエーブチェーンが、すごくフェミニンな感じ。
「わあ、可愛い!」
私が声を上げると、泉水さんはホッとした顔になった。
「気に入っていただけましたか?」
「はい!」
「良かった・・・とてもお似合いですよ。」
泉水さんがそう言って私を見つめたので、私はなんだか照れてしまった。
私も、膝の上に置いてあったマフラーを差し出す。
「メリークリスマス。」
泉水さんは、微笑んで受け取ってから、少し不安そうな顔をした。
「あの・・・これは・・・もしかして・・・」
「私が編みました・・・初めてだから上手にできなかったけど・・・」
そう言った途端に、泉水さんが泣きそうな顔になった。
「私のために・・・編んでくださったの・・・ですか?」
私は、泉水さんの反応が思った以上だったので、怯んでしまった。
「は、はい・・・」
「・・・ありがとうございます!」
泉水さんは飛びつくように私を抱き寄せると、ぎゅうっと苦しくなるくらい抱きしめてくれた。
「このような嬉しいプレゼントを頂いたのは、初めてです・・・」
耳もとで泉水さんの掠れた声がした。
それからしばらく、泉水さんは私を抱いたままじっとしていた。
私も、泉水さんの温かい身体に包まれて、すごく幸せだったから、そのまま身体を預けていた。
泉水さんの優しい雰囲気がゆりかごみたいで、眠ってしまいそうになる。
「今年のクリスマスは、貴女と一緒に過ごす事ができて・・・とても幸せです。」
「私もです。」
私達は、いつまでもそうして抱き合っていた。