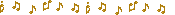
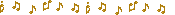
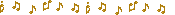
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

記念公園前のバス停を降りて、私は思わず声を上げた。
芝生に続くイチョウ並木が、電飾で飾られていて、とてもキレイ。
彰紋君は、あの時、二人がお互いに気持ちを確かめ合ったベンチに座って待っていた。
「あれから、もうひと月が過ぎたんですね。」
私に気付いた彰紋君は、嬉しそうに言った。
「早いねえ。」
私も言いながら隣に座る。
「はい。幸せすぎて、あっという間でした。」
そう言って、彰紋君は、じっと私を見つめた。
嬉しいけど、恥ずかしくて何て言えばいいか分からない。
私は、耐えられなくて、話を逸らしてしまった。
「姫乃さんは、どうしてる?」
「あれから会っていないので分かりません・・・でも、親衛隊の子から聞いた話では、推薦書にサインを貰ったみたいです。」
「そっか・・・よかったね。」
「はい。」
彰紋君は、にっこりと笑って頷くと、カバンから小さな箱を取り出した。
「クリスマスプレゼントです。」
「わあっ!開けてみてもいい?!」
「どうぞ。」
リボンを解こうとして、私は思わず手を止めた。
このロゴ、見たことある。
「これって・・・ティファニー?」
「はい。」
もしかして、すっごく高いんじゃないのかな?
リボンを解いて、箱を開けると、ブレスレットが入っていた。
小さなハートがいっぱい連なっていて、とっても可愛い。
「可愛い〜!ありがとう!」
「いいえ。気に入っていただけましたか?」
「うん!すごく!」
「良かった・・・あの・・・お願いがあるんです。」
「え?」
彰紋君は、目を丸くした私の手からブレスレットをするりと取ると、私の手首に付けながら言った。
「僕が貴女のそばに居られない時、いつもそれをつけていて欲しいんです。」
「えっ、だって、こんな高そうなの、いつもつけてたらもったいないよ!学校につけてったら失くしちゃうかもしれないし。」
「失くしたら、また買いますから。」
「えっ?」
「すみません。こんなこと言うと、花梨さんに怒られちゃいますね。」
「そ、そうだよ、ものは大事にしないと。」
私は彰紋君の言葉に便乗して口を尖らせた。
だって、彰紋君からのプレゼント、失くしてもいいなんて、酷いよね?
「でも、これだけは、僕にわがまま言わせてください。」
彰紋君がいつになく強い調子で言ったので、私は驚いた。
「このブレスレットを、僕の代わりに貴女のそばに置いて欲しいんです。」
彰紋君が、真剣な瞳で私を見据えた。
私が驚いているのに気付いて、少し恥ずかしそうに地面を見る。
「学校も離れ離れですし・・・僕が、いつも貴女のことを思っているって伝わるように・・・」
彰紋君が、そんな風に思ってくれているなんて、すごく嬉しい。
「・・・分かった。じゃあ、毎日着けることにするね。」
「本当ですか?」
「うん。」
「ありがとうございます!」
彰紋君が、満面の笑みになった。
「その代わり、失くしたらまた買ってね。」
「はい!」
冗談で言ったんだけど、彰紋君は嬉しそうにこくこくと頷いてる。
「もっと高いのおねだりしちゃおうかなあ?」
そう言ったら、彰紋君は、やっと冗談だって気付いたみたいで、クスッと笑った。
「ぜひ、目の飛び出るようなのをおねだりして僕を困らせてください。」
そう言って、真面目な顔になると、続けた。
「僕は、貴女がどんなわがままを言っても、全て叶えられるような大人になりたいんです・・・だから、立派な経営者になれるように、一生懸命がんばります。」
「うん。たくさんわがまま考えとく。」
彰紋君が、あはっ、と笑う。
私も笑いながら、彰紋君へのプレゼントを出した。
初めて編んだマフラー。
ところどころ編み目がばらついてるから、使ってもらえるか心配だけど。
彰紋君がそれを見て、歓声をあげた。
「わあっ、これ、花梨さんが?!」
私が頷くと、彰紋君は、すごい、すごい、と言いながら、嬉しそうにマフラーを広げた。
「不器用だから、上手にできなかったけど・・・」
「そんなことないですよ!」
彰紋君はバーバリーのマフラーを外して、私が編んだマフラーに付け替えると、嬉しそうに言った。
「温かいです!」
「そう?」
「はい、とっても!」
彰紋君はそう言いながらマフラーを外した。
私の肩を抱き寄せると、私の首と彰紋君の首の両方に渡ってマフラーをかける。
「花梨さんみたいに、温かいです。」
彰紋君は、そう言って、私にぴったりくっつくと、ほっぺにキスしてくれた。
私が照れながら彰紋君を見ると、今度は唇に軽くキスをくれた。
「もう少し、このままで居てもいいですか?」
彰紋君がそう言ったので、私は黙って頷いた。
それから、私達は、二人で寄り添って、ずっと公園の電飾を見つめていた。