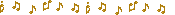
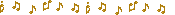
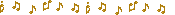
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

日常茶飯事
皆がそれぞれ練習を始めてしまうと、花梨は暇になった。
花梨の歌う曲が決まったのは良いが、これから泉水が楽譜を起こし、それをメンバーが練習して、それから合わせて、その後でやっと花梨の出番が来ることになるのだから仕方がない。
あと2、3週間はこの状態が続くのかな、と思いながらスタジオの片隅で大人しく座って練習風景を眺めていると、彰紋と目が合った。
唇を慣らすためトランペットのマウスピースだけで音を出していた彰紋は、ハードケースからもう1つマウスピースを取り出すと、花梨に近づいてきた。
「つまらないでしょう?」
音の洪水の中で、彰紋が声を張り上げる。
花梨が曖昧な顔をして、首を横に振ると、彰紋が微笑んでマウスピースを差し出した。
「これ、予備ですけど、良かったら使ってください。」
「ありがとう。」
花梨も声を張り上げて受け取る。
彰紋は頷くと、そのまま花梨のそばで音を出し始めた。
花梨もマウスピースを口に当てる。
掠れた音しか出ず、花梨は頬を染めた。
隣で彰紋は、マウスピースだけにもかかわらず音程を変えたりしている。
「やっぱり彰紋君は上手いね。」
「長くやってますから。」
「今度、体育祭でファンファーレをやるの。」
マウスピースを口元に近づけながら彰紋が頷いた。
周りの音がうるさいので、自然に言葉は最小限になる。
「大きい音が出なくって。」
弱めに音を出しながら聞いていた彰紋が微笑んで口を開く。
「やはり、基本はこれです。」
マウスピースを指差す。
「これで芯のある音が出れば、かなり違ってきますよ。」
神妙な顔で頷いて、花梨がもう一度マウスピースを口に当てる。
彰紋はそれを見届けてトランペット本体を取りに行った。
一生懸命、彰紋のような音を出そうと頑張るせいで、だんだん花梨の体に力が入っていく。
戻ってきた彰紋がそれを見て、驚いたように言った。
「花梨さん、力が入りすぎですよ。」
「ふぇ?」
花梨が上気した顔を上げる。
頭に血が上ったせいで潤んでしまった瞳に見上げられ、彰紋は息を飲んだ。
そんな彰紋には気付かず、花梨は力を抜くため深呼吸を始める。
彰紋も軽く頭を振って目をしばたたかせると、トランペットから音を出し始めた。
しばらくトランペットを暖めるため音階などを吹いていた彰紋が息をつく。
隣から、少し上達した花梨の音が聞こえてきた。
「いい音が出るようになって来ましたね。」
花梨が嬉しそうに頷く。
「その感覚を忘れないうちに。」
彰紋は自分のマウスピースをトランペットから外すと、本体の方を花梨に渡した。
驚いた顔をした花梨だったが、感謝を込めて頷くと、持っていたマウスピースを取り付けて音を出す。
彰紋の音には及ばなかったが、花梨にとっては一番いい音が出たのだろう。
花が開いたような笑顔を彰紋に向けた。
彰紋はその笑顔をずっと見ていたいという切ない気持ちになる。
彰紋の顔から笑みが消えたのを見た花梨は、彰紋が練習をしたがっているのだと思ってトランペットを返そうとした。
それを彰紋が制して口を開く。
「感覚を忘れないようにたくさん吹いた方がいいですよ。」
少し申し訳なさそうな顔をして、花梨がファンファーレを吹く。
花梨が吹いているのは旋律ではなかったが、彰紋には何の曲かすぐに分かった。
彰紋も1年の頃、旋律ではない裏方パートをやらされて吹いたことがあったからだ。
どこの学校もウケ狙いは同じか、と苦笑する。
その曲は競馬の出走のときに使われるファンファーレだった。
「彰紋君、お手本!」
何度か吹いて満足した花梨が、無邪気に笑いながらトランペットを彰紋に渡す。
笑顔で受け取ると、そのまま彰紋は花梨が吹いていたのと同じメロディーを吹いた。
その後ろでギターを弾いていたイサトが愕然として固まる。
二人はそれに気付かない。
彰紋の音を注意深く聴いてから、花梨は再びトランペットを受け取って口に付けた。
「あ〜!」
イサトが叫ぶ。
彰紋がギクリとして振り向き、花梨が不思議そうにイサトを見た。
「花梨、お前・・・か、間接・・・キ・・・」
イサトがその続きを言えずに口ごもる。
「あ・・・」
花梨も、いま気付いたというように頬を染めた。
イサトは彰紋と花梨が間接キスをしたと言いたいのだ。
しかし、彰紋は落ち着いた声をイサトに向かって張り上げる。
「吹奏楽部では、こんなの日常茶飯事ですから。」
ねえ、というように花梨を振り向く。
花梨も慌ててこくこくと頷いた。
少し音を低くして様子を見ていた他のメンバーもまた元のように音を出し始める。
「本当かよ?」
イサトが不審そうな目で彰紋を見た。
うっ、と怯みそうになった彰紋も、辛うじて大きく頷く。
花梨は、頬を染めてしまった自分に、日常茶飯事、日常茶飯事、と言い聞かせていた。
しかし、花梨の高校の吹奏楽部は女子生徒ばかりで、花梨にそういった経験はない。
再びトランペットに口を付けようとするが、嫌じゃないのに何故か勇気が要る。
イサトは少し不満そうに再びギターを弾き始めた。
彰紋はトランペットを見つめて逡巡している花梨を見て、笑顔を作ると耳元へ優しく話しかける。
「外で少し休憩しませんか?」
なんとなくいたたまれない気持ちだった花梨は、その提案に頷いた。
スタジオの外に出た彰紋は、狭い階段に腰を下ろした。
ポケットからハンカチを出して隣に広げると花梨を促す。
「そんな、ハンカチが汚れちゃうよ。」
「花梨さんの服が汚れるよりはいいですよ。」
「・・・ありがとう。」
ハンカチの上に花梨が座ると、彰紋と肩が触れ合う距離になった。
男性とここまで密着した事がない花梨は、どうしても肩に意識が行ってしまう。
しかし、ハンカチをずらして離れるのも失礼な気がした。
勝手に頬が染まっていく感覚に、花梨は戸惑っていた。
「この前のメール・・・」
「は、はい!」
花梨が過剰な反応をしたので、彰紋は目を丸くして花梨を見た。
「ごめんね・・・」
花梨がますます顔を赤くして謝ると、彰紋は嬉しそうに微笑んだ。
「いいえ、あの、この前のメールのこと、お話しようと思って。」
「あ、肺活量の事?」
花梨が頬を手で覆いながら首を傾げる。
その仕草を、可愛い、と思いながら彰紋は続けた。
「はい。実は僕、朝ジョギングしてるんです。」
「へえ〜?」
「肺活量を増やすには、有酸素運動がいいって聞いたから。」
「ジョギングって有酸素運動なんだ?」
「はい。息を止めないように、苦しくない程度の全身運動をするのが良いそうですよ。」
「そうなの?有酸素運動って難しい言葉だし、もっと大変なのかと思ってた。」
「一応汗をかく程度は身体を動かした方がいいみたいです。僕は犬の散歩がてら平安記念公園まで走ってます。」
「えっ?犬飼ってるの?」
「はい。」
「犬と一緒に朝のジョギングかあ〜。気持ち良さそうだね。」
「はい、とっても。花梨さんもどうですか?」
「うん。うちから平安記念公園なら、歩いて30分ぐらいだし、やってみようかな。」
「ええ、ぜひ。」
「でも、起きられるかな・・・」
「早く起きられた時だけでも良いと思いますよ。」
「そうだね。」
「うちの菊花にも会わせたいですし、公園まで来る時にはメールください。」
「うん。そうする。菊花って、犬の名前?」
「はい。メスなんです。」
「へぇ〜。可愛い名前だね。」
「花梨さんほどではありません。」
自然に通り過ぎた彰紋の言葉に、うんうん、と頷きかけた花梨は、その意味に気付いて固まる。
「あ、ありがとう・・・」
再び頬を染めて俯いた花梨を見て、彰紋はもう一度、嬉しそうに微笑んだ。