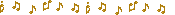
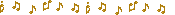
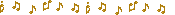
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

王子様
「ふぇ〜、ここが隋心実業かぁ〜。」
花梨が校門をくぐって間抜けな声を出した。
「恥ずかしいから、あんまりキョロキョロしないでね。」
千歳が花梨の腕をつかむと、小声で注意する。
花梨は千歳を誘って隋心実業高校の文化祭に来ていた。
彰紋には来るなと言われていたのだが、花梨はどうしても彰紋の様子が気になって、見に来てしまった。
彰紋が通う高校や、吹奏楽部の様子が知りたかったというのもある。
「演奏見て帰るだけなのに、嫌な思いなんてするはずがないよね。」
「そうね、私もそう思うわ。あっ、あの人ステキ!」
千歳は花梨の事情を知った上で、一緒に来てくれた。
千歳が言うには、花梨の事も心配だが、随心の文化祭にも行きたかったのだそうだ。
随心の吹奏楽部は全国レベルなので前から演奏を聞いてみたかったし、ステキな男子学生と知り合えるかも知れないので、一石三鳥なのだと言う。
千歳って頭のいい人が好みなんだ、と花梨は思いながら千歳の横顔を見る。
ゆっくりと展示や露店を見ながら歩いているように見えるが、その瞳はしっかりと美形の男子を探しているらしい。
頭が良くて美形の男子かあ、と思った花梨の頭に彰紋の顔が浮かぶ。
・・・彰紋君、私が見に来たと知ったら怒るかな・・・
抱えた花束を見つめる花梨の顔が曇った。
教室展示や中庭でのクイズ大会などを一通り見てから、二人は体育館に入った。
女子生徒からビニール袋をもらって靴を入れると、並べてあるスリッパを履く。
中を見ると、体育館の入り口ギリギリまで椅子が並んでいた。
「わぁ、たくさんお客さんが入るんだねえ。」
「本当。うちとは大違いね。」
受付には、演奏会よろしくプログラムが置かれ、クロークと花束受付まで設置されている。
「花束受付ですって。丁度良かったじゃない、花梨。顔を合わせなくて済むわね。」
千歳がそう言って微笑む。
花梨も頷いた。
「うん。助かったよ。まだ持って帰ろうか迷ってたんだもん。」
二人は印刷屋に発注して製本したと思われる立派なプログラム冊子を取ると、花束受付に向かう。
花束受付の女子生徒が、笑顔で対応した。
「お名前と、どなた宛かをご記入ください。」
荷札とボールペンを差し出す。
その時初めて、花梨は彰紋から苗字を教えてもらっていない事に気付いた。
「あの・・・名前しか知らないんです。」
しどろもどろになりながら言うと、千歳が不思議そうに花梨を見る。
女子生徒が笑顔で頷いた。
「お名前だけで大丈夫ですよ。」
花梨がほっとして荷札に自分の名前と彰紋の名前を書くと、それを見た女子生徒が笑顔を消した。
憮然として花束を受け取ると荷札を取り付ける。
「お受けいたしました。ありがとうございます。」
女子生徒は口先だけでそう言って、チラリと花梨を見ると、次の客の対応を始めた。
花梨と千歳は、黙ったままそこを離れると、半分ほど埋まっている客席の中で、なるべく前の方を選んで座る。
パイプ椅子に腰掛けた途端、千歳が冷たく言い放った。
「嫌な思いって、こういうことだったのね。彼、モテモテなのを自覚しているんだわ。」
「そ、そうかなあ。」
花梨が青い顔で首を傾げる。
少なくとも彰紋の様子は、そういう類いの後ろめたい感じではなかった。
「絶対そうよ。」
千歳は静かに怒りを滲ませながら言うと、プログラムを開く。
そこには、部員の顔写真がパートごとに並べられていた。
「花梨、どの人?」
花梨は千歳が開いたページの中に彰紋を見つけて指し示す。
「ふうん、確かにモテモテかもね・・・」
彰紋の写真を眺めていた千歳は、花梨が不安そうに自分の顔を覗き込んでいるのに気付いて、思わず吹き出した。
「花梨、何て顔してるのよ。大丈夫、私、童顔は好みじゃないの。御門彰紋君って言うんだ・・・ニックネームは王子様。甘いマスクから繰り出されるジャジーなハイトーン。今回はソロに大抜擢。」
千歳が花梨をからかうように写真の下の紹介文を読み上げる。
「やめてよ、千歳。」
花梨が頬を染めると、千歳が小気味良さそうにクスリと笑った。
あ、今の顔、勝真さんに似てる、などとのんきな事を花梨が思っていると、今度は肩をすくめる。
「王子様ですって・・・大変な人を好きになっちゃったわね、花梨。」
そう言ってから、はたと口をつぐむと、真顔になって再び口を開く。
「御門って・・・ミカド楽器の御曹司?!」
「えっ?!彰紋君、そんな事一言も言ってなかったよ?」
花梨は首を振ったが、千歳は腕組みをして舞台の方を睨む。
「いいえ、そんなにたくさんある苗字でもないし・・・王子様ですもの。あり得るわ。あなたが名前しか知らないのも、素性を隠したくて苗字を教えなかったからではないの?・・・彼、ちょっと怪しいわね。」
「ま、またまた、千歳、いくら推理小説が好きだからって・・・」
「犯人は、この中に居るわ。」
「い、居ないと思う・・・事件じゃないし・・・」
「いいえ、これは花梨騙し事件よ。」
「しょぼい事件・・・」
「何を言ってるの?あなたは被害者よ?!」
千歳はぐっと拳を作ると、宙を睨んだ。
「この事件は解決するわ。平安団地の名探偵、チィちゃんの名にかけて!」
「そうだったんだ・・・」
花梨が千歳の意外な過去を知って唖然としていると、ブザーが鳴って体育館の明かりが消えた。
「巧妙に隠蔽されたお兄とイサトのいたずらの数々を・・・」
暗い中でなおも話を続ける千歳の言葉を遮るようにマーチが響いてきて、花梨と千歳は目を見合わせる。
舞台の幕が開いて、演奏する部員達が姿を現した。
「新しいわね・・・」
「チューニングなし・・・」
二人がそれぞれ呆然としながら呟く。
千歳が暗い中でプログラムを見て、感嘆の声で言った。
「最初は軽く星条旗ってところね。」
吹奏楽のコンサートは管を暖めるため、楽なマーチから始めることが多い。
歯切れよく整然とマーチが演奏される。
花梨はトランペットを演奏する彰紋をじっと見ていた。
space‐timeでジャズやフュージョンを演奏する時の彰紋は、少し猫背になって激しく吹くことが多いのだが、こうして舞台の上で胸を張って丁寧に音を出す彰紋からは、品格が醸し出される。
王子様かもね・・・と花梨が見とれていると、千歳が呟いた。
「あのピッコロ、上手いわね。」
曲が中盤に入り、ピッコロソロの部分になっていた。
ピッコロを演奏している女子生徒を見て、花梨は首を傾げる。
「あれ?あの人・・・」
「花梨、知ってるの?」
「うん、どっかで見たような・・・」
その言葉を聞いて、千歳が再びプログラムを開いて花梨に見せる。
フルートパートの部分を見て、花梨ははっと気付いた。
最初に紹介されている女子生徒は、先日泉水と行った南天音大の演奏会で会った姫乃だった。
「あ、姫乃さんだ!」
「誰?」
「えっとね、音大の先生が開いてるフルート教室に通ってるらしいよ。」
「音大志望って事ね。」
「そうなの?」
「そうよ。音大に入るために、その大学の講師について癖や好みを知っておくのは常套手段よ。」
「へえ・・・」
花梨が感心しながら姫乃を見つめる。
一つのフレーズごとに感情を込めて身体を揺らす、その動きはとても優雅だ。
身体が揺れる度に茶色い髪がサラサラと流れる。
透明感のある美貌も、フルートによく似合っている。
・・・うらやましいなあ、キレイで、才能があって・・・
花梨はしばらく姫乃に見とれていた。
演奏が全て終わると、引退式が始まった。
引退する学生が、一人一人呼ばれて客席に向かい、挨拶をすると、後輩から花束を渡されて、後輩と抱き合ったり涙を流したりする。
「盛大だわ・・・」
「ウチもこのぐらいしてあげた方がいいんじゃない?」
平安高校では、夏休み前に3年生は引退と決められているので、終業式の後に花束を渡すだけだ。
トランペットの3年生の挨拶が終わり、彰紋が花束を渡してしっかりと握手する。
「フルートはちょっと異常ね。」
千歳の言葉に花梨がフルートパートを見ると、花束を持って微笑む姫乃の周りで、後輩達が号泣していた。
「すごい・・・後輩の方が泣いちゃってる・・・」
花梨もあんぐりと口を開けた。
姫乃は余裕の笑みで後輩達の頭を撫でる。
隣にもう一人引退するらしい生徒が花束を持っているが、そちらは暗い顔でポツンと佇んでいた。
花梨は少し違和感を覚えたが、姫乃の人望に、素直に感動する。
「姫乃さん、よく気が回る人だもんね・・・」
「そうなの?」
「うん、私も一回しか会ったことないけど、とても優しくしてもらったよ。」
「美人で優しい姫・・・」
再び舞台を見つめる千歳の瞳がキラリと光った。
姫乃が指揮台の前に進み出て、ブレザーの襟からピンバッチを外す。
彰紋がその隣に進み出て、姫乃からピンバッチを受け取って襟に取り付けると、二人揃って客席へ深く頭を下げる。
客席から拍手が巻き起こった。
次に二人が部員達に向かって頭を下げると、部員達が楽器を持ったまま足を踏み鳴らす。
「王子様、来年度の部長になるみたいね。」
千歳が目を丸くする花梨を肘でつついた。
最後に、3年生の思い出の曲が演奏される。
泣いてしまって楽器を吹けない生徒なども居て、演奏はぐちゃぐちゃだったが、その光景は、とても感動的だった。
全ての演奏が終わり、体育館の明かりがつくと、花梨は慌ててハンカチで涙を拭う。
「もらい泣きしちゃった・・・」
千歳が微笑んだ。
「どうせ出口は混んでいるし、ゆっくりしてから出ましょう。」
そう言うと、再びプログラムを開く。
千歳はさっきの引退式で、姫乃がもう一人の引退する生徒に見向きもしなかったのを見て、引っかかるものを感じていた。
顔写真を見て、プロフィールを読む。
『ニックネームは姫。確かな技術と篤い人望で部をまとめ上げてきた逸材。引退が惜しまれる。』
・・・姫と王子。
部員達が何の理由もなく、そんな風に二人をセットにして呼ぶだろうか。
二人とも怪しいわ、と千歳はプログラムを閉じる。
落ち着いたらしい花梨を促して立ち上がり、出口へ向かうと、まだ人がごった返していた。
場内整理係らしい女子生徒がその様子を見守っているのを見つけて、千歳はそっと近づく。
「すみません。あの、来年度の部長さんになる方、何ていう方ですの?」
恋する乙女の瞳を作り、うっとりと言うと、その女子生徒は憮然として事務的に答える。
「御門彰紋さんです。」
冷たい態度をものともせずに、千歳は続ける。
「ステキな方ですねえ。恋人とか、いらっしゃるのかしら・・・」
その言葉に、女子生徒は薄ら笑いを浮かべると、自慢げに言った。
「居ますよ。お似合いの姫がね。」
キョトンとして千歳の後ろで成り行きを見守っていた花梨が固まる。
千歳が、やっぱり、とため息をつくと、花梨を振り向いて言った。
「あなた騙されてたのよ。」
その言葉に女子生徒が千歳を睨んで吐き捨てる。
「王子様を悪く言わないで下さい。どうせその子も玉の輿目当てでしょ?!」
千歳はそれを聞くと、静かに呟いた。
「やっぱり、ミカド楽器の・・・」
その様子に女子生徒は鼻で笑うと、自慢げに言う。
「あら、知らなかったの?そうよ。王子様はミカド楽器の跡取り息子よ。」
千歳は女子生徒を見据えると、呆れたように言った。
「あなたが偉いわけでもないのに、よくそこまで自慢げになれるわね。」
女子生徒が怒りと恥ずかしさで真っ赤になったのを見てから、背を向ける。
「さ、花梨、行きましょ。もう用は済んだわ。失恋のヤケ食い、つきあってあげる。」
しょんぼりとした花梨を促して歩き出した千歳の背中を、女子生徒の声が追いかける。
「ちょっと待ちなさいよ!」
怒鳴り声に出口で行列を作っていた客が何人か振り向く。
あわわ、と花梨が青くなると、その背後で鈴の鳴るような声がした。
「エリちゃん、どうしたの?そんな大声出して。」
振り向くと、花束とフルートを抱えた姫乃が立っていた。
女子生徒が天の助け、とばかりに泣きつく。
「姫!あの人が王子様の事を悪く言うんです!」
姫乃は怪訝な顔で女子生徒が指差した方向を見る。
呆れた顔で女子生徒を見る千歳の後ろに花梨を見つけて、はっとした顔になった。
「・・・ここでは他のお客様にご迷惑だから、場所を変えましょう。エリちゃん、あとは私に任せてくれる?」
穏やかに言うと、女子生徒に微笑みかけた。
「で、体育館裏ってわけね。」
千歳が挑戦的な声を出す。
姫乃はそれを無視してコンクリートの上に花束とフルートをそっと置くと、花梨に近づいて微笑んだ。
「花梨さん、お久しぶり。会いたかったわあ。」
「ど、どうも、こんにちは。」
花梨がしどろもどろになって挨拶する。
「泉水様の次はアキちゃん?・・・あなたって、おぼこそうな見た目に似合わずやり手なのね。」
姫乃が笑みを崩さずに言う。
「そ、そんなつもりじゃ・・・泉水さんには音大を案内してもらっただけで・・・」
「あら、音大に入るためなら誰でもやっている事ですもの、嘘をつく事ないわ。」
「へ?」
「チョロそうな泉水様を手なずけて、恵先生に気に入られれば、合格間違いなし、でしょ?」
「・・・・・・」
笑顔のまま恐ろしい事を言う姫乃に、花梨は青ざめて口をつぐんだ。
「芸術家としては最低の部類ね。」
千歳がその隣で吐き捨てる。
「うふっ、何とでも言って。カラダでもお金でも、使えるものは全て使うわ。最後にステージに立っているのは、この私よ。」
姫乃は千歳に満面の笑みで答えた。
そうだ。
その位の野心がなければ、プロとして、やっていけないのかもしれない。
でも・・・この悲しい感じは何だろう。
花梨がそこまで思った時、背後で彰紋の声がした。
「姫!何をしているんですか!」
「あら、アキちゃん、どうしてここが分かったの?」
「あなたが時々ここに部員を呼び出して従わせているのは知ってましたから。親衛隊の子達が探していましたよ。何も、こんな最後の日まで・・・」
そう言いながら、花梨の方を見た彰紋が、愕然とした。
「か、花梨さん!」
花梨は申し訳なさそうに、ぺこりと頭を下げる。
「ごめんね、彰紋君。内緒で見に来ちゃったの。」
「謝る事ないわ、花梨。彼はあなたのこと騙してたのよ。」
千歳の言葉に、全てを理解した彰紋は、苦い顔になって地面を見つめた。
「弁解しないのね。」
「はい。結果的にそういうことになってしまったのは、僕が悪いからです。」
千歳と彰紋がしっかりと視線を合わせる。
そこへ姫乃があっけらかんと口を挟んだ。
「アキちゃん、花梨さんのこと好きなんでしょ?いいわよ、別れても。そのかわり、あなたのお父さんから恵先生に言ってもらう件、お願いね。」
「・・・・・・」
彰紋が再び地面を見つめた。
事情を飲み込んだ千歳が、珍しく怒りを露にした顔で姫乃を見る。
突然、花梨がつかつかと姫乃に歩み寄ると、いきなり平手打ちを食らわせた。
「あなたみたいな人に音楽を演奏する資格はないです!」
頬を押さえた姫乃が、初めて笑顔を消す。
「分かったような口を利かないで!」
そう言って叩き返そうと姫乃が振り上げた手を、彰紋が走り寄って押さえた。
「姫!やめてください!僕、父と話します。だから・・・これ以上・・・もう、やめて・・・」
言っている内に彰紋の肩が震えて、言葉に詰まる。
その背中に、花梨が穏やかな声をかけた。
「彰紋君・・・それは優しさじゃないよ。姫乃さんが間違ってると思うなら、間違ってるよって、言ってあげなくちゃ。」
「花梨さん・・・」
振り向いた彰紋の瞳から涙がこぼれた。
姫乃を押さえていた手を離して涙を拭うと、姫乃に向かって静かに話しだす。
「姫、僕はあなたのフルートが大好きでした。入学式の後の部活紹介であなたの演奏を初めて聞いて、僕はどんなに感動したか、あなたは知らないでしょう?」
姫乃は感情を押し殺したような顔で、黙って彰紋の言葉を聞いている。
「だから、あなたが夢をつかむためのお手伝いは、何でもするつもりでした。あなたを泉水さんと恵先生に紹介させるため僕に近づいたのだと分かってからも、それであなたの夢がかなうなら、と思ってました。」
「アキちゃんの得意なきれいごとね。」
姫乃がうんざりしたような顔をした。
「そう、きれいごとです。僕はそんな事ばかり考えてたんだ。自分を騙して・・・あなたに騙されたふりをして・・・結局あなたも騙して・・・花梨さんまで・・・」
自分を責めるように紡がれる彰紋の言葉に、姫乃が少しだけ眉を上げる。
「花梨さんに出会って、僕はそのきれいごとも、あなたの信念も、どちらも間違っている事に気付きました。花梨さんは音楽を素直に楽しむ人です。その素直な表現に、見ている人は皆、惹かれてしまう。花梨さんの歌のとりこになってしまう。そして気付いたんです。音楽を表現することに、僕のような理論も、あなたのような策略も必要ないんだって。」
彰紋が同意を求めるように花梨を振り向く。
花梨は励ますように大きく頷いた。
それを見て、彰紋が再び姫乃に向き直る。
「姫・・・あなたの演奏は、温かみを失ってしまいました。恵先生についたお陰で、技術力は高くなったかも知れません。でも、僕に感動を与えたあの演奏とは、かけ離れてしまいました。泉水さんを恋人にしようと、僕の父が恵先生に何を言おうと、あなたが昔の心を取り戻さない限り、あの温かい演奏が取り戻される事はないでしょう。思い出してください。あの頃のあなたは、素直に音楽が好きだったでしょう?」
姫乃が青ざめる。
「恵先生が推薦書にサインをしないのは、案外、そこに気付いてらっしゃるからかも知れませんね。」
彰紋が穏やかに言った。
姫乃が自分の肩を抱いて震え出す。
「アキちゃん、私、どうしよう・・・南天に入れなかったら・・・私・・・」
「簡単な事ですよ、昔のように、素直に音楽を楽しめば良いだけのことです。」
「それだけのことで?・・・それだけのことのために・・・私・・・今まで・・・」
姫乃がぽろぽろと涙をこぼす。
彰紋が、ポケットからハンカチを出すと、優しくそれを拭った。
千歳と花梨はそれを見て目を見合わせる。
二人は少し困ったように微笑みを交わすと、静かにその場を離れた。
それに気付いて追いかけようとした彰紋だったが、引っ張られる感触がして自分の胸を見る。
姫乃が彰紋のブレザーをつかんでしゃくりあげていた。
彰紋は、花梨を追うのを諦めて天を仰ぐと、眉間にしわを寄せてぎゅっと目を閉じた。