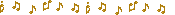
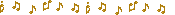
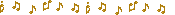
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

ごめんなさい
花梨はバスの中で何度も携帯電話を閉じたり開いたりしていた。
もう一度携帯電話を開いて受信メール一覧を見る。
一番上の受信メールを選択して、もう一度読み返した。
『一昨日は、文化祭に来ていただいてありがとうございました。
姫乃さんの件、お礼とお詫びをさせていただけませんか。
今夜、平安記念公園で待ってます。花梨さんの気が向いたら来て下さい。
aki(^_^)♪』
時間の指定もないし、花梨に用事があるかどうかを聞くつもりもないらしい。
何時間でも待つという意味なのだろう。
バスが平安団地前で停まった。
「じゃあね、花梨。私だったら・・・行かないわ。」
千歳が気遣うように花梨を見ながらバスを降りていく。
花梨は頷くと、小さく千歳に手を振って、携帯電話を閉じた。
花梨は、彰紋と姫乃のよりが戻ったと思っていた。
彰紋に会って、今は姫乃さんとうまくやっています、などと言われたら、さすがの花梨も喜んであげられるかどうか分からない。
平安神社のバス停が近づいてきた。
ここで降りずにいれば、記念公園前のバス停につく。
花梨は、まだ迷っていた。
結局、花梨は記念公園前のバス停に降り立っていた。
何もしないままこの恋を終わらせるのは良くない、と思い直したのだ。
きちんと告白をして、彰紋に断ってもらえば、ひとつの思い出として心に残せるかもしれない。
そう決意すると、公園内に足を踏み入れた。
彰紋は、私服で芝生の上に座っていた。
電灯から離れているので暗くてよく分からないが、片膝を抱えて、足許を見つめているようだった。
花梨が静かに近寄ると、彰紋が顔を上げる。
「花梨さん・・・来て・・・くださったんですね・・・」
彰紋が途切れ途切れに発する声と言葉から、花梨はまだ彰紋が自分を責めているらしい事に気付く。
「彰紋君・・・」
それ以上何を言って良いか分からずに花梨が口をつぐむと、彰紋が立ち上がった。
「明りの下に移動しましょう。貴女のお顔を見ながらお話したいので。」
その言葉で、花梨は彰紋が昼間からそこに居た事に気付いた。
夕方に来たのであれば、最初から明かりの下に居るはずだ。
「彰紋君、今日は学校休みだったの?」
「はい、文化祭の代休で。」
「じゃあ、いつからここに?」
「3時ごろです。」
やっぱり、と花梨は思った。
「長時間待たせちゃって・・・」
花梨が言いかけると、遮るように彰紋が振り向く。
「いえ!自分の考えをまとめたかったんです。花梨さんが部活なのは分かってましたし・・・」
言いながら、電灯の下のベンチに腰掛けるよう促す。
花梨が座ると、彰紋は、その前に立って深々と頭を下げた。
「この間は、ありがとうございました、花梨さん。」
花梨が慌てて立ち上がる。
「そんな、彰紋君、やめてよ・・・」
「それと、本当にごめんなさい。」
花梨の制止も聞かずに、彰紋は、もう一度頭を下げた。
「私、気にしてないから、とりあえず座ろう、ね?」
花梨が一生懸命で彰紋を促すと、彰紋は暗い顔のままでベンチに腰掛けた。
花梨も隣に座る。
「僕の事、軽蔑しないんですか?」
彰紋が俯いたまま、呟くように言った。
「軽蔑なんて・・・どうして?」
「僕は、貴女に隠して姫乃さんとつきあってたんですよ?」
花梨は胸の奥が冷たくなるのを感じながら、冷静を装って静かに言う。
「確かに、びっくりしたけど・・・私の考えは、変わってないよ。」
その言葉を聞いて、彰紋が顔を上げた。
「好きでもない人と、つきあってもいいっていう考えですか?」
「本人同士がそれで良いなら、ね。」
二人が静かに視線を合わせる。
先に目をそらした彰紋が、首を振った。
「今はもう、そんな風に割り切れません。」
「え?」
彰紋は、しばらく足元を見つめていたが、顔を上げると話し始めた。
「僕は・・・姫乃さんのフルートが好きでした。だから、今まで、僕のことを好きじゃない姫乃さんと一緒に居ても、全然平気でした。でも、花梨さんに会って思い知らされてしまったんです。僕が好きなのは、姫乃さんじゃなくて、姫乃さんのフルートなんだって。それから、恋する気持ちと憧れの気持ちは、全く違うものだって・・・」
「え・・・」
「今まで知っていた浮かれたような気分ではなくて、とても切ない、初めての感情・・・それが、恋する気持ちだと知ったんです・・・」
彰紋が花梨を切なげに見つめて続ける。
「その気持ちを知ってしまってから、僕は、それを誤魔化して姫乃さんと付き合っているのが、辛くて・・・苦しくて・・・」
言っているうちに彰紋の瞳が潤み始める。
「彰紋君・・・」
彰紋は目をしばたたかせてから、再び口を開いた。
「今の姫乃さんには、支えとなる人が必要かもしれません。でも、これ以上、自分を騙して姫乃さんの側に居たら、僕、一生後悔すると思ったんです・・・だから・・・あの後、泣き止んだ姫乃さんに、もう会わないって言いました・・・そしたら、姫乃さん、また泣いて・・・私をどん底に落としたまま行っちゃうのって・・・」
彰紋が堪えきれず俯いて涙をこぼす。
「・・・でも・・・僕・・・彼女を・・・置き去りにして・・・帰りました・・・っく・・・僕のせいでみんな不幸に・・・だから・・・軽蔑してください・・・僕のこと、嫌いだって・・・」
花梨は思わずその頭を抱き寄せた。
「彰紋君・・・私はそれが本当の優しさだと思う・・・そのままそばに居たら、また姫乃さんを騙すことになっちゃうもんね・・・」
彰紋はその言葉を聞くと、縋るように花梨に身体を預け、声を殺して泣いた。
「辛かったよね・・・」
花梨はそう言ってふわふわした髪の毛を撫でながら、ハンカチを出して彰紋の涙を拭う。
少し落ち着いた彰紋が、花梨の胸の中で恥ずかしそうに呟いた。
「ごめんなさい・・・こんな・・・僕、貴女に軽蔑されてると思っていたから・・・男らしく好きだって告げて、きっぱりと振られて帰ろうと思ってたのに・・・」
その言葉を聞いて、花梨は思わずクスリと笑った。
「私も・・・姫乃さんとうまくいってるって話だと思ったから・・・告白だけして振られようと思って来たんだよ・・・」
彰紋がゆっくりと身体を起こして花梨を見る。
「花梨さんも・・・?」
「うん。」
花梨が自嘲的な顔で頷いた。
喜びをかみしめるようにじわじわと笑顔になった彰紋だったが、再び顔を曇らせる。
「そうだ、花梨さん・・・僕、もう一つ貴女に謝らなくてはいけないことがあります。」
「何?」
花梨がキョトンとした顔になった。
「貴女に内緒にしていた事があるんです。」
「あ、もしかして苗字?」
「はい。もうご存知ですか?」
「うん。文化祭のプログラムで・・・あと、ミカド楽器のことも、部員の子から聞いちゃった。」
「そうですか・・・ごめんなさい。」
「どうして内緒にしたかったの?ミカド楽器の御曹司なんて、けっこう自慢できる話じゃない?」
「・・・花梨さんにだけは、本当の僕を好きになって欲しかったから・・・」
彰紋が頬を染めて花梨を上目遣いに見ると続ける。
「今思えば、無茶な考えだったんですけど・・・いくら僕ががんばっても、花梨さんが僕の事を好きになるって保証は無いわけだし・・・」
モジモジとブレザーの裾をいじりながら言う彰紋の様子に、花梨は微笑んで言った。
「彰紋君の作戦は成功だと思うよ。もし、彰紋君がミカドの御曹司だって知ってたら、私、こんなに心の深いところで彰紋君のこと好きになってたかどうか分からない。もっと心の浅いところで、簡単に好きになって、玉の輿、とか思ってたかもしれない。」
「花梨さん・・・!」
彰紋が感激の声を上げると、花梨に飛びついた。
「ひゃ・・・」
花梨は彰紋に抱きしめられて、頬を染める。
うっとりとした声で彰紋が花梨の耳もとに囁く。
「嬉しい・・・僕、花梨さんの事、大好きです。もちろん、花梨さんの歌も。」
「私も・・・彰紋君と、彰紋君のトランペット、両方大好き。指輪物語のソロ・・・カッコよかったよ・・・」
花梨の言葉を聞いた彰紋は、少しだけ身体を起こして、赤く染まった花梨の頬に軽くキスをした。