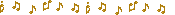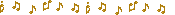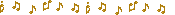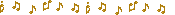
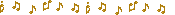
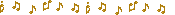
特別コース
「『歌のお姉さんの声楽特別コース』ですって?!まさか・・・!」
いつも温和な彰紋が大きい声を出して、会議室の空気が緊張をはらんだ。
「もちろん、講師は花梨さんにお願いしたいと思います。」
「そんなっ・・・花梨さんはまだ・・・父さんだって知ってるでしょう?!」
他人行儀なままの父親に対し、冷静さを失った彰紋は従業員の前にもかかわらず父親への甘えを滲ませる。
「分かっています。正式決定は出産後で良いでしょう。ですが、できれば来春の生徒募集に間に合わせたい。御門販売部長、この春から教務部長へ移動して新規事業立ち上げの準備にあたってくれませんか。」
あくまで役職名で彰紋を呼ぶ父親に、彰紋はなおも言い募ろうとしていた口を噤んだ。
父親の言わんとしていることを感じ取り、必死で冷静さを取り戻してから口を開く。
「僕のトランペットクラスを増やしてください。そんなに生徒さんを増やしたいなら、個人レッスンに個別指導を導入すれば効率がいいはずです。」
「個別指導は指導の質が下がる分、月謝を下げることになります。新規開講に見合うほどの効率が上がるとは思えません。」
「・・・でしたら社長、僕は販売部でもう少し頑張って楽器の売り上げを・・・」
「具体的な販売プランを出して下さい。」
遮るように言われて彰紋が言葉に詰まる。
泣きそうな顔で俯いた彰紋に、父親は穏やかな声で言った。
「御門販売部長はin the timeとの提携を立案し実現してくれました。信頼性の高いリペアを紹介できるお陰で、高価な楽器を買って長く使おうと考えて下さるお客様も増えましたし、向こうからの紹介で客層も若返っているようです。販売部はもうあなたが居なくても大丈夫です。次は彰紋、教務部の新規事業立ち上げを経験しておいて下さい。少子化のため教務部は今後も経営が難しくなっていくと思います。次々に魅力的な講座を開講できなければ、生徒数も頭打ちになってしまいます。」
今回の無茶な企画と人事異動が、何より父親が息子を思っての提案だということに気付いて、彰紋が力なく首を振る。
「・・・ですが・・・それなら・・・こんなに急がなくても・・・せめて子供が大きくなるまで・・・」
切れ切れに呟く彰紋を、再び父親の穏やかで圧力のある声が遮る。
「このビルは老朽化が進んでいます。私はこれから数年のうちに、最後の仕事としてこの建物を建て替えてから、あなたに社長の職を譲りたいと考えています。ここに居る皆さんも、そのつもりでいて下さい。」
その場に居る全員が息を飲んだ。
従業員たちにとって、社長が初めて経営の譲渡について口にした瞬間だったのだ。
全員がいずれそうなるだろうと分かってはいたものの、こうして決定的になると彰紋へ集まる視線も違うものになる。
彰紋は目を丸くしてから、慌てて反論した。
「数年のうちなんて言われても・・・僕はまだっ・・・結婚したばかりで・・・!」
「夫婦生活が短いからといって経営者になれない訳でもないでしょう、彰紋。」
笑みを含んだ呆れ声で父親が言って、彰紋は顔を赤くした。
玄関を入るとすぐに、小麦粉を揚げた香ばしい匂いがして、彰紋は自然とリビングへの足を速めた。
「おかえりなさい。」
リビングのドアを開ければ、花梨が台所から微笑む。
何度見ても、その光景は安らぐ。
花梨が自分の家に暮らしていて、安らかに微笑みながら迎えてくれる。
それが彰紋にとって、何よりの幸せ。
それこそが、できれば花梨には専業主婦のままでいて欲しい、と彰紋が願う理由の一つでもある。
「・・・ただいま帰りました・・・今日は天ぷらですか?」
微かによぎった先ほどの会議の内容を花梨に悟られないよう、彰紋は努めて明るく言った。
「えへへ、ハズレー。」
花梨が可愛らしく舌を出しながら、対面キッチンを回り込み、ダイニングテーブルに皿を出す。
本人は軽々と歩いているのだが、彰紋から見ればやはり、出産の近い妊婦の立ち働く姿というのは痛々しい。
「あっ、花梨さん、あまり動かないで。」
彰紋は急いでスーツの上着を脱ぎ、ネクタイを外してソファーに投げると腕まくりをした。
「僕が運びますから、花梨さんは食事をよそって下さい。」
過保護すぎる彰紋に慣れっこの花梨は、小さく呆れた笑みを見せて素直に従う。
「はぁい。」
台所に入っていった花梨を見届けて、彰紋は対面カウンターの上に置かれた料理を運び始めた。
天ぷらだと思った匂いは、どうやら魚のムニエルだったらしい。
だが。
・・・アジの開き・・・?
あまりムニエルには見たことのない形状の魚が小麦粉にまぶされている。
首を傾げながらも配膳して、次の皿を手にする。
・・・これは・・・
どう見ても、気持ちが悪くなった人がリバースするアレにそっくりだった。
ふんわり香るミルクの匂いもまた小学校の遠足でバス酔いした記憶を呼び起こす。
花梨の料理はいつもこんな調子で、彰紋は毎日のように食欲を大幅に削がれてから食事にありつくのだ。
最後にオーブンで温めたフランスパンを持って、花梨が嬉しそうに食卓へ座る。
「あー、お腹空いちゃった♪」
先に食卓に着いていた彰紋が貼り付けた笑顔を花梨に返すと、花梨は恒例とばかりに説明し始めた。
「今日のメニューは、カレイのムニエルとレンズ豆のスープなの。」
防衛策のため彰紋が「今日のメニューは何ですか」と毎日のように言っていたせいで、花梨は見れば分かるようなメニューも説明するようになっていた。
「わあっ、それは美味しそうですね。早速いただきます。」
心中で小さく詫びながら、彰紋はフォークとナイフを手にする。
「いただきます。」
花梨もニッコリ笑んで、リバーススープをスプーンですくった。
一口食べて、満足そうに頷いている。
「レンズ豆って、鉄分もタンパク質も繊維もタップリなんだって。妊婦には最高の食材だよね。」
「そ、そうですか。」
つい先日も、似たような話でヒヨコ豆の摂取に付き合わされたような気がするが、花梨の料理の救いは一口食べればとても美味しいということだ。
両親に連れられて普通よりは多く美食を嗜んできた彰紋も、ヒヨコ豆だけは美味しく食べられたことがなかった。
だが、花梨はどこで調べてきたのか見た目はチキンナゲットのコロッケにして美味しく食べさせてくれた。
今日のメニューも、勇気を出して食べれば上々。
干物ソテーのようなムニエルも、カリッとフワッとかなり美味しい。
レンズ豆のスープも、リバース的ドロドロ感がまた喉越し良く、疲れた身体に染みる。
毎度のように見てくれに騙される自分が可笑しくなって、彰紋は思わず笑みを浮かべながら夢中で食べていた。
色んな意味で笑顔にさせられてしまう魅力が、花梨の料理にはあるのだ。
花梨もそんな彰紋を見ながら楽しそうに食べていたが、ふと思い出したように口を開いた。
「さっきね、お義父さんが帰り際にうちに寄っていったよ。」
パンを千切っていた彰紋が固まる。
「・・・・・・どんな用件でしたか?」
気持ちの整理を付けてから冷静を装ってももう遅く。
花梨は少し悲しそうに、上目遣いで言った。
「彰紋君は・・・反対なの?」
乗り気だということが明らかな花梨の様子に、彰紋は少なからず驚く。
「ちょっと待って下さい・・・来春からの特別コースの件ですよね?」
「・・・うん・・・会議資料もらったの・・・」
誤解の可能性が打ち砕かれて、彰紋は苦い顔になった。
「・・・やっぱり反対なんだ・・・」
花梨がしょんぼりとした様子で言って、ムニエルにフォークを入れる。
「僕は・・・花梨さんを経営に利用するため結婚した訳じゃありません。」
「ええっ?!そんなこと誰も思ってないよ?!」
花梨が驚きのあまり飛び上がるほどの反応を見せた。
しかし、彰紋は俯いたまま沈黙で答える。
花梨の持っているフォークから、刺さっていたムニエルがスローモーションのようにポトリと落ちて、しばらく静止していた二人の時を動かした。
「ねえ、彰紋君・・・」
花梨がムニエルをフォークに刺し直しながら静かに続ける。
「・・・もしかして、私がそんな風に思うって考えてるの?」
彰紋が息を飲んで顔を上げると、花梨が少しムッとしてムニエルを口に入れていた。
「・・・ごめんなさい・・・あなたの心を疑うつもりはありませんでしたが・・・あなたにそう思われたくないと・・・そう思ってしまいました・・・」
言って、彰紋は再び俯く。
「・・・それに・・・例えあなたがそう思わなくても、あなたを講師として使役することで、他の皆さんにそう思われるのが・・・『ミカドが利用するために迎えた嫁』と、そうあなたが評価されたら僕は耐えられない・・・僕が純粋にあなたを愛して結婚したんだということを、他の誰にも疑われたくないんです。」
憮然としていた花梨の眉間に皺が寄る。
「う〜ん・・・確かに、私がそう思わなくても、外から見てそう言う人はいるだろうけど・・・」
そう言って首を傾げてから、花梨はしばらく考えていたが、ふとお腹に視線を落とす。
「ん?なあに?あんまり考え込んじゃダメ?」
どうやらお腹の子が何かしらの抗議を胎動で表したらしい。
「そうですね・・・大事なママを悩ませてごめんなさい。」
彰紋が苦笑で花梨のお腹に向かって語りかけると、顔を上げた花梨は悪戯っぽい顔で続けた。
「パパもあんまり考え込んでばかりいると、産まれてきてからパンチされちゃうかもよ。」
彰紋が苦笑を深くする。
「はい、肝に銘じます。」
言って、彰紋は気持ちを切り替えようとスープを一口食べたが、あまり上手くいかずに大きくため息を吐いた。
花梨はもともと悩まない方だが、胎動を感じるようになった頃から輪をかけて楽天的になった。
きっと、こうして子供に励まされ、母親は強くなっていくのだろう。
それに引き替え、自分はまだまだ強い父親になれていない。
再び思案顔でパンを食べ始めた彰紋を見て、花梨は困ったような笑みになる。
「彰紋君・・・私ね、歌が好きなの。」
急に分かり切っていることを言われたので、彰紋がキョトンと頷いて続きを促した。
「子供が産まれてからも、歌と関わって生きていきたいの。」
花梨の言わんとしていることを徐々に理解し始めた彰紋が、パンを持ったまま固まる。
「子供が大きくなったら歌と関わる仕事に復帰したいって、ずっと思ってたから、お義父さんの話を聞いてすごく嬉しかったの。だって、歌に関わる仕事がそのまま愛する夫を助ける仕事になるなんて、最高の一石二鳥じゃない?」
花梨はそこで言葉を切ると、お腹に向かって、だよねぇ、などと同意を求めてから、笑顔で続けた。
「来年の春っていうのは考えてたより早いけど、赤ちゃんはレッスンの間だけお義母さんに預けたりして・・・うん、きっとできるよ。家族みんなで協力して、ミカド楽器を良くするために頑張ろう?」
「花梨さん・・・」
明るく言う花梨と裏腹に、彰紋の表情は未だ冴えない。
それを見た花梨は小さく考えてから、今度は悪戯っぽい顔になって言った。
「やっぱりミカドのために頑張るのはやーめた。私、歌いたいだけなんだもん。歌の仕事をして頑張ってる姿を、子供に見せたいだけなんだもん。レッスンの回数も、子育てに支障がないようにワガママ言わせてもらいます。それで良いですか、御門教務部長?」
ぷっ、と彰紋が泣き笑いのような顔で吹き出す。
「はい・・・鋭意努力させて頂きます。」
花梨は彰紋に少しだけ元気が戻ったのを見ると、独りでウンウンと頷いて納得し始めた。
「うん、そうだよ。私はミカドのためじゃなくて、歌が好きだから講師になるんだもん。利用されてる嫁だなんて、誰にも言わせない。今までだってそうだったもの。歌が好きだっていう気持ちだけで、たくさんの子供達が笑顔になってくれたんだし。私の「歌が好き」っていう気持ちは、彰紋君の愛だって証明しちゃうんだから!」
むん、とガッツポーズを見せる花梨に、彰紋は真面目な顔で言った。
「ええ、本当に、その通りかも知れません・・・高校生だった僕の価値観を変えてくれたのも、あなたの歌に対する情熱でした・・・そうですね、僕、頑張ります。あなたへの愛を証明できるよう、あなたの歌が好きだという情熱をかけて新規講座を立ち上げることにします。そうさせて下さい、花梨さん・・・いえ、御門先生。」
「うん!ヨロシクね!・・・イタっ!」
Vサインで破顔していた花梨が、急にお腹を押さえる。
彰紋が緊張の面持ちで腰を浮かしたが、花梨は目を丸くして言った。
「・・・赤ちゃんも大賛成みたい。」
どうやら大きな胎動があったらしい。
どっと緊張が解けて座り込んだ彰紋に、幸せな笑いが込み上げる。
彰紋を皮切りに起こった二人分の笑い声は、それからしばらく続いた。