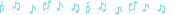
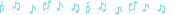
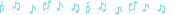
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

紙一重
「遅かったねえ!」
「ああ、帰るタイミング失っちまって・・・」
「勝真さんて、なんだかんだ言って要領悪いよね。」
「余計なお世話だ。」
勝真はそう言いながらダイニングに入って、何か揚げものをしている花梨に軽くキスをする。
「おかえりなさい。」
「ただいま。美味そうな匂いだな。」
花梨が持っているバットを勝真が覗き込む。
「なんだこりゃ?コロッケに出ベソがあるぞ。」
「出ベソコロッケかあ、いいネーミングだねえ!こんど作詞家の人に言ってみよっと。」
「そうじゃないだろ・・・コラ。」
勝真が花梨の髪の毛をくしゃくしゃとかき回す。
「やあ〜っ、ごめんなさい、ごめんなさい!」
「まったく・・・いつまでたっても料理は上手くならないんだな・・・」
髪の毛をくしゃくしゃにしたまま、花梨がしゅんとした。
「ごめんね・・・どうしてもバクハツしちゃって・・・」
勝真が苦笑すると、花梨の後ろに立ち、両手で胸を揉みながら耳もとに囁く。
「でも、不思議と味はいいんだぜ・・・お前と一緒で・・・飽きない・・・」
「やん・・・危ないよ、揚げ物中に・・・」
「へいへい。」
勝真はネクタイを緩めながら花梨から離れると、寝室に行ってジャージに着替える。
「タイラさんちのコロッケは〜♪ポンと出ベソで味がいい〜♪」
ダイニングから花梨のでたらめな歌が聞こえてきた。
いつものことなので勝真は聞き流していたが、ふと考える。
思えば、ずいぶん贅沢だ。
子育てをする親の間で絶大な支持を得ている花梨の歌を、でたらめとは言え独り占めしているのだから。
熱狂的なファンが夫であれば、漏らさず録音しているかもしれない。
そう考えながらダイニングに戻ってくると、花梨がテーブルに皿を置きながら、心配そうな顔をした。
「どうしたの?」
「ん?変な顔してたか?」
「うん・・・すごく辛そう。最近、たまにそういう顔するから、ちょっと心配・・・」
「最近・・・」
思い当たる事があって、勝真が再び辛い顔になると、花梨は炊飯器を開けながら言った。
「話してくれると嬉しいな・・・きっとお仕事のことだからダメなんだろうけど・・・」
その寂しそうな後姿を見ながら、勝真は冷蔵庫を開ける。
「すまない、心配かけて・・・」
言いながら、発泡酒の缶を5本出した。
花梨が茶碗にご飯をよそいながら首を振る。
「ううん、勝真さんは、私が家事とかおろそかにしても好きなように仕事させてくれるから、何かしてあげられたらって、いつも思ってるの・・・心配ぐらいは、させて。」
勝真は、黙って椅子に座ると発泡酒を開ける。
花梨がテーブルに勝真の分の茶碗と箸を置くと、5本置いてある缶のうち3本を取り上げて戻っていく。
「あ、おい・・・」
「勝真さんの身体も心配!この間、千歳に怒られちゃった。初めての人間ドックで肝臓と血糖ひっかかるなんて、甘やかし過ぎだって。」
憮然とした顔で言いながら、花梨が缶を冷蔵庫にしまう。
勝真はため息をついてうな垂れてから、持っていた発泡酒を煽った。
「くーっ!」
冷たい発泡酒が空っぽの身体に染み込んで、勝真が声を上げる。
「オジサンくさ・・・」
花梨が呟きながら自分の茶碗と箸を持ってくると、勝真の向かいに座った。
「いただきます。」
「いただきます。」
二人でぺこりとおじぎをして、箸を持つ。
「今日、幸鷹と電話で話した。」
「え?!幸鷹さんと?元気そうだった?」
ソースを取り皿に出しながら、花梨が顔を輝かせた。
「ああ。相変わらずバリバリ仕事してるみたいだな。」
「へえ〜カッコイイ〜。ドラマみたいに『東京地検特捜部の者です』とか言っちゃうのかな〜?」
ムッとしながら、勝真が花梨からソースを受け取ってコロッケに直接かける。
「俺だって『警視庁少年育成課の者です』だぞ。」
「え?そんなの聞いた事ないよ?聞いたことあるのはね、『警視庁湾岸署』と・・・」
「そんな署はない。」
「なに怒ってるの?もしかして妬いてるのぉ〜?」
花梨が熱いご飯を口に入れて、はふっと笑う。
「な・・・何年夫婦やってると思ってるんだよ・・・妬くわけないだろ・・・」
「もう、素直じゃないんだから・・・幸鷹さんと結婚してたら、もっとラブラブだったかもなあ・・・」
もっとラブラブってどんな状態のことを言うんだよ、と思いながら、勝真がコロッケを齧る。
「ん、美味い。」
仏頂面のまま、小ぶりのコロッケを一気に口の中に詰め込む。
花梨が面白がってなおも続ける。
「私、ホントは幸鷹さんのこと、けっこう好きだったんだよ・・・バンドのリーダーで、いろいろ優しく面倒見てくれたし・・・」
「・・・ふぉう・・・」
冗談じゃない、と勝真は言おうとしたが、頬張っていたコロッケが口から出そうになって慌てて口をつぐむ。
「勝真さん、汚い・・・」
花梨が軽蔑の眼差しで見ながら、コロッケを取ると、とり皿のソースにつけて齧る。
勝真は慌てて発泡酒でコロッケを流し込むと、口を開いた。
「・・・じゃあ、なんで俺とつきあったんだよ?」
「だって・・・勝真さん強引だったし・・・流されてるうちに幸鷹さんよりも好きになってたっていうか・・・」
花梨が頬を染めて上目遣いで勝真を見る。
こういうところは10年経っても変わらない。
「・・・ふーん・・・」
ナイス20歳の俺、と思いながら勝真は冷静を装って味噌汁をすする。
「やっぱあれだよね、あの無理やりチューでクラッときちゃったんだよ。ドラマみたいだったもん。」
「ファーストキスが台無しだからやり直せって言ったくせに。」
「だ、台無しとは言ってないよ・・・多分・・・」
「そうだっけ?」
「言ってない!絶対!」
「さっき、多分て言っただろ。」
「今、思い出したの!」
膨れる花梨に苦笑しながら、勝真は思っていた。
もし、自分があの時、キスをためらっていたら、花梨は幸鷹の妻になっていたかもしれない。
「・・・紙一重か・・・」
思わず漏れた言葉に、花梨がキョトンとする。
「何が?」
「もしかしたらお前が幸鷹と結婚してたかもしれないって思ってさ。」
「そうかな・・・?」
「そうだよ。お代わり。」
勝真が偉そうにご飯と味噌汁の碗を突き出すと、花梨が首を傾げながら立ち上がって受け取る。
2本目の缶を開けながら、勝真は再び苦い思いに囚われていた。
ご飯と味噌汁を持って戻ってきた花梨が、そっと勝真の前に碗を置く。
勝真が顔を上げると、花梨が少し寂しそうな顔をしていた。
辛そうな顔、とやらになっていたのだろう、花梨にそんな顔をさせているのが自分である事に、無性に腹が立つ。
コロッケにぷすりと箸を刺してから、勝真は息を深く吐いて話し始めた。
「この間さ・・・」
「待って、無理にお仕事の話しなくていいの・・・」
椅子に座りながら、花梨が泣きそうな顔になった。
「いや、俺が聞いてほしいんだ。」
花梨が泣きそうな顔のまま頷く。
「この間、一斉補導があったの、知ってるか?」
「うん。勝真さんが帰ってこなかった日に、ニュースでやってた・・・やっぱり、来年移動をお願いした方がいいんじゃないかな・・・勝真さん優しいから・・・自分を見てるみたいで、身につまされちゃうんでしょ?」
「いや、そういう話じゃないんだ。まあ、確かに、機動隊よりかは嫌なもん見せられる事が多いけど、ワルガキの考えてる事なんか、手に取るように分かるからな。むしろ俺には向いてると思う。」
花梨がホッとした顔になった。
勝真がコロッケを齧りながら続ける。
「その一斉補導の時にさ、昔の女に会ったんだ。」
味噌汁を飲みながら聞いていた花梨が、顔を強張らせる。
「・・・中学生に売春斡旋してた。」
花梨が息を飲んだ。
「それから時々考えるんだ。俺も紙一重でそうなってたかもしれないってさ・・・」
「どういうこと?」
「俺もお前に出会わなかったら、身体で金を稼ぐなんてことを、平気で小娘に教えてたかも知れないってことだよ・・・いや、むしろ買う方だったかもな・・・」
勝真が眉間にしわを寄せて発泡酒を飲み干すと、残った味噌汁をザバッとご飯にかける。
「そんなことないと思うけど・・・」
いつもは、勝真さんお行儀悪い、とブーブー言う花梨だが、今日はそれには触れず首を傾げる。
「そんなことある。セックスが身体だけじゃなくて心も繋ぐものだって教えてくれたのはお前なんだからな。あの頃は、俺もあいつも、ただ気持ちよさを求めてただけだった。多分、あいつは、お前みたいな相手に出会えなかったんだ・・・」
そう言うと、勝真はズルズルと味噌汁のかかったご飯をかき込んだ。
花梨がキャベツにソースをかけながら、頬を染める。
トン、と音を立てて空の茶碗を置いた勝真が続けた。
「お前にあの時キスしなかったら、俺は犯罪者で、お前は幸鷹の嫁さんだったと思うと、怖いんだよ。紙一重で俺は幸せになったけど、お前にとってはどうだったのか・・・他の誰かを不幸にしていないかってさ・・・ごっそさん。」
箸を置くと、ふうっと息をついて腹をさする。
キャベツを食べながら黙って聞いていた花梨だったが、急にしかめ面をした。
「勝真さん、キャベツも食べなきゃダメ。こんな時間にいっぱい早食いしたんだから、消化を助けるもの食べないと。」
勝真が渋々箸を持ってソースのかかったキャベツをつまむ。
「勝真さんがキャベツを食べなかったことが原因で、紙一重で死んじゃうかも知れないんだから・・・そしたら、私、不幸だよ。」
「俺はもっと重い話をしたつもりだったんだけどな・・・」
勝真が情けない顔をしながら、もりもりと残ったキャベツを頬張る。
花梨は何故かニコニコしながら最後の味噌汁を飲み干すと、皿をまとめて台所に下げ始めた。
キャベツを食べ終えた勝真は、椅子から立ち上がってリビングへ移動すると、テレビをつけた。
ソファーに身体を沈ませてリモコンを操作する。
テレビ画面に表示された番組表の中から1時間前に放送されていたニュース番組を選ぶと、再び考え始めた。
少し前から、そろそろ子供が欲しいと思っている。
しかし、それは、花梨にとって不幸なのではないかと思うと、なかなか言い出せない。
花梨にとって、今は一番仕事が楽しい時だろう。
それを辞めさせるのは気が引ける。
子育てを手伝いたい気持ちは十分あるが、友人の結婚式でも休めないような稼業だ。
多分・・・保育園の送り迎えさえもままならない。
花梨を一人子育てに縛り付けてしまう事になる。
花梨がお茶の入った湯呑みを二つ持ってきて、片方を勝真に渡すと隣に座った。
また辛そうな顔を見られてしまった、と勝真が慌てて顔を上げると、花梨は寂しそうな顔ではなく、何故か微笑んでいた。
ダイニングから食洗機の水音が微かに聞こえてくる。
勝真がお茶を一口飲むと、湯呑みをミニテーブルに置いてから不思議そうに花梨を見る。
花梨も湯呑みを置いて、微笑みながら口を開いた。
「私は勝真さんで良かったと思ってるよ。今、とっても幸せ。それでも怖い?」
勝真がはっとした。
・・・そうだ、この言葉が欲しかっただけだ、俺は・・・
勝真はゆっくりと首を振る。
「いや・・・お前にそう言ってもらえれば、それでいい・・・他の奴等の不幸なんて、どうでもいいんだ・・・」
「やっぱりね・・・」
何故か花梨がニコニコしながら続ける。
「よく覚えておいて。今までも、これからも、勝真さんが幸せなら、私も幸せだよ。」
「これからも・・・」
「うん。」
「俺が子供欲しいって言ってもか?」
花梨が目を見開く。
勝真はそれを見て、しまった、と思った。
しかし、花梨は瞳を潤ませて勝真の胸に飛び込んできた。
「嬉しい・・・その言葉、待ってたの・・・」
「・・・え?!」
勝真が目を丸くする。
テレビからワッと歓声が湧いた。
勝真が驚いてテレビを見ると、ホームランのボールが客席スタンドに吸い込まれていくのが映っていた。
腕を伸ばしてテレビのリモコンを押すと、興奮して喋るスポーツキャスターの映像がプツンと消える。
胸に顔を埋める花梨の頭を撫でると、花梨がグス、と鼻をすすった。
「お前も、欲しかったのか・・・」
「うん・・・」
くぐもった涙声が聞こえてくる。
「何で言ってくれなかったんだよ・・・」
「だって、私が欲しいって言ったら、勝真さん絶対イヤだって言わないもん・・・勝真さんが、本当にお父さんになりたいと思った時に産まれてきた方が・・・子供も幸せだから・・・」
勝真は花梨の配慮に平伏したい気持ちになる。
「でもお前、仕事・・・」
「いいの・・・自分の手で育てたいから辞める・・・勝真さんが応援してくれたお陰で夢はかなったし・・・収録で忙しくてほとんど家事できなかったのに、勝真さん黙って全部やってくれた・・・」
そう言ってから、涙に濡れた顔を上げて続ける。
「あ、でも・・・余裕ができたらレコーディングだけ復帰するかも・・・CDが思った以上に売れてて・・・」
「そうしてくれ。これ以上、お前を独り占めするのは、マジで怖い。」
「なんで?」
幸せすぎてだよ、と心の中で言いながら、勝真は花梨から視線を外して口を開く。
「・・・いろんな奴等に恨まれそうだからだよ。」
「そんなことないのに・・・」
花梨は再び勝真の胸に顔を埋める。
勝真は言えなかった言葉の分、強く花梨を抱きしめて、髪の毛にほお擦りをする。
花梨がくすぐったそうに笑うと、勝真を見上げた。
「やっぱりいい事があった・・・勝真さんのブルー年が来たんだね。」
「ブルー年?」
「うん。勝真さんね、3年に一回ぐらい、こういうことで悩むの。気付いてた?」
「いや・・・」
「うるう年みたいに一定で来るから、ブルー年。」
「そんなことあったか?」
「この前はね、千歳の結婚式の前。その前は、私にプロポーズする前。両方とも、俺はこんなに幸せでいいのかって、悩んでた。でも、それが解決すると、必ずいい事があるんだよ。きっと、勝真さんが幸せに向かって一歩踏み出すから・・・今回もそうでしょ?」
言われてみれば・・・と勝真がその時の事を思い出す。
呆然と回想に入ってしまった勝真に、花梨がクスリと笑う。
「その度に、私は勝真さんが幸せなら幸せだよって励ますんだけど・・・3年ぐらい経つと忘れちゃうの?」
「・・・そう、かもな・・・」
花梨がクスクス笑いながら、なおも呆然としている勝真の膝の上に乗って首の後ろに腕を回す。
「でも、嬉しいの・・・何度も繰り返し、自分は幸せすぎる、なんて悩んじゃう勝真さんが・・・それと、『私は幸せだよ』っていう言葉が、その悩みを解く鍵なのも・・・」
言いながら、勝真に軽くキスをする。
「私、紙一重が勝真さんで、本当によかった。」
「ありがとな・・・花梨。」
勝真が幸せそうにため息をつくと、少し長いキスを返す。
一旦唇を離した二人だったが、真顔で見詰め合ってから堰を切ったように再び唇を寄せ合う。
激しく唇を貪りあいながら、二人はもつれるようにソファーに倒れこんだ。