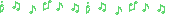
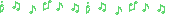
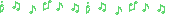
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

援助します
風呂から上がった花梨は、リビングでアイスクリームを食べていた。
網戸から入った風が通り抜ける。
思ったよりも風が涼しかったので、花梨は身をすくめた。
「もうすぐ、アイスなんか食べられなくなっちゃうんだよなあ。」
アイスクリームを一口食べると、味わうように目を閉じる。
「一年中食べてるくせに。」
花梨の弟が飄々とした顔で言いながら花梨の後ろを通り過ぎた。
右手には、最近穿きはじめたトランクスを自慢げにぶら下げている。
「そんなことないもん!」
花梨は弟の背中を睨みつける。
「携帯鳴ってたぞ。」
花梨の弟は、振り返りもせず風呂場へ入っていった。
「生意気なやつ!」
花梨は吐き捨てると、携帯を取りに行こうと腰を浮かしたが、アイスに視線を落としてから、また座りなおした。
「とりあえず味わおうっと。」
部屋に戻って携帯電話を見ると、弟の言う通り、着信を表すLEDが点滅していた。
「店からだ!」
土曜日のシフト調整をしてくれたのだろうか。
思わずベットの上に正座して携帯の通話ボタンを押した。
「はい!オレンジブロッサムでございます!」
すぐに聞き覚えのある声が元気よく応答する。
「お疲れ様です。高倉ですけど店長居ますか?」
「あ、花梨ちゃん、お疲れ様。今、替わるね。」
「お願いします。」
間延びしたミッキーマウスマーチがたっぷり2回分続いて、ふいに途切れた。
「やあ、姫君。夜遅くにすまないね。」
耳もとで響く翡翠の声に、花梨は腰の辺りを撫でられたような感覚がしてゾクリとした。
誤魔化すように正座を崩す。
「い、いえ、こちらこそお忙しい時にすみません。」
「ああ、大丈夫だよ。店長室に回してもらっただけだから。」
確かにプライベートの都合でシフトを変更する話は他のバイトの前ではしにくいだろうと思い、少し申し訳ない気持ちになる。
「そうですか・・・。」
「お風呂かい?」
「へ?」
「お風呂に入っていたのだね?」
「ええまあ。なんで分かるんですか?」
「そりゃあ、この時間に電話に出ないとなれば、お風呂か寝てるかどちらかじゃないか。」
「確かにそうですね。」
「お風呂上りの姫君もいいねぇ。」
まるで見ているかのような言い方に、花梨は思わず窓を見る。
しっかりとカーテンが閉まっていた。
「な、な、何を想像してるんですかっ?!」
真っ赤になった花梨が叫ぶと、翡翠の笑い声が聞こえてきた。
「もうっ!だからセクハラって言われるんですよ。」
「いやいや、許しておくれ。私は姫君を怒らせるために電話をしたわけではないのだよ。」
少し真面目になった翡翠の声に、花梨も落ち着きを取り戻す。
「そうでした。」
「ありがとう。」
あっさりと怒りを鎮めた花梨に、翡翠は珍しく真面目な声で礼を言い、そのまま本題に入った。
「昨日言っていた土曜のシフトのことだけどね。」
「はい。」
「日曜の子と代わってもらったよ。それでいいね?」
「はい!ありがとうございます!」
花梨が満面の笑みになる。
「それから、すでにシフトが出てしまっている来週と再来週の土曜日は9時3時にずらして、その次からは日曜にしかシフトを入れないようにしよう。」
「すみません。」
今度は申し訳なさそうな顔になる。
翡翠は、受話器から聞こえる花梨の声で、花梨が今、どんな表情をしているのかが容易に想像できた。
それほど、花梨の声というのは表情豊かなのだ。
そして、花梨の感情も、素直に変化し豊かに現れる。
翡翠はそんな花梨を羨ましく思う気持ちが日に日に増していることに気付いていた。
「いや、謝ることはないよ。姫君が日曜に用事がある場合は、少し稼ぎが減るかも知れない。」
「あ、それは構いません。お小遣いの足しにしているだけですから。」
「そうだね。姫君はブランド物に散財したりはしないタイプだからね。」
「はい。」
「まあ、欲しくなる時が来たら、私が買ってあげよう。」
「またまたぁ。セクハラの次は援助交際ですか?」
花梨が笑いながら返す。
翡翠の言葉を全て冗談として受け入れる体勢が整ったのだ。
「援助交際か。それもいいね。」
「だめですよ。逮捕されちゃいます。」
花梨の可愛らしい言葉に、翡翠は笑みを深くした。
そのままでいて欲しいという気持ちから、訂正はせず話を変える。
「援助ついでに、今度、私とデートしてくれまいか。」
「えっ?デートですか?」
「そうだよ。」
冗談ととっていいのか分からず、花梨はしどろもどろになる。
「だって、あの、デートって、恋人同士が・・・」
「ああ。なんだ、そんなことか。では言い方を変えよう。」
そんなこと、と言われて花梨は少しムッとしたが、翡翠の言葉を待つ。
「試食会に行こう。」
「試食会?」
「そろそろ秋の新作スイーツが出る頃だからね。」
「えっ?新作スイーツ?」
花梨の声が浮き立つ。
翡翠は吹き出しそうになるのを堪えて言った。
「秋の限定メニューの参考にしたいのだよ。」
「でも、それだったらキッチンリーダーを・・・」
「男同士で新作スイーツなど恥ずかしいじゃないか。それに、姫君ぐらいのお年頃の意見を聞きたいしね。」
「そ、そうですか?」
完全に乗り気の声だ、と翡翠はほくそ笑む。
「いくつかの店を梯子することになると思う。甘いものばかり食べるから少し辛いかも知れない。もちろん経費だから奢りだよ。」
「ぜんっぜんつらくないです!行きます!」
堪えきれず翡翠は吹き出してしまった。
「よし、決まりだ。なるべく忙しい休日を避けたいのだが、それは無理なお願いかな?」
「いいえ、少し先ですが、体育祭の代休があります。」
「ああ。9月最後の週だね。」
「なんで知ってるんですか?」
「混雑状況を読むために、近隣の行事は全て把握しているのさ。バイト管理のためにテスト日程もね。」
ここが翡翠さんのすごいところだ、と花梨は思う。
「なるほど。」
「限定メニューは10月から始める予定だから、それならギリギリ間に合うだろう。」
翡翠が独り言のように発した仕事の声は、花梨が尊敬の気持ちを深くするのに十分だった。
「よろしくお願いします。」
思わず頭を下げる。
「こちらこそ。詳しくはまた今度会った時にでも。」
「分かりました。」
「ではね。」
「失礼します。」
「おやすみ。私の白菊。」
「!」
花梨はそのままの姿勢で固まってしまった。
翡翠が紡いだ最後の言葉は、囁くように優しく、添い寝されているような気分なってしまったのだ。
耳からツー、ツーという無機質な音が聞こえてきて我に帰る。
携帯電話の切断ボタンを押して、ため息をつきながら画面を見つめていると、横から声がした。
「オトコだな。」
風呂から上がった花梨の弟がトランクス一丁で腕組みをしていた。
「覗かないでよ!」
花梨は枕を投げて弟の顔に命中させると、慌ててベットから下りて枕を拾い、部屋のドアを閉める。
「ドアを開けっ放しにしとく姉ちゃんが悪いんだぞ!」
花梨の弟が閉まったドアに向かって減らず口を叩くと、急にドアが開いた。
花梨の弟が慌てて走り出す。
その頭に、枕がぼこん、と当たった。