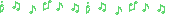
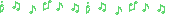
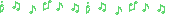
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

愛しい人
「5番と36番の枝豆だけでも、先に上げてくれないか。」
翡翠が涼しい顔をして告げると、両手にビールのジョッキを3つずつ持ってキッチンから出て行く。
日曜日の夜7時。
オレンジブロッサムの混雑状況はピークを迎えていた。
昼はコーヒー中心のメニューが、夜はビールやカクテル中心に変わる。
フロア内は、デート帰りのカップルや、レジャー帰りのグループなどで満席だ。
入り口で席が空くのを待つ客も居る。
「13番と7番のアフターお願いします!」
翡翠と入れ替わりにキッチンへ入ってきた花梨が、そう言いながら料理をトレイに載せると、返事も待たずに出て行く。
「ひえ〜・・・」
茹で上げた枝豆に塩をまぶしながらキッチンリーダーが呟いた。
いつもなら、忙しい時間帯は翡翠がキッチンを手伝うのだが、今日はフロアのアルバイトが少ないのでフロアを手伝っている。
平安高校は先週がテストだったが、今週がテスト期間中の高校が多いらしく、ウエイトレスに高校生のアルバイトが多い翡翠の店は、フロアの人数が揃わなかった。
可愛い花梨に酔客の世話をさせたくない翡翠は、花梨を夜のシフトに入れたがらない。
しかし、今回に限ってはそんな事も言っていられず、渋々11時〜21時の長時間シフトに組み込んだのだった。
花梨は夜のシフトに入ることがあまりないので、酒類の注文の受け方やカクテルの作り方が分からず、料理を運ぶ係を任されている。
5番テーブルと36番テーブルに枝豆を運んで、ぺこりと頭を下げてから、花梨が足早にキッチンへ戻っていった。
酒に酔った男性客のグループが花梨を見てヒソヒソと囁くと、ニヤニヤ笑いあう。
何人かのウエイトレスも、その周りを行き来しているが、なにぶん美人ばかりが揃っているため、幼い容貌の花梨がかえって目立ってしまうのだ。
花梨がキッチンに戻ると、翡翠がカクテルを作るためシェーカーを振っていた。
パーカッションを演奏する時もそうだが、翡翠の動作は一つひとつが洗練されていて、目を奪う。
見とれる花梨に気付いた翡翠は、悪戯っぽい顔でウインクをした。
花梨は頬を染めて目をそらすと、吊る下がった伝票を見ながら料理をトレイに載せ、憮然として呟く。
「もう、翡翠さんてば、この忙しいのに・・・」
その言葉を聞いて、翡翠が満面の笑みを浮かべながらグラスにカクテルを注ぐ。
照れるあまり、店長と呼ぶのを忘れている。
花梨が頬を染めたまま、足早にキッチンから出て行った。
その後姿をチラリと見送ってから、翡翠は手早く別のカクテルを作り始めた。
日曜の夜は客の引きも早い。
翌日に備えて早めに家路につく人が多いからだ。
キッチンから止め処なく出てきていた料理がひと段落したので、花梨は客が去ったテーブルの皿やグラスなどを片付け始めた。
入り口から21時に花梨と交代する予定の短大生が入ってきたのを見て、どっと緊張が緩む。
長時間働いた上、疲れてきた頃に忙しい時間帯を迎えたので、頭の中がゴチャゴチャしている。
突然、隣のテーブルに座っていた男性グループの一人が、振り向いて声を上げた。
「オネエサン、追加!」
花梨が驚いてそちらを向く。
「あ、はい!」
隣のテーブルに座っていたのは、先ほど花梨をみて何やら囁きあっていた男性グループだった。
花梨は、片付け途中のテーブルにトレイを置くと、エプロンのポケットから端末を取り出した。
しかし、酒類の注文が要領よく受けられないことを思い出す。
「少々お待ちください。只今他の者を呼んで参ります。」
花梨がぺこりと頭を下げて踵を返そうとした。
すると、酔った男性客が甘えたような声を上げる。
「ええ〜、オネエサンに言ったのに〜。」
花梨は慌てて向き直った。
「す、すみません。」
仕方がなく端末を開くと、追加注文を受ける態勢になる。
男性客はヘラヘラと花梨を見ながら注文をする。
「えっとぉ。ナマチュー3つ。あとぉ、ジャーマンポテトとぉ、オニオンフライ。」
花梨が端末を操作しながら、耳慣れない言葉に首を傾げる。
「ナマチュー?」
その様子を見て、男性客がフフンと笑いながら花梨を覗き込む。
「オネエサン、知らないの〜?」
「す、すみません。」
花梨が困った顔で謝る。
その様子に気を良くした男性客がいやらしい笑みを浮かべて言った。
「オネエサンのチューのことだよ。チューしてよ〜。」
花梨が目を丸くして、男性客を見る。
次に助けを求めるようにそのテーブルに居る他の客を見たが、全員がいやらしい笑みを浮かべている。
「えっと・・・」
花梨が困り果てていると、その中の一人が堪え切れなくなったように吹き出した。
「オネエサン、カーワイー。」
「生ビール中ジョッキのことでちゅよぉ〜。わかりまちたかぁ?」
「たまんねぇ〜。」
口々に花梨を冷やかす。
花梨は、真っ赤になってぺこりとお辞儀をすると、キッチンに逃げ帰った。
牛乳パックを開けてグラスに注ごうとしていた翡翠が花梨の様子に気付いて眉を上げる。
「姫君、どうかしたかい?」
「い、いえ、大丈夫です。ちょっとお客さんにからかわれちゃって・・・」
そのまま花梨は端末の生ビールを探すと、全ての注文を入力して送信する。
翡翠はそれを見ながら、これがあるから夜シフトには花梨を入れたくなかったのだ、と笑みを消した。
花梨に酔客を上手くあしらうことなどできまい。
初心な反応が、酔客を調子に乗せる事も、翡翠はよく知っていた。
自分のアルバイト管理が至らないせいで、花梨に嫌な思いをさせてしまった。
牛乳の上にコーヒーリキュールを静かに注ぎながら、翡翠は自分を責めた。
花梨は端末を閉じると、先ほど片付けていたテーブルへ戻って再び片付け始める。
「オネエサン、可愛いねぇ。」
「ねえ、デートしてよ。」
口々に声をかける男性客に、ぎこちなく営業スマイルを向けながら、花梨はトレイに皿を載せていた。
翡翠がカルーアミルクを持ってキッチンから出ると、男性客にからかわれている花梨に気付き、苦々しい表情でそちらを一瞥する。
優雅な動作で客の前にカルーアミルクを置いて、花梨を助けようと戻ると、ちょうど花梨がトレイを持ってその場所から離れるところだった。
もう、このまま上がらせてしまおう、と翡翠が思った時だった。
調子に乗った男性客の一人が、背を向けた花梨のお尻を撫でた。
「きゃっ?!」
花梨が驚いてトレイを取り落とす。
皿やグラスの割れる音が盛大に響いて、店内の客が、全員花梨の方を見た。
花梨のお尻を触った男性客は、ばつの悪そうな顔をして、割れた皿を見る。
次の瞬間、翡翠に胸倉をつかまれて、宙に浮いた。
涼しげな顔のまま瞳だけをギラつかせた翡翠の迫力に、男性客の酔いが一気に覚める。
「ひ、翡翠さん・・・やめてください・・・」
花梨の制止も聞かずに、翡翠は男性客の胸倉をつかんだまま、店の外へ出た。
一緒に居た男性客と花梨も、慌てて外に出る。
翡翠は、店内から見えない所まで男性客を連れて行くと、いきなり一撃で殴り飛ばした。
呻きながら起き上がる男性客と、慌てて駆け寄るその仲間達を見下ろすと、腕まくりをしながら低い声を出す。
「私の白菊を辱めた代償は、存分に支払ってもらおう・・・」
全員が震えながらあとずさる。
翡翠が一歩近づくと、口々に助けて、などと言いながら立ち上がって走り出した。
最後の一人が背を向けると、翡翠がその襟をつかんで静かに言う。
「お会計。」
「ひいっ!」
捕まえられた客は、情けない声を上げて財布を出すと、入っている札を全部つかんで翡翠に渡す。
翡翠は、それを受け取ると、襟を放した。
捕まっていた客が慌てて走り去る。
「少し足りなそうだが・・・仕方ない。怪我をさせた治療代としよう。」
そう言いながら札をポケットにしまうと、翡翠は踵を返した。
駅前での大立ち回りに、翡翠の周りには人だかりが出来ている。
翡翠はその中に、震えながら自分を見る花梨を見つけた。
「姫君・・・見ていたのか・・・」
困った顔でそう言いながら近づく翡翠を、花梨は恐怖の混じった目で見つめる。
「どうか怖がらないでおくれ。」
翡翠が自嘲的な笑みを浮かべて言うと、花梨もほっと息をついた。
片足を引きずって翡翠に歩み寄る。
「怪我をしているのかい?」
驚いた翡翠が、屈んで花梨の足を見る。
脛が斜めに切れていて、そこから血が流れていた。
「・・・割れた皿が当たったのだね。」
翡翠が眉間にしわを寄せると、花梨を抱き上げる。
花梨はしゅんとした顔で翡翠の首に腕を回してつかまった。
翡翠が花梨を抱き上げて店に戻ってくると、他のウエイトレス達が、青い顔をして翡翠の周りに集まってきた。
「驚かせてすまなかったね。割れた皿は・・・片付けてくれたのだね。ありがとう。高倉君が怪我をしているから、手当てをする。高倉君にちょっかいを出した迷惑な客には帰ってもらったから、テーブルを片付けて、伝票を店長室に置いておいてくれ。それと、フロアリーダー、店内放送でお客様にお詫びしておいてくれるかい。」
フロアリーダーと呼ばれたウエイトレスが、神妙な顔で頷く。
それを見て、翡翠はにっこりと笑いかけた。
「大丈夫だよ。今の騒ぎについてクレームがあったら、私を呼んでくれ。休憩室に居るから。よろしく頼むよ。」
そう言うと、足早にバックヤードへ入っていた。
休憩室へ入り、椅子の上に花梨を座らせると、靴と、血が染みた靴下を脱がす。
隣の椅子を持ってきて、その上に怪我をした花梨の足を置くと、翡翠は救急箱を取りに店長室へ行ってしまった。
花梨は、自分の傷を見ながら、申し訳ない気持ちになる。
自分のせいで、翡翠や他のウエイトレス達に迷惑をかけてしまった。
静かな場所で一人になった途端、傷がジンジンと痛み始めた。
翡翠が救急箱と、暖かいおしぼりをいくつか持って戻ってきたので、花梨は見上げて情けない声を出す。
「翡翠さん、迷惑かけてごめんなさい・・・」
翡翠は首を振りながら、持ってきたものを机の上に置くと、優しく微笑んだ。
「いや、姫君が謝ることではないよ。」
言いながら、おしぼりのビニールを開けて、少し冷ます。
花梨の前の椅子に座ると、そっと花梨の傷に当てた。
「イタ・・・」
花梨が歯を食いしばって痛みに耐える。
翡翠がそれを見て低い声を出した。
「姫君にこんな痛い思いをさせるとは・・・もう何発か殴っておくべきだった。」
その言葉に、花梨が苦しげに息を吐きながら首を振る。
「ケンカはダメです・・・イタタ・・・怖い翡翠さんは・・・嫌いです・・・」
翡翠は優しく血を拭き取って、おしぼりをたたむと苦笑した。
「しかし、姫君は彼らに辱めを受けただろう?」
「でも・・・殴るほどのことじゃないですよ。ホラ、翡翠さんだって、セクハラするじゃないですか。」
冗談めかして花梨は言ったのだが、翡翠が真顔になる。
花梨がまずい事を言ったかな、と息を飲んだ。
翡翠が花梨から目をそらすと、髪をかき上げながら憮然とした顔で続ける。
「いや、私は姫君のお尻には触れた事がない。私より先に触れるなど、万死に値する。」
花梨が呆れた顔になった。
「翡翠さん、それじゃまるで嫉妬じゃないですか。」
「まるでもなにも・・・100%嫉妬だよ。」
翡翠が花梨を見つめると続ける。
「姫君が他の男に触れられたのを見て、私が正気で居られる訳がないじゃないか。分かっているだろう?」
花梨が真っ赤になって目を丸くした。
「ええっ?・・・わ、分かってないです!」
花梨の反応に、翡翠が盛大にため息をつく。
「まさかとは思っていたが・・・」
恨めしげに花梨を見つめる翡翠の様子に、花梨は頬を染めながらも慌てて釈明を始める。
「だ、だって、他のウエイトレスさんにも同じようにしてるじゃないですか!」
「姫君には区別がついていなかったのだね・・・」
ますます恨めしげな顔をした翡翠だったが、急に吹き出すと、くっくっと笑い出した。
笑いながら、翡翠が降参、という風に両手を上げる。
「姫君には恐れ入ったよ。いや、私が間違っていたと言うべきだね。遠まわしな小細工など、姫君の純粋な心に通用するはずもないのだから。」
そう言って、キョトンとした花梨の顔を覗き込むと、囁いた。
「ねえ、愛しい人、私は心から君の事を愛しているのだよ。分かっておくれ。」
花梨は、翡翠の端正な顔のアップと、背筋を這い上がるような囁き声に身体中が痺れたように動けなくなってしまい、真っ赤な顔でコクコクと頷く事しかできない。
その様子を見て、翡翠は満足そうに微笑むと、救急箱から消毒液を取り出した。
それを見て、赤くなっていた花梨がみるみる青ざめる。
「ちょっと辛いかもしれないね・・・そうだ、こうしよう。」
翡翠は花梨を抱き上げると、膝の上に横向きに乗せ、ご丁寧に花梨の腕を自分の首につかまらせる。
「痛かったら、私にしがみつきなさい。」
にっこりと笑って、消毒液と新しいおしぼりを持つと、花梨の傷口に近づけた。
「ひ、ひすいさんて、やっぱりセクハ・・・ああーっ!」
再び赤くなって抗議しようとした花梨だったが、傷口に消毒液がかかった途端に悲鳴を上げて翡翠に縋りつく。
「いっ・・・たぁーい!」
痛みに耐えるため、ぎゅっと抱きついてくる花梨を受け止める翡翠は、意外にも自省的な顔をしていた。
花梨の髪に頬擦りをして頭を撫でると、こぼれた消毒液と血液をおしぼりで拭き取りながら、口を開く。
「姫君がこんな痛い目に遭うのも、もとはと言えば、私のアルバイト管理が至らなかったせいだ。すまなかったね。」
花梨はその言葉に顔を上げると首を振った。
「痛かったり恥ずかしかったりしたけど、それよりも翡翠さんにもらった言葉の方が嬉しいから、だから、翡翠さんは悪くないです。」
翡翠は花梨の言葉を聞きながら救急箱から包帯を取り出していたが、思わずそれを取り落とす。
花梨は不思議そうに転がる包帯を見送ったが、次の瞬間、翡翠に思い切り抱きしめられていた。
「あ、あの・・・」
真っ赤になって口をぱくぱくとさせる花梨の耳もとに翡翠が囁く。
「キスしてもいいかい?」
「・・・!」
背筋に電流が走って目を見開いた花梨に、翡翠がたたみ掛ける。
「ねえ、愛しい人?」
「ま、待って・・・」
やっとの事で言葉を発した花梨の耳に息を吹きかけながら、翡翠が再び囁いた。
「あんな言葉をもらった後に、待っていられると思うかい?」
再び電流が走り、花梨が熱い吐息を吐く。
「私の花梨・・・」
翡翠がそう囁きながら花梨のうなじに口付ける。
「あ・・・」
花梨が吐息まじりの声を出してピクリと震えた。
その様子に、翡翠は笑みを浮かべながら花梨の顔を覗き込む。
花梨がとろんとした瞳で翡翠を見つめると、ゆっくりと瞼を閉じた。
翡翠が嬉々として顔を近づける。
二人の唇が触れ合う寸前に、休憩室のドアが開いた。
「店長、高倉さんの様子は・・・」
フロアリーダーが言いながら入ってきて固まる。
真っ赤な顔で慌てる花梨が翡翠の膝の上に乗っているのに気付いて、フロアリーダーも真っ赤になる。
「て、店長!何してるんですか?!まったくもう!」
フロアリーダーの怒声が飛んで、翡翠が肩をすくめると、ぺろりと舌を出した。