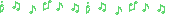
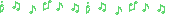
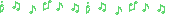
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

人攫い
「おはよう、姫君。」
突然後ろから抱きすくめられ、耳もとに囁かれて、花梨は飛び上がった。
「ひゃあっ、翡翠さん?!」
慌てて振り向けば、翡翠の悪戯っぽい笑顔に見下ろされる。
「よく分かったね。」
「こんなことするのは翡翠さんしか居ませんから、すぐ分かります!」
抱きすくめられたまま憮然とする花梨に、翡翠は笑みを浮かべたまま返した。
「そうだね。他の男が君を抱き締めようものなら、私は何をしでかすか分からないよ。」
「笑顔で怖い冗談を言わないでください・・・」
「おや、私は本気だよ。」
翡翠が大げさに驚いた素振りをするのに対し、花梨も大げさにため息を吐いて見せる。
「本気なら、もっと怖いです。」
言いながら、花梨は身体に絡みついた翡翠の腕を解こうと手をかけた。
「つれないね。それに・・・少しご機嫌も斜めのようだ。」
「そんなことないですよ・・・」
離す気があまりない翡翠の腕を、よいしょ、と抜け出して、花梨は腰に手を当てた。
「・・・翡翠さんは、少し周りもよく見て下さい。」
翡翠が肩を竦めて周囲を見回す。
「特に変わりもない、いつもの駅前だ。」
「そうじゃなくて・・・こんなにいっぱい人が居る場所で、恥ずかしいです!」
花梨が唇を尖らせた。
通学時間帯の駅前は、バスや電車を乗り降りする人でごった返している。
その真ん中で、翡翠は花梨を抱きすくめていたのだ。
「何も悪いことをしている訳ではない。人混みの中から偶然にも見つけた愛しい恋人を、腕の中につかまえただけだよ。」
翡翠が悪びれもせずに言う。
花梨は小さく息を吐いて諦めたような顔をすると、忙しなく時計を見た。
「もう行かなくちゃ。翡翠さん、また・・・」
言いながら視線を翡翠に戻した花梨が固まる。
翡翠が真顔だったからだ。
「花梨・・・」
真顔のまま翡翠は一言そう言って、しばらく黙ったまま花梨を見つめてから、突然いつもの笑みを浮かべて続けた。
「・・・引き止めてしまったお詫びに、タクシーで高校まで送ろう。」
花梨が目を丸くする。
「ええっ?!そんな、まだ間に合いますから大丈夫で・・・」
言いかけた花梨を、翡翠の焦れたような声が遮った。
「いいから。私がそうしたいんだ。さ、行こうか。」
こういう時の翡翠は、他人に有無を言わせない雰囲気を醸し出す。
それは恋人である花梨さえも、他人と同じように操縦してしまう強引さを持っている。
「は、はあ・・・」
花梨は目を白黒させてそう答えると、首を傾げながら翡翠に付き従った。
タクシーが到着したのは、駅にほど近い高層マンションだった。
あまりの近さに運転手は不審な顔をするが、翡翠は何食わぬ顔で財布を取り出す。
そして花梨は困り果てていた。
翡翠がタクシーに乗り込んで高校ではない行き先を告げて以降、花梨はずっと抵抗していたのだ。
だが。
「翡翠さん、やっぱり私・・・」
「おや、まだそんなことを言っているのかい?私には君を無事にご両親まで送り届ける義務がある。無理はしない方が良いよ。ほら、こんなに熱が・・・」
根も葉もないことを言いながら、翡翠は花梨の額に手を当てて顔を覗き込む。
そのまま口付けられそうになり、不審そうにこちらを振り返る運転手に気付いた花梨は、真っ赤になって身を引いた。
「わ、わかりました、降ります、降りますから・・・」
こんな調子で翡翠は花梨をマンションまで連れて来てしまったのだ。
タクシーを見送って、花梨が時計を見る。
「翡翠さぁん、もう遅刻しちゃいますよ〜。」
泣きそうな顔で責める花梨にも、翡翠は余裕の笑みを崩さない。
「またタクシーを呼んであげよう。少し用を済ませてからね。」
ポケットから鍵を取り出すと、スタスタと先に歩き出した。
「ええっ?!」
花梨は背中を向けた翡翠と、自分の時計、そして高校へ続く道を、あたふたと何度も見比べて。
それから、さっさとエレベーターホールに入ってしまった翡翠を、えーん、などと言いって追いかける。
翡翠はそれに気付くと嬉しそうに振り向いて、花梨の肩を抱き寄せた。
「困らせてすまないね・・・どうしても君とまだ一緒に居たいのだよ。」
優しい瞳に覗き込まれて花梨が頬を染める。
それを見て取ると、翡翠は満足そうに笑んでエレベーターに乗り込んだ。
火照った頬を掌で冷ましながら続いて乗り込んだ花梨が、エレベーターの中を見回して言う。
「こんな高級そうなマンションに、何の用があるんですか?」
「内緒。」
くすくす、と翡翠は可笑しそうに笑いながら、手慣れた動作で最上階のボタンを押した。
「もう・・・」
そんな翡翠に、花梨は時計を見てから諦め顔で肩を竦める。
だがその態度は、少しだけ嬉しそうでもある。
恋人と会えないはずの平日を、思いがけなく一緒に過ごしている。
学校のことは気になるが、それ以上に翡翠のそばに居られることが嬉しい。
エレベーターが動き出すと、待っていたように翡翠が身体を屈めた。
サラサラと目の前を零れ落ちる長い髪に見惚れている花梨を、横から熱っぽい瞳が覗き込み、そのまま顔が近づく。
優しく唇を啄まれて、花梨はうっとりと瞳を閉じた。
重力から離れていく密室で、羽が生えてしまいそうな軽いキスを何度も繰り返されて。
最上階に着くまでの短い間に、花梨は学校のことなどどうでも良くなってしまった。
翡翠に手を引かれて、ふわふわとした心地でマンションの一室に入る。
玄関先で待とうとする花梨を翡翠が中へと促して内鍵を掛けたところでやっと、花梨が素っ頓狂な声を上げた。
「ええっ?!ここって、翡翠さんのお家なんですか?!」
翡翠が弾かれたように笑う。
お腹を抱えて笑い続けながら、翡翠は花梨を奥へと促した。
「さ、おいで。」
「えっ・・・ええっ?」
わたわたと周りを見回してから、花梨は仕方なく靴とコートを脱いで上がり込む。
先にさっさと中へ入った翡翠は、鮮やかな動作でコートを脱いでポールハンガーに掛けると、奥の部屋に入ってしまった。
追いかけて行くのもはばかられて、花梨は呆然とリビングに立ち尽くす。
片づいた、と言うより、あまり生活の匂いのしない部屋だった。
テレビとソファ、小さなローテーブル。
奥のダイニングキッチンには、テーブルさえもない。
広い間取りが無駄に思えるほどの、家具の少なさだ。
ソファの前にあるローテーブルには、飲みかけのワイングラスが寂しそうに置かれていた。
奥の部屋では、翡翠が何やら衣擦れの音をさせている。
着替えでもしているのだろうか。
そう言えば、今朝駅で会った翡翠がこうして自宅に戻っている。
きっと、夜勤明けなのだろう。
「待たせてすまないね。」
そう言ってウキウキと奥の部屋から出てきた翡翠は、腕にシーツを抱えていた。
「い、いえ・・・」
キョトンとしたまま首を振る花梨の前を素通りして翡翠はバスルームへ消えて行く。
「ソファに座って少し待っていなさい。」
バスルームから声だけが飛んで、花梨は素直にソファに座った。
すぐに水音がし始める。
「あれ・・・?」
流石の花梨もおかしさに気付く。
二人は恋人同士で。
ここは翡翠の自宅で。
翡翠はシーツを取り替えてシャワーを浴びている。
「え・・・?」
それでも花梨は首を傾げる。
まさか、いくら翡翠でもそんな突然。
自分のことを大切に思ってくれているという自負がある。
「う〜ん・・・?」
だが少し不安もある。
翡翠の行動は本当に読めない。
つい一昨日、ディズニーランドでのファーストキスが濃厚ディープだった前科もある。
そんな翡翠に、あれよあれよと押されて流されてきてしまったような気もする。
それに、今日は平日で皆は学校で。
ガチャ、とバスルームから音がして、花梨は飛び上がった。
そのまま大きな窓まで後ずさる。
窓際でドキドキしている花梨の前に、ざっくりとジーンズだけ穿いて上半身は裸のままの翡翠が現れて、花梨の心臓は飛び出そうになった。
「やあ、お待たせ。」
今まで見たこともないほどニコニコと上機嫌な翡翠に、花梨のドキドキは不安度を増す。
「ひ、翡翠さんっ?!」
花梨が真っ赤になってひっくり返った声を出すと、翡翠は濡れた髪をタオルで拭いながら歩み寄った。
「何かな?」
満面の笑みである。
翡翠は最初からこのつもりだったのだと気付いて、花梨は次の言葉が出ない。
そんな花梨を、翡翠は追いつめるように覗き込んだ。
視線を逸らすため目を伏せた花梨の視界に、逞しい翡翠の胸板が飛び込む。
「ふ、服を、着て・・・くだ・・・」
花梨が震えながら言葉を絞り出すと、翡翠は花梨の顎をつかんで瞳を合わせ、それを遮った。
「もう分かっているのだろう?君は・・・」
花梨が息を呑むと、余裕の笑みを浮かべる翡翠の瞳だけが剣呑な光を帯びる。
「・・・逃げ出すチャンスは何度もあったはずだ。だが、それをしなかった。」
初めて聞く厳しい声と雰囲気に、花梨の眉が八の字になる。
「・・・っ・・・だって・・・翡翠さんが好きだもの・・・信じてるもの・・・」
ぴく、と翡翠は眉を上げると、そのまま黙ってタオルを首に掛け、花梨を軽々と抱き上げた。
「・・・なら、構わないね?」
静かに言って、翡翠は奥の部屋へ花梨を運んでいく。
頷きも抵抗もしない代わりに、花梨がぽろりと涙を零した。
「おっと・・・少し悪ふざけが過ぎてしまったようだ・・・君を悲しませるようなことはしないから、安心したまえ。」
言いながらも、翡翠は花梨をキングサイズのベッドに横たえる。
「ひ、ひす・・・」
小さく抵抗を見せた花梨に、翡翠はいきなり覆い被さり、唇を貪り始めた。
甘く、激しく、優しく、強く。
緩急の差が激しいキスが長く続いて、花梨は翻弄される。
両手はいつの間にか翡翠に優しく握られ、指を絡められ、シーツに押し付けられていた。
脇が空く、それだけで腕の力が逃げてしまって快感に堪えることができない。
満足そうに翡翠が唇を離した時には、花梨はぐったりと茹で上がったようになっていた。
「学校なんて、どうでも良くなってきただろう?こうして永遠に睦み合っていたいと思わないかい?」
悪戯っぽく言いながら、翡翠は身体を起こす。
頭まで茹だってしまった花梨は、翡翠さんの言う通りかも知れない、などとぼんやり思う。
浅い呼吸を繰り返し、答えることもできない花梨。
その身体を跨いで座ったような姿勢のまま、翡翠は目を細めてそれを眺めたが、ふいに花梨の服に視線を留める。
「制服が皺になってしまうね・・・」
独り言のように言うと、翡翠は手際よく花梨のスカートのホックを外した。
花梨がビク、と身体を竦ませたが、諦めたように身体の力を抜く。
それをいいことに、翡翠はスカートを取り去り、上着とブラウスも脱がせてしまった。
下着だけのあられもない姿になって、流石に花梨が腕で身体を隠す。
「綺麗だよ・・・止まれなくなりそうだ・・・」
低く囁くと、翡翠は花梨の隣に横たわり、布団にくるまって花梨を抱き締めた。
「愛している・・・君が大切なんだ・・・君のためなら私は手段を選ばないよ・・・」
吐息交じりの声が、花梨の脳内を甘い蜜のような悦びで満たす。
花梨はうっとりと瞳を閉じて、翡翠に身体を預けた。
幸せな眠りから目覚めて、花梨はギョッとした。
目の前が翡翠の寝顔だったからだ。
しかも半裸で翡翠に抱き締められている。
声を上げそうになり、慌てて翡翠を起こさないよう息を殺す。
だが、その気配だけで翡翠は目覚めたようだった。
「ん・・・よく眠れたかい?」
寝起きの掠れた声が色っぽすぎて、既にパニックの花梨は卒倒しそうになる。
そんな花梨に構わず、翡翠は重そうに身体を起こして一つ気怠い息を吐いてから、あっさりとベッドを降りた。
クローゼットからシャツを出して羽織ると、ボタンを留めながら悪戯っぽく微笑んで部屋の外に向かう。
「もう少しゆっくりしておいで。簡単で良ければランチを作ってあげよう。」
そう言うと、翡翠は部屋を出てドアを閉めてしまった。
流れるような翡翠の動作の色っぽさに見惚れてしまっていた花梨は、そこでやっと我に返る。
がばっ、と飛び起きて布団を捲り、自分の身体を確認してみる。
着衣を、と言っても下着だけだが、脱がされた形跡は、多分、ない。
記憶を遡っても、翡翠に脱がされた覚えはない。
あのまま、翡翠は花梨を抱き締めて、ただ軽いキスを繰り返した。
温かい布団と翡翠の身体に包まれて心地よいキスを受けているうちに、花梨は気持ち良くなって眠ってしまったのだ。
時計を見れば、もう午後1時を過ぎている。
今日が平日であることを思い出すと同時に、さあっと冷や汗が出て、それからすぐに、もう慌てても無駄だと悟って冷や汗が引く。
どこからどう見ても、完璧な、サボりだ。
真面目な花梨は、そんな風に学校をサボった経験などない。
だが、学校をサボるのは悪いことだと思うのに、何故か可笑しくて仕方ない。
翡翠にまんまと一杯食わされた自分が可笑しいのだ。
きっと今ごろ千歳がやきもきしていることだろう。
携帯電話に着信しているであろうメールに、早く返事をしなくては。
花梨はどこか爽快な笑みのままベッドを降りると、制服を着て、軽くベッドを整えてから部屋を出た。
ダイニングキッチンを覗けば、翡翠が卵液に食パンを浸しながら振り向く。
「生憎、冷蔵庫に卵と牛乳しかなくてね・・・」
「わあっ、フレンチトーストですか?!」
花梨が飛び上がらんばかりに喜ぶと、翡翠はニヤリと人の悪い笑みを浮かべた。
「おや、悪い人攫いにお咎めの言葉はないのかな?」
ぷっ、と花梨が吹き出す。
「もう、いいです・・・」
言って、笑いながら翡翠に歩み寄り、その背中に抱き付く。
「・・・本当はいけないことだけど、翡翠さんと一緒なら楽しいです。」
翡翠が心地よい調べを聞くように瞳を閉じて、呟いた。
「そう・・・それでこそ私の白菊だ・・・寒空にもお構いなしで、可憐に明るく花を咲かせる・・・」
「え?・・・何ですか?」
よく聞こえなかった花梨が、翡翠の背中に抱き付いたまま顔を上げる。
翡翠は最後の食パンを卵液に浸してから、花梨に向き直って抱き締めた。
「忙しい毎日のせいで、花が萎れかけていたのだよ。」
「お花が?・・・じゃあ、お水をあげないと・・・」
翡翠の言葉を言葉通りに受け取った花梨が、花を探して周囲を見回す。
素直すぎる花梨の反応にくすくすと笑って、翡翠は花梨の額に軽く口付けた。
「そうだね。それなら今日は、夕方の練習が始まるまでここでゆっくり過ごして行きなさい。」
「へ?」
花梨が首を傾げる。
翡翠はそんな花梨の頬を愛おしむように両手で包み込むと、そのまま引き寄せて深く口付けた。