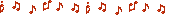
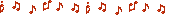
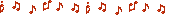
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

一緒に帰ろう
「じゃあね。今日は歌のレッスンでしょ?」
「うん。うちのパートリーダーに伝えといてくれる?毎回ごめんね。」
「いいのよ。また明日ね。」
「バイバイ。」
花梨が手を振ると、千歳も手を振りながら音楽室がある南館の渡り廊下へと歩いて行った。
花梨と千歳は、入学してすぐ、アイウエオ順に並べられた席が前後だったので仲良くなった。
花梨が歌を習っていると聞いて、肺活量が増えるから、と吹奏楽部に誘ったのも千歳だった。
今は一番の親友だ。
花梨は時計を見ながら玄関を出る。
まだレッスンまでは時間があるので、ゆっくり歩くことにした。
他にも帰る学生がまばらに歩いている。
正門前広場に出ると、隅の方で、赤く長い髪が揺れているのが見えた。
イサトだ。
バスケットボールを弾ませながら、何人かの男子生徒と話をしていた。
学生が昼休みなどに利用できるようバスケットが設置してある場所だ。
花梨が声をかけようか迷いながら歩いていると、イサトが花梨に気付いた。
驚いた顔になったが、すぐに笑顔で花梨に駆け寄る。
男子生徒たちは、そんなイサトと花梨を見て何やら囁き合った。
「よお、花梨!」
「こんにちは、イサト君。」
「お前、部活は?」
「今日は歌のレッスンだから。」
「そっか。歌のレッスンてどこでやんの?」
「駅前商店街のミカド楽器。」
「じゃあ、駅まで一緒に帰らねぇ?」
「うん。いいよ。」
花梨が頷くと、すぐにイサトは男子生徒たちの方へ踵を返した。
「わりぃ、やっぱ俺帰るわ。」
言いながら持っていたバスケットボールを乱暴に預けると、芝生の上に投げてあったカバンを持って再び花梨に駆け寄る。
「おい、お前が言い出しっぺだろ。」
バスケットボールを持たされた生徒が口をとがらせてイサトの背中に抗議したが、他の生徒は口笛を吹いたり、口でひゅーひゅー、などと言って囃し立てた。
バッと頬を染めたイサトが、振り返って怒鳴る。
「お前ら、うるせーぞ!」
その様子に、男子生徒たちは、ますます調子に乗って口々に何か言い始めた。
「無視だ無視。花梨、行くぞ。」
イサトは憮然として花梨を促し歩き出す。
呆然と男子生徒たちを見ていた花梨も慌てて歩き出すと、その背中に、ひときわ大きく男子生徒の声が届いた。
「ちゃんとコンドームしろよー。」
男子生徒たちが爆笑して、周りの学生がちらりと二人を振り返る。
花梨が俯いて頬を染めた。
イサトは耳まで真っ赤にすると、拳に力を込めて呟いた。
「あいつら、ぜってー殴ってやる!」
肩を怒らせながらずんずんと歩いていってしまうイサトを花梨も早足で追いかけた。
正門を出て、男子生徒たちから見えなくなると、イサトが頬を火照らせたままで、花梨を振り返る。
「ごめんな。恥ずかしい思いさせて。」
「ううん。」
花梨も頬を火照らせて首を振った。
安心したイサトが歩き出す。
花梨も横に並んだ。
「明日、俺の分とお前の分で2発ずつ殴っとくからな。」
「そんな、いいよ。ちょっと恥ずかしかったけど・・・なんか、男の子同士の友情っていいね。」
「はぁ?そうか?」
「うん。きつい冗談も、ケンカも、ストレートで後腐れないでしょ?」
「まあな。」
「女の子同士だと、どうしても気を遣っちゃうところがあって、例えば私がイサト君の立場だったら、イサト君が通りかかっても、言い出しっぺだし放って帰るのは悪いな、とか思っちゃう。」
「・・・それは、俺だってそうだぜ。」
イサトが急に声のトーンを落として真面目な顔になった。
「え?だって・・・」
「今日の場合は、特別!」
今度は真面目な顔を引っ込めて、怒ったような顔になる。
「え?」
「男の友情よりも、花梨と仲良くなりたいってこと!」
ぶっきらぼうに言い放つ。
まだイサトの頬は赤いままだ。
「あ、ありがとう・・・」
友としてなのか、女としてなのか、花梨は判断に迷う。
迷っているうちにも心臓の鼓動は勝手に速度を増していく。
再び頬が染まっていく感覚に花梨は俯いてしまった。
イサトはそれを見ると、花梨に見えない方の手で小さくガッツポーズをしてから、話題を変えた。
「昨日は楽しかったな。」
「うん!とっても!」
「お前の歌、すっげぇ良かったぜ。俺、早くお前とライブしてぇよ。」
イサトの言葉に、花梨は面食らった。
そんな風にストレートに気持ちを口に出す男子を、花梨は知らない。
「そ、そうだね・・・」
「お前ってさ、歌手になりてぇの?」
「え?」
「歌のレッスンに通ったりしてさ。」
「あ、うん。まあ、そんな所かな。」
急に変わった話題にやっと追いついて、花梨が答えた。
「そんな所?」
「うん。歌手って言ってもいろいろあるから。」
「へえ、モームスみたいになりたいんじゃねぇの?」
「うん。ちょっと違うかな。イサト君は、歌のお姉さんって分かる?」
「うたのおねえさん?」
「小さい頃、ニコニコプン見てた?」
「ああ。見てた見てた。俺の初恋はピッコロってぐらい見てた。」
花梨がはじけたように笑いながら続ける。
「そうそう、それ。その中でお姉さんやお兄さんが歌を歌ってたでしょ?」
「ああ、そういえば居たな。」
「そういう人になりたいの。」
「へぇ。」
「私ね。子供が大好きだから、子供達に歌を通していろんな事を伝えていけたらいいなあって思うの。」
「花梨・・・」
そう言って口をつぐんでしまったイサトを花梨が見上げると、イサトは何か言おうとして迷っているようだった。
しばらくアスファルトを見つめ黙っていたが、横目で花梨を見る。
「笑わねぇ?」
「へ?」
「俺がこれから言うこと、絶対に笑うなよ。」
「う、うん。」
花梨は目を白黒させる。
「実はさ、俺も、すっげぇ子供が好きで。」
「ええっ?」
「毎週土曜日と、他にも暇な時は近所の学童クラブでボランティアしてるんだ。」
「すごい!尊敬しちゃう!なんで笑うなんて思ったの?」
「だってよぉ、子供好きな男子高校生って変じゃねぇ?」
「そんなことないよ!・・・ま、まぁ、確かに少ない部類に入るかもしれないけど、恥ずかしいことじゃないもの!」
「ありがとな。花梨。」
イサトがほっとしたようにため息をついたが、花梨は一人の世界に入ってしまっていた。
「いいなあ。学童クラブでボランティアかあ、やってみたいなあ。一緒に歌とか歌いたいなあ。」
イサトはキラキラと目を輝かせる花梨の様子に目を細める。
「お前さ、そんなに羨ましいなら、今度手伝ってくれよ。」
「ええっ?いいの?」
「だってよ、メチャクチャ大変だぜ?あいつら・・・」
それから駅に着くまで、イサトは自分がいかに子供達に手を焼いているかを面白おかしく話し続け、花梨はお腹が痛くなるほど笑ったのだった。