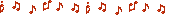
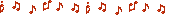
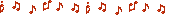
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

おはよう
土曜の朝、花梨はイサトの家のそばにあるバス停に降り立っていた。
近くの石垣に寄りかかって待っていたイサトが花梨に駆け寄る。
「よお。」
「おはよ。」
イサトは、GパンにTシャツというラフな格好の花梨を見ると、少し頬を染めて呟いた。
「・・・合格。」
「え?何が?」
「服装だよ。動きやすい格好って言っただろ!」
怒ったように言い放つ。
花梨が目を丸くして口を開いた。
「合格なんでしょ?何でそんなに怒ってんの?」
「・・・っ、怒ってねぇよ。行くぞ!」
赤い髪を翻して、イサトが歩き出した。
やっぱり怒ってるみたい、と思いながら花梨は後ろについて歩く。
ほどなく金網で覆われたグラウンドが見え始めた。
「あの学校?」
「ああ、俺と勝真が通ってた小学校だぜ。」
イサトが頷いてから、花梨と歩調をあわせて横に並ぶ。
「え?勝真さんも近所なの?」
「あ、言ってなかったっけ?俺と勝真は、幼馴染なんだよ。」
「知らなかった!」
「俺がギターを始めたのも、勝真の影響だし、バンドも勝真に誘われて入ったんだ。」
「へえ〜。どうりで仲が良いと思ったよ。」
「そうだろ?本当の兄弟よりも仲がいいくらいだぜ。」
「そうなの?」
「俺は真面目くさった自分の兄貴より勝真の方が好きだし、勝真も生意気な妹より俺の方を可愛がってくれてるし。」
「そうなんだ?」
驚いてイサトを見上げる。
「まあな。」
少し誇らしげに言いながら、イサトは門の前に張られた鎖を跨ぐ。
花梨もそれに倣って鎖を跨いだ。
見ると、イサトは2メートルほどある門を軽い身のこなしでよじ登っていた。
花梨が、やっぱり男の子だなあ、と呑気に思っていると、門の上でイサトが手招きした。
「ええっ?私も登るの?」
「こっちの方が近道なんだよ。そこの隙間に足をかけて、一気に登れば大丈夫だから。」
言われた通りに足をかけるが、イサトとは足の長さが違うので、なかなか登れない。
「なんだよ。鈍くせぇなあ。」
言葉とは裏腹に笑ったイサトが手を出す。
「こんなのムリだよ〜。」
泣き言を言う花梨を、イサトは軽く引っ張りあげてしまった。
しかし、今度は下りられない。
「怖いよ・・・」
先に飛び下りたイサトは、そんな花梨を見て優しく笑うと、手を広げた。
「ほら、受け止めてやるよ。」
「ええっ?」
その結果を予測して、花梨は頬を染めた。
「お、お前、今、ヘンなこと考えたろ。」
イサトもつられて頬を染める。
「いいから早く来いよ。俺の方が恥ずかしくなるだろ。」
花梨は意を決してイサトに向かって跳んだ。
いつもは少年のようなイサトの顔が頼もしい男の顔になり、次の瞬間、花梨は、イサトの腕が自分の腰の辺りを抱き止めたのを感じた。
ほっと息をついて、固いものを抱きしめている感覚から見下ろすと、イサトの頭があった。
慌てて身体を起こす。
「ごっ、ごめん!」
「・・・ぷはっ。」
イサトが苦しそうに息を吐き出した。
「お前なあ・・・」
そう言いながら、かがんで花梨を地面に下ろす。
申し訳なさそうに俯く花梨に文句の続きを言おうとしたイサトだったが、はたと口をつぐむと、頭の後ろに両手をやって、にへらっと笑った。
「お前の胸、柔らけぇのな。それに、いい匂いもした。」
花梨はイサトのストレートな言葉に耳まで真っ赤になった。
両腕で胸を隠してイサトを睨む。
「イ、イサト君のエッチ!」
にやにやしながら恥ずかしがる花梨を見ていたイサトだったが、急に眉をしかめて何かに気付いたような顔をした。
すぐに耳まで赤くなってGパンのポケットに手を入れる。
「さ、行くぞ。」
そのままイサトは、少し前かがみになって先に歩き出した。
花梨も、イサトの様子に首を傾げながら後ろについて行った。
グラウンドを横切り校舎に向かうと、二人の子供が玄関の前で所在無さげに佇んでいた。
「あいつら、またこんな早くに追い出されたのかよ。」
そう呟くイサトの言葉に、学童の現実を垣間見て、花梨は気を引き締める。
「よっ。今日も早いな。」
しかし、イサトは先ほどの呟きが嘘のような明るい声で二人の子供に挨拶した。
男の子と女の子だったが、二人はよく似ていた。
「お前が遅いのだ。」
「申し訳ありません。イサトお兄様。」
よく似た二人から同時に正反対の回答が返ってきて、花梨は思わずくすりと笑ってしまった。
男の子がじろりと花梨を睨み、女の子は不思議そうに花梨を見た。
花梨はしまった、と思ったが、にこやかに挨拶をすることにした。
「初めまして。高倉花梨です。よろしくね。」
イサトは花梨が二人に話しかけるのを見届けて、どこかへ行ってしまった。
「私は藤原紫です。よろしくお願いします。」
「私は双子の兄の御苑だ。」
「やっぱり双子ちゃんなんだ。よく似てるもんね。」
花梨が相好を崩すと、深苑が顔をしかめた。
「子供扱いをしないでもらいたい。」
花梨は深苑の言葉にはっとして笑みを消す。
「お兄様!」
紫が悲しげな顔をして嗜めると、深苑は気まずそうに横を向いた。
「ありがとう、紫ちゃん。でも、深苑君の言う通りだね。ごめんなさい。」
花梨が再び紫に笑顔を向ける。
紫もほっとしたように微笑んで首を振った。
「お待たせ。」
イサトが右手に鍵を持って戻ってきた。
「こっちに学童専用のプレハブがあるんだ。」
イサトが中庭へ歩き出す。
花梨達もあとからついて歩き出した。
「イサト。遊びではないのだぞ。」
深苑がふいに説教口調でイサトに話しかけた。
「はぁ?何が?」
深苑はいつもこんな調子なのだろう。
さして驚きもせずにイサトが間の抜けた声を返した。
「ここは恋人を連れて遊びに来るような場所ではない。」
「へ?」
イサトがそう言いながら振り向くと、紫と深苑が揃って花梨を横目で見ていた。
花梨が視線に気付きうろたえる。
「えっと・・・」
「バッ、バカ!花梨はそんなんじゃねぇよ!」
イサトが頬を染めて深苑を睨む。
花梨は冷や水を浴びたような気がしたが、イサトに合わせて頷く。
「そ、そうそう。友達。イサト君と私は、ただの友達よ。」
今度はイサトの顔が引きつった。
「な、なあ。誤解だよなあ。はは、は・・・」
「笑っちゃうよね。アハ、アハハ・・・」
乾いた笑いが静かな中庭にこだました。