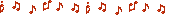
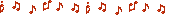
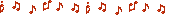
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

体育祭
1年生で文化部の花梨と千歳にとって、体育祭はできればサボりたいイベントだった。
2年になればいろいろ準備や係があるのだが、1年のうちはクラス内で1人1種目に出場するというノルマをこなせば、あとは運動部の友達が大活躍しているのを応援席で座って見ているだけだ。
風が涼しいとはいえ、まだまだ日差しは強い。
花梨は縦割りで一緒のチームになった2年生が指示するとおりに団扇を上げたり下ろしたりして応援を真面目にこなしていたが、千歳は隣でフェイスタオルを日除けにかぶり、耐えられない、というようにぐったりとしていた。
二人とも黄色い鉢巻を締め、2年生の女子がデザインした揃いの黄色いTシャツを着ている。
平安高校は学区内で2番目に偏差値が高い高校だ。
そのため殆どの生徒が進学するが、2番目というだけあって浪人する生徒も多い。
合格率を上げるため、教員側が校内のイベントを簡単に済ます方向へ舵を取っているので、体育祭もイマイチ盛り上がらないものになっていた。
中間テストに響かないよう9月末に開催されるのも、受験に響かないよう3年生が不参加になっているのも、教員の温かすぎる配慮だ。
「千歳、大丈夫〜?」
音楽室へ向かうため、花梨と千歳は渡り廊下を歩いていた。
「この状態でホルンを吹いたら死んでしまうかもしれないわ。」
長い黒髪を珍しく後ろにまとめた千歳が、濡らしたタオルを頬に当てながら演技がかった声で言った。
「髪の毛が黒いからかなあ?」
花梨が千歳の頭をさすりながら呑気なことを言う。
それを聞いて千歳が呆れたような声を出した。
「あなたが元気すぎるのよ。日焼け止めも塗らないで・・・顔が真っ赤よ。」
「ええっ?」
鳩が豆鉄砲を食らったような顔で花梨が頬に手を当てる。
「もう・・・」
千歳が母親のように言うと、花梨の頬に濡らしたタオルを当てる。
「わっ、気持ちいい〜!」
無邪気に笑う花梨の様子に千歳も微笑んだ。
二人で代わる代わるタオルを頬に当てながら音楽室へ入る。
色とりどりのTシャツや鉢巻が、静かに座って楽器を吹いている様子は、少し奇妙だった。
花梨と千歳も自分に割り当てられた楽器を棚から取り出して音を出す。
しばらくそうしていると、体育委員の男子生徒が走り込んで来た。
「準備、お願いします!」
吹奏楽部が本部テントの中に整然と座り終えた頃、最後の種目のために生徒達が入場門に集まってきていた。
その中にイサトを見つけた花梨はドキリとする。
白い鉢巻をキリッと締めて黙々と屈伸をするイサトが、やけに男らしく見えたからだ。
花梨が見とれていると、放送部のアナウンスが入った。
『本日のメインイベント!混合リレーの選手達が入場します!』
グラウンドを挟んで本部テントの向かいにある応援席が、最高潮の盛り上がりを見せる。
花梨は初めて見る興奮状態に、特等席だなあ、などとぼんやり思っていた。
ドドドドッと土煙を上げて選手が入場する。
応援席がそれぞれ2年生の振り付けしたとおりに応援を始めた。
団扇を使うチーム、軍手を使うチーム、色ごとに工夫を凝らした応援がよく見える。
花梨はもう一度、特等席だなあ、と思った。
第1走者と第2走者が位置につく。
吹奏楽部の部員達が楽器を構えると、指揮者が棒を振った。
あまり上手ではないが、それなりのファンファーレが鳴り響く。
本部テント横の保護者席からどよめきと笑い声が漏れた。
そのファンファーレが競馬の出走で使われている曲だったからだ。
曲が終わると、体育委員が前に出て、空に向けてピストルを撃った。
ワッと応援席が騒がしくなる。
吹奏楽部の2年生も、譜面台に表彰式の楽譜を用意すると、楽器を置いて応援し始めた。
花梨は何とはなしに、イサトを探していた。
すぐに目の前の選手集団の中で声を張り上げているイサトを見つける。
白いたすきをしていた。
「アンカー?!」
花梨は驚いて思わず呟く。
イサトがそんなに足が速いとは知らなかったのだ。
じわりと広がる甘い思いと共に、花梨の心臓がスピードを上げる。
だが、それ以上に花梨の心を占めたのは不安だった。
自分が走るわけでもないのに、その責任を思うと緊張してしまう。
転んだらどうしよう、抜かれたらどうしよう。
花梨にとってアンカーには、そんな記憶しかない。
イサトの出番が近づいてくる。
イサトがトラックに出た。
『最後の走者はグラウンド一周です!』
「ええっ?!そうなの?」
花梨は思わず悲鳴に近い声を上げた。
場内アナウンスと会話する花梨を、吹奏楽部の面々が不思議そうに振り向く。
イサトもちらりと花梨を見た。
が、すぐに後ろから緑の鉢巻をした選手が走り出し、イサトが慌てて助走を始める。
ピンクの鉢巻の選手と赤の鉢巻をした選手が行ってから、白の鉢巻をした選手が駆けてきた。
イサトは、その選手から奪うようにバトンをもぎ取ると全力で走り出した。
『白、速いです!』
あっという間にピンクと赤を抜き去って緑の選手を追いかける。
「すごい・・・」
花梨が呆然と呟く。
応援席側の直線に入り、緑の選手とイサトの距離が少しずつ縮まっていくのがよく分かった。
赤く長い髪が真っ直ぐにイサトの後ろへ流れる。
白い鉢巻をした吹奏楽部員が手を叩いて応援する。
花梨は胸の前で手を組んで祈るような気持ちでいた。
がんばって、がんばって、と心の中で何度も唱える。
緊張のあまり花梨は声を出して応援することもできないでいた。
その間にも、イサトはどんどん緑の選手との差を縮めていく。
目の前にゴールテープが張られた。
最後の直線に入り、イサトがラストスパートをかける。
次の瞬間、緑の選手とイサトがほとんど同時にゴールを駆け抜けて行った。
緑の応援席と白の応援席が同時にドッと沸く。
吹奏楽部ブースの隣に設置された放送席で、マイクの前に居た放送部の女子生徒が隣の男子生徒と顔を見合わせた。
慌てて男子生徒が立ち上がり、体育委員のブースへ走る。
『混合リレーの結果は、しばらくお待ちください。』
緑と白の応援席から不満の声が聞こえてきた。
花梨は両手を組んだまま固まっていた。
震えが止まらない。
イサトは苦しそうに膝に手をついて肩で息をしていた。
白い鉢巻の選手達がその周りでイサトを叩いたり撫でたりしている。
放送部の男子生徒が戻ってきて女子生徒に何か言った。
『混合リレーの結果につきましては、これから審査に入りますので、先に表彰式の準備に入らせていただきます。』
その言葉にイサトが体を起こし、横腹を押さえながら他の生徒達と一緒に退場門へ向かう。
ふいにイサトが振り向き、苦しそうに片目を瞑りながら花梨に向かってVサインを送った。
花梨が両手を組んだまま、泣きそうな顔で大きくウンウンと頷く。
吹奏楽部の2年生が自分達に対してだと誤解して、イサトに拍手を送る。
イサトはその拍手にも手を振って答えると、応援席の方へ戻って行った。
楽器を片付けてミーティングを終えた花梨と千歳は、ハーフパンツだけ着替えて制服のスカートにTシャツといういでたちで玄関を出た。
二人が帰ろうとすると、玄関の柱に寄りかかって待っていたイサトが駆け寄る。
「おい、花梨。」
「あ、イサト君。」
イサトもTシャツに制服のズボンだった。
緩んだネクタイのように鉢巻を首にかけている。
他の男子生徒もみんなそうしていたので、この学校の流行なのだろう。
「なあに、あなた達、知り合い?」
千歳が嫌そうな顔でイサトを見た。
「悪いかよ。」
イサトがフン、とそっぽを向く。
「千歳、イサト君のこと知ってるの?」
「家が近所なのよ。」
「そうなんだ?」
「どうやら、あなたにしか用がないみたいだから、私は先に帰るわ。」
「え?」
花梨が困ってイサトと千歳を見比べる。
「そーだ。帰れ帰れ。」
イサトがそっぽを向いたまま憎まれ口を叩いた。
そんなイサトを完璧に無視して、千歳が花梨へ笑いかける。
「じゃあね、花梨。」
「うん・・・バイバイ。」
千歳が背を向けて歩き出した。
花梨は、どうせ知り合いなら仲良しが良かったのに、と思いながらイサトを見上げる。
すぐに、大事なことを思い出し、笑顔になった。
「そうだ!イサト君、1位おめでとう!」
「おう!」
「すごかったねぇ。」
「だろ?任せろよ!」
「もう私、震えが止まらなかったもん。」
自慢げに胸を張っていたイサトが、急に優しげな瞳になって言った。
「お前のお陰だよ。」
「え?何が?」
「あのさ・・・後夜祭、行かねぇ?」
花梨の問いには答えずに、イサトがぶっきらぼうに言う。
「へ?」
後夜祭は、体育祭で使った入場門等をグラウンドで燃やす際に、周りでフォークダンスを踊るというイベントだった。
教員達も黙認していて、体育祭の前にはフォークダンスの振付けを覚える授業が行われるほどだ。
花梨も一応イベントは知っていたし、踊りも踊れる。
2年生との出会いに期待する友達などは喜んで参加しているが、花梨と千歳はそういうタイプではなかったので、参加せずに帰ろうとしていたのだ。
「別にいいけど、パートナー要らないんじゃなかった?」
フォークダンスは元々パートナーが次々と代わるものなので、パートナーを誘って参加する必要はない。
「外円はな。」
「なにそれ?」
「外円は相手が代わるけど、内円はずっと同じヤツと踊るんだよ。」
「へえ〜。知らなかった!」
「俺、他にオンナの知り合い居ねぇしさぁ・・・嫌か?」
イサトが明後日の方向を向いて言うと、横目で花梨を伺う。
「ううん。嫌じゃない。光栄だよ。」
花梨が嬉しそうに言うと、イサトが頭の後ろに手をやって、へへっと笑った。
「ねえ、なんでそんなつまらなそうな顔してるの?」
向かい合ってイサトの手を取りながら花梨が心配そうに口を開いた。
「ん?そうか?」
自分の腕の下をくぐる花梨をそのまま捕まえてしまいたい衝動に駆られながら、イサトが上の空で答える。
「楽しくないの?」
至近距離で見上げてくる花梨の瞳を見つめることができず、イサトは目をそらした。
「そ、そんなことねぇよ・・・」
花梨は、首を傾げながらも口をつぐむと、再び踊りに集中する。
イサトが花梨の腰へ右手を置く。
花梨のコロンの香りと、スカートから微かに伝わってくる曲線の感触に、ゴクリと唾を飲む。
イサトは、正直困っていた。
花梨と近づきたい、少しだけでいいから触りたい、という気持ちから踊りに誘ったのはイサトだ。
しかし、近づくたび、触れるたび、イサトはどうしようもなく翻弄されてしまっていた。
『さあ、次はサザンの曲だよ。マイムマイムの振付で踊ってね。恋はノーリーズン!』
放送部の生徒がDJ気取りでナビゲートする。
フォークダンスといっても、放送部が振付に合うよう選曲したヒット曲がかかっていた。
イサトと手をつないでステップを踏みながら花梨が思いついたように言う。
「そういえば、イサト君って、なんで陸上部に入らないの?」
「あ?・・・ああ、つまんねぇから。」
マイムマイムの振付は密着度が少ないので、イサトにも少し余裕がある。
「もったいないよ。あんなに足が速かったら、大会だって出れるのに。」
「まあな。でもよ、すぐに結果が出ない事をコツコツ続けるのって、苦手なんだよな。」
花梨が吹き出した。
「分かる気がする!」
「そこは笑うとこじゃねぇぞ。」
イサトも言葉とは裏腹に笑顔になる。
花梨の笑い声を聞いた外円の男子生徒が、羨ましそうに内円を振り返った。
白い鉢巻を首にかけたその生徒は、はっとした顔になると、ニヤニヤしながら円を抜けて、放送席へ走る。
突然、音楽に割り込むように、アナウンスが入った。
『えー、宴もたけなわでございますが、本日のヒーローが可愛い彼女と内円で踊っているという情報を入手しました。』
踊っていた学生達がどよめき、ピューイッと口笛を鳴らす音が聞こえた。
イサトと花梨も驚いた顔を見合わせる。
『インタビュー、聞きたい人〜?』
「はーーーい!」
外円の男子生徒達がヤケになったような声で手を挙げて叫ぶ。
海老ぞりのようなジャンプをしながらそこらじゅうを跳ね回る生徒もいた。
『混合リレーで大活躍して白を優勝に導いた赤羽イサト君!彼女と一緒に放送席まで来てください!』
「マジかよ?!」
イサトが戸惑った声で言って花梨を見た。
花梨も目を丸くしてイサトを見る。
周りの学生が二人を遠巻きに囲んでヒューヒューと冷やかした。
どこからか、イサト!イサト!とコールが起こり、大合唱になる。
「わりぃ、花梨。ちょっとだけつきあってくれ。」
イサトが観念したような顔で言うと、花梨の手を引いて放送席まで歩き出した。
周りの学生がオーッ、と声を上げ、手を叩いて道を開ける。
花梨は、手を引かれながら恥ずかしさと戸惑いに交ざる誇らしい気持ちに気付いて、イサトの横顔を見つめた。
白い鉢巻を首にかけた男子生徒達がニヤニヤしながら朝礼台を運んでくる。
「あいつらか・・・」
イサトがため息まじりで言う。
花梨にも見覚えがあった。
恥ずかしい目に遭ったことを思い出し、青くなる。
彼らに促されるまま、二人は朝礼台に上がった。
そのまま男子生徒達はイサトの足元に陣取る。
その中の一人が財布を持ってグラウンドから走り去っていった。
放送部の生徒がマイクを持ってイサトの横に並ぶ。
『赤羽イサト君です!』
周りに集まってきた生徒達からワーッと声が上がった。
『可愛い彼女のお名前は?』
マイクを向けられ、花梨は困り果てながら答える。
『えっと・・・高倉花梨です。』
生徒達からヒューといった高い冷やかし声が上がり、どこかで男子生徒がおかしなイントネーションでカーワーイーイーと叫んだ。
右の方で黄色いTシャツを着た生徒のかたまりから、キャ〜ウソ〜?!と声が上がる。
花梨のクラスの生徒だ。
左の方から白いTシャツを着た茶髪の女子生徒が叫ぶ。
「イサトの裏切り者〜!」
隣に居た髪の長い女子生徒も叫ぶ。
「後夜祭出ないって言ったじゃんよ〜!」
茶髪の女子生徒が再び叫ぶ。
「相手が居るならそう言えよ〜!」
花梨が驚いてイサトを見た。
「あちゃー・・・」
イサトが花梨から顔を背けて呟く。
どうやらクラスの女子の誘いを断って花梨を誘ったらしい。
『はいはい、皆さん落ち着いて。まずはイサト君、今日の走りはやっぱり彼女が見てたからですか?』
『ま、まあな。』
花梨の友達が顔を見合わせ、夢見るようにキャ〜と声を上げた。
白いTシャツの女子生徒達から、酔いが足りなーい、という声と笑い声が上がる。
『飲んでねぇし。』
イサトがすかさず突っ込む。
『では、花梨さん、今日のリレーでは、自分のチームとイサト君、どちらを応援しましたか?』
花梨は迷ったが、正直な事を言うことにした。
『あの・・・イサト君、です。』
再びヒューという冷やかし声が上がり、男子生徒がカーワーイーイーと叫ぶ。
イサトは頬を染めて奥歯にものが詰まったような顔をした。
『お二人が付き合い始めたのはいつからですか?』
二人が困ったように顔を見合わせる。
『・・・まだ付き合ってねぇよ。』
イサトの言葉に、エーッという不満の声が大合唱となった。
『後夜祭に誘ったのはどちらから?』
『・・・俺。』
『もしかして、これから告白だったとか?』
花梨がどんな顔をしていいか分からず固まる。
『・・・いや・・・別に・・・』
イサトが困ったように首を傾げながら答える。
実際、イサトにそんなつもりはなかった。
花梨のことは好きだが、なにぶん、出会ってからまだ10日だ。
告白するほど機が熟しているわけではない。
イサトの足元で男子生徒が、告れよー、と囃し立てた。
コクレ!コクレ!とコールが起こるが、イサトは顔の前で手をブンブンと振って拒否する。
足元の男子生徒が紙コップを放送部の生徒に渡した。
『あれー?こんな所に麦茶がありますよー?』
ドッと朝礼台の下から笑い声が起きる。
「麦茶?」
花梨が首を傾げた。
ほとんどの生徒は何のことか分からないらしく反応が薄い。
『イサト君、喉が渇いたんじゃないですか?』
コップの中身を見たイサトが、額に手をやって天を仰ぐ。
コンビニの袋を持った足元の男子生徒達を睨んでから受け取ると、一気に飲み干した。
『もしかして、これから告白ですか?』
放送部の生徒が、もう一度同じ台詞を繰り返す。
再びコクレ!コクレ!とコールが起こるが、イサトはやはり拒否する。
足元の男子生徒が暗い中で紙コップに何かを注いでもう一度、放送部の生徒に渡す。
『あれー?こんな所に麦茶がありますよー?』
状況を飲み込み始めた生徒達が、顔を見合わせたりニヤニヤしたりして成り行きを見守った。
3杯目を飲み干したイサトがゲフッとゲップをしたのを見て、花梨はようやく状況が飲み込めた。
麦茶と言って渡されているのはビールだ。
このままでは告白するまで飲まされてしまう。
イサトはまだ、告れコールを拒否していた。
花梨の頭に、イサトが先日の打ち上げで酷い目にあったという泰継の言葉が浮かんだ。
酷い目というのがどういうものかはよく分からないが、心配だ。
「イサト君、もうやめて。」
4杯目を渡されたイサトに花梨が縋り付くと、生徒達がヒューヒューと沸く。
「だってよ・・・嫌だろ?こんなトコで。」
イサトは花梨の気持ちを尊重して飲み続けていたのだ。
生徒達が興味津々で二人の様子を見守る。
花梨が小声で続けた。
「でも・・・このまま飲み続けたって・・・」
「潰れればコイツらも気が済むんだよ。」
「酷い目に遭うんでしょ?」
「吐きまくるだけだよ。お前に嫌な思いをさせるよりはいい。」
「イサト君・・・」
イサトの気持ちが伝わってきて、花梨は言葉に詰まる。
花梨が黙ったのを見て、イサトが4杯目を飲み干した。
苦しそうに口の端からこぼれたビールを肩で拭う。
再び告れコールが始まって、イサトは拒否をするため手を上げようとした。
しかし、その腕は花梨にしっかりつかまれていた。
「花梨・・・」
「お願い。私はいいから。」
泣きそうな顔で花梨が言うと、イサトが申し訳なさそうに花梨を見つめる。
花梨の瞳に涙が滲み始めたのを見つけると、イサトは頷いて花梨の肩をつかんだ。
オオオーッと、生徒達の声が地鳴りのように響く。
放送部の生徒がイサトにマイクを向けた。
イサトは、どんな状況だろうと心からの言葉を伝えなければ花梨に申し訳ない、と思う。
精一杯、優しく言った。
『花梨、お前を好きだよ。』
花梨が頷くと、涙をこぼす。
イサトがゴールテープを切った時のような拍手と歓声がグラウンドに鳴り響いた。
※未成年の皆さんへ。「お酒は20歳になってから!」です。
イッキ飲みの強要は、過失傷害罪や強要罪として処罰される場合があります。