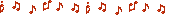
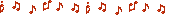
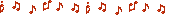
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

ハイかイイエ
「あ、来ましたわ、花梨お姉様。」
池の鯉を眺めていた紫が車の音を聞き取って校門を振り向いた。
花梨がそちらを見ると、しばらくしてから黒塗りの高級車が静かに滑り込む。
「あんな静かな音が分かっちゃうんだ!」
花梨が目を丸くして紫を見ると、紫は頬を染めてお菓子の袋を弄んだ。
その様子が可愛らしくて、花梨が微笑む。
腕組みをして近くの石に腰掛けていた深苑も立ち上がった。
「花梨、イサト、時間を取らせたな。」
そう言うと、背中にとりつけた黒いゴミ袋をなびかせながら、車に向かって歩き出す。
「気にすんな。」
イサトがその背中に声をかけ、見上げる紫に微笑む。
「お二人とも、ご迷惑をおかけいたしました。さようなら!」
紫が言うと、深苑を追って走り出した。
黒い画用紙で作った三角帽子が取れそうになって慌てて押さえると、再び走り出す。
イサトと花梨は黙ってその様子を見送った。
運転席から初老の男性が降りてきて、恭しく後部座席のドアを開ける。
「とりっくおあとりーと、です〜!」
「菓子をくれなければいたずらをするぞ。」
二人は口々にその男性へ言いながら車に乗り込んだ。
「分かりました。帰りに菓子屋へお寄りいたします。」
男性はそう告げると静かにドアを閉め、運転席に乗り込む。
花梨の隣でそれを見ていたイサトがクスリと笑った。
「あのセリフを深苑が言うとやけに怖ぇな。」
そう言ってから花梨を見て、花梨が暗い顔をしているのに気付く。
「どうした?」
「うん・・・なんか、ハロウィンにあんな返事もらうなんて、可愛そうだなって思って。」
「まあな・・・金があっても幸せとは言えねぇよな。あれじゃ。」
「そうだね・・・」
後部座席の窓が開いて紫が手を振る。
二人が笑顔を作って手を振り返すと、車が走り出した。
「さ、俺達も帰ろうぜ。練習に間に合わなくなっちまう。」
「うん。」
急に静かになった前庭を、二人は正門へと黙って歩いた。
イサトから告白を受けて以来、二人きりになるのは初めてで、花梨は何を話せばいいのか戸惑う。
イサトはその隣で頬を染めたまま黙って歩いていた。
花梨に聞きたいことがあるのだが、なかなか言い出せない。
テスト前にバスで会った時にも、言い出せないうちに邪魔が入ってしまったのだった。
お互いがお互いを見ないように歩くせいで、距離感が取れなくなり、二人の肩が触れ合う。
イサトがドキリとして飛び退いた。
その様子に、花梨が不安そうな顔をする。
「イサト君・・・?」
花梨に見つめられて、イサトはぎこちなく目をそらすと、少し躊躇ってから口を開いた。
「俺・・・まだ返事もらってねぇんだけど。」
「え?」
「・・・体育祭のときの。」
花梨がはっとして頬を染める。
確かにあの時、花梨は泣いてしまって返事どころではなかった。
一応、頷いたのだが、イサトは返事と思わなかったらしい。
そのまま校内の注目の的になってしまったので、イサトと二人でゆっくり話すチャンスがないまま、ひと月が過ぎていたのだ。
もちろん花梨だってイサトの事が好きだ。
そう言わなくちゃ、と思うのだが、心臓が高鳴って口を開くことができない。
そっぽを向いていたイサトが痺れを切らして花梨を見る。
花梨が耳まで真っ赤になっているのを見て、目を丸くした。
「お前・・・」
イサトはそう言うと、ふと口をつぐんでから優しく言葉をかける。
「じゃあ、こうしようぜ・・・ハイかイイエで答えろよ。」
これはイサトがよく子供に使う手段だ。
へそを曲げて黙り込む子供や、泣きすぎて喋れなくなった子供に意思表示をさせる時、イサトはこんな風に優しく問う。
花梨は、そういう時にイサトが出す優しい声が好きだ。
心臓を柔らかくつかまれるような切なさが、花梨の胸を満たしていく。
イサトが少し間をあけてから続ける。
「・・・俺のこと、好きか?」
花梨は躊躇わずにコクリと頷いた。
「そっか・・・へへっ、じゃあ、今からお前は俺のもんだからな。」
イサトが嬉しそうに笑うと、頭に両手をやる。
「・・・うん。」
頬を染めたまま、花梨も小さく返事をした。
「他の男と喋ったりすんなよ。」
「ええっ?それはムリだよ!」
花梨が驚いてイサトを見上げる。
「彼氏の命令だぞ!」
イサトがニヤニヤしながら花梨の顔を覗き込んだ。
花梨はからかわれている事に気付いて頬を膨らませる。
「なにそれ!勝手な彼氏!」
「だはは、ヘンな顔〜!」
イサトが花梨の頬をつつく。
やっと想いが通じた嬉しさから、花梨に触れたくて仕方がないのだ。
「やめてよ〜。DVだよ!」
イサトに触られて恥ずかしくなった花梨が、適当なことを言ってそっぽを向くと、イサトが吹き出した。
「今のがDVかよ?・・・ショボ!」