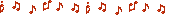
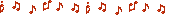
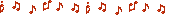
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

花
ミカド楽器でレッスンを終えて、花梨は駅へ向かっていた。
足取りが軽い。
今日は、イサトと期末テスト終了祝いにカラオケに行く約束をしているのだ。
平安駅のロータリーでキョロキョロと見回すと、小さめのヘッドホンをしたイサトが柱に寄りかかっているのが見えた。
好きな音楽を聴いているのだろうか、伏目がちに床を見つめる横顔には、どこか色気がある。
花梨はそれを眺めながらそっと近づくと、イサトの見ている方向に手を出してひらひらと振った。
「おっ!」
イサトが驚いて顔を上げる。
花梨を見てから、嬉しそうに顔を綻ばせた。
「よお、早かったな。」
そう言って、学ランの胸ポケットに留めてあるリモコンを操作すると、ヘッドホンを外して首にかける。
「何聴いてたの?」
「ん?ああ、アジカン。」
答えながら、イサトはカラオケボックスに向かって歩き出した。
花梨も横に並んで歩き出す。
「アジカン好きなんだ?」
「まあな。音に嘘がなくて好きなんだよ。」
「嘘?」
「なんかさ、自分でギターやってるからかも知んねぇけど、歌の邪魔になんねぇように変えられたギターの音が嘘っぽく聞こえる時があるんだよな。」
「ギターの音を修正しちゃってるってこと?」
「そういうこと。時朝に聞いたら、今はレコーディング技術が発達してるから、歌声に合わせて音質を変えるのなんか朝飯前なんだってさ。」
「へえ?」
「だから、アジカンだけじゃなくて、本当の音を大事にしてるロックバンドなら、けっこう好きだぜ。」
「例えば?」
「そうだな・・・有名なとこだと、ラルクとか、トライセラとか。」
「へえ・・・」
イサトは少しの間黙ってから、続けた。
「だから、お前にも、本当の音を出して欲しい。」
「え?」
「アクラムのこと。」
「・・・うん・・・」
花梨が歯切れの悪い返事をしたのを聞いて、イサトが少しムッとする。
「他の奴らはお前が良ければいいとか言ってるけどよ、俺はそんなの認めねぇから。」
「・・・・・・」
花梨が返事をしないので、イサトは不安そうに続けた。
「アクラムの言いなりになって歌うお前をいいなんて思えねぇ。俺は、本当のお前とライブしてぇ。」
「・・・イサトくん・・・」
「それと、ヘンなブリッコみたいに歌うお前をテレビで見るのなんか嫌だぜ。」
「・・・うん・・・」
「俺、子供と一緒に居るお前が好きだし、夢をかなえようと頑張ってるお前が好きだ。だから、妥協してアイドル歌手なんかやるなよ。」
イサトが建物に入り、エレベーターの上ボタンを押しながら言った。
「・・・・・・」
花梨の返事がないのでイサトが不安気に振り向くと、花梨は、頬を染めて俯いていた。
イサトも自分が言った言葉を思い出して頬を染める。
エレベーターの扉が開いて、二人で乗り込む。
密室になり、恥ずかしさと気まずさに耐えられなくなったイサトがぶっきらぼうに言った。
「・・・仕方ねぇだろ、ホントの事なんだから。」
花梨が俯いたまま答える。
「・・・うん・・・ありがとう。私も、子供と一緒にいるイサト君、好きだよ。」
イサトが頬を染めると、口を尖らせてボソボソと言った。
「・・・そういう恥ずかしいことサラッと言うなよ。」
花梨がムッとして顔を上げる。
「イサト君の方が先にサラッと言ったんだよ?」
イサトはうっ、と怯むと、エレベーターの開くボタンを見つめて連打しながらボソリと言った。
「・・・そうだな・・・」
花梨は歌いながら、隣に座るイサトをちらりと見た。
イサトが慌てて目を逸らす。
部屋に入ってからずっと、二人はそんなことばかり繰り返している。
花梨は、イサトがリクエストする曲をずっと歌わされていた。
イサト君も歌えば、と言っても、前に出て歌おうか、と言っても、イサトは、いい、の一点張りだ。
花梨は歌い終わると、頭の上で手を組んで仏頂面をしているイサトを横目で見て言った。
「イサト君・・・楽しい?」
「あ?・・・ああ、楽しいぜ。」
「ぜんぜん、楽しくなさそう・・・」
イサトは不安そうな花梨の視線に気付いて、慌てて身体を起こすと、頬をかいた。
「わりぃ。お前も、歌ってばっかじゃ、つまんねぇよな。」
「ううん、私は別に平気だけど、イサト君、どう見てもつまんなそうだもん。」
「・・・そうか?」
「うん。イサト君も歌いたいんじゃないの?アジカンとか。」
「・・・別に。」
「ホントに?」
不審そうな花梨の瞳に射竦められて、イサトが目を逸らした。
「ホント。」
花梨にしてみれば、その様子は嘘をついているようにしか見えない。
「じゃあ、なんでカラオケなの?・・・ゲーセンとかの方が楽しいんじゃない?」
花梨が憮然とした声を出したので、イサトはため息をついた。
しばらく黙り込んでから、ボソボソと喋り出す。
「・・・お前の歌をうんざりするほど聴きてぇと思ったんだよ。」
「え・・・」
花梨が絶句して頬を染める。
「・・・それと、歌ってるお前の顔を見てた。」
「・・・・・・」
花梨がますます赤くなって俯いた。
イサトがドサリとソファーにもたれてそっぽを向いたまま吐き捨てる。
「・・・こんなこと言わすなよ。」
「だって・・・イサト君、ずっと怒った顔してるんだもん・・・私のこと見てくれてるなんて、分かんないよ・・・」
花梨が赤くなったまま戸惑った顔を上げると、イサトも頬を染めて戸惑った顔をする。
「怒った顔してたつもりはねぇよ・・・なんかさぁ、お前とこういう場所に・・・その・・・二人きりっていうか・・・そういうの、照れんだよ・・・どんな顔してればいいか、分かんねぇんだよ・・・」
花梨が真っ赤になってイサトから目を逸らす。
「ふ、普通にしてれば、いいんじゃないかな・・・?」
イサトも気まずそうに目を伏せる。
「・・・分かってるけどさ、できねぇんだよ・・・」
しばらく二人は押し黙っていたが、花梨が遠慮がちに言った。
「歌うね。」
「へ?」
「イサト君、うんざりするほど聴きたいんでしょ?」
「あ、ああ、まあな。」
「じゃあ、歌う。」
花梨はそう言って、悪戯っぽい笑みを浮かべると続けた。
「もう、心配しないで歌い続けるから。イサト君がどんなヘンな顔してても無視するね。」
イサトも、花梨につられて悪戯っぽい笑みを浮かべると、わざと大きく顔をしかめた。
「こんな顔してもか?」
花梨がクスクスと笑いながら頷く。
「うん。無視。」
イサトがふっと笑うと、何かを思いついたような顔をする。
「・・・じゃあ、急に俺が具合悪くなったらどうするんだよ。」
「知らない。歌い続ける。」
花梨がわざとすまして答える。
「ひでぇ〜!」
イサトは楽しそうに笑うと、急にお腹を押さえて苦しむ振りを始めた。
「あっ、急にハラが・・・」
「知らないもん!」
花梨が笑いを噛み殺してそっぽを向いた。
「・・・た、助けてくれ・・・花梨・・・」
イサトが調子に乗って花梨の肩によりかかる。
花梨の柔らかさにドキリとして、イサトは動きを止めた。
花梨はそれに気付かず、堪えきれずに笑い出してイサトの方を向く。
イサトが突然、がばっと身体を起こすと、曲目リストを開いて花梨に背を向けた。
「さてと!次は何がいいかな・・・ヤイコばっか続いたからな・・・」
上ずった声で独り言を言っているように装う。
動揺しているのが明らかだ。
花梨はポカンとそれを見た。
「どうしたの?」
イサトが情けない顔で振り向くと、曲目リストを閉じて花梨に渡した。
「別に・・・好きなの歌っていいぜ。」
花梨は首を傾げながら頷いて、曲目リストを開く。
イサトがドサリとソファーに寄りかかってため息をついた。
「なんかヘコむ・・・俺って情けねぇな・・・」
「そうかな?」
「そうだよ。」
花梨は、もう一度首を傾げると、曲目リストをペラペラとめくってリモコンを操作した。
場違いな明るい前奏が響き渡る。
『例えばあなたがいてあたしは優しくなれるとか♪あたしがいてあなたがいて元気になれるとか♪』
花梨が明るいメロディーに乗せてあっけらかんとした声で歌う。
花梨の明るい声に包まれて、イサトの心が救い上げられる。
『HappyDaysどんなコトでもきっと♪HappyDaysできるような気がする♪』
歌い終わると、花梨はイサトに向かって微笑んだ。
「好きなんだ、この曲。明るくて元気になれるでしょ?」
イサトが穏やかに微笑んで頷く。
「歌詞も、幸せだあって叫んでる感じで好き。私も今、イサト君とつきあえて幸せだから。」
花梨がそう言って頬を染めた。
「こんな情けねぇのに?」
イサトが自嘲的な顔をした。
花梨が首を傾げる。
「イサト君が情けないなんて思ってないよ?」
イサトは、しばらく黙って自分の膝を見つめていたが、急に顔を上げて曲目リストをめくり出した。
「これが俺の返事。」
そう言ってリモコンを操作する。
イサトが、いつになく真面目な顔で丁寧に歌い出した。
『花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えたキセキ♪』
花梨が、わあっ、と感嘆の声を上げる。
初めて聴くイサトの歌は、素人にしては上手かった。
花梨が両手を胸に当てて目を閉じる。
『いつまでも守りきれるだろうか泣き笑い怒る君の表情を♪』
『だから僕は精一杯生きて花になろう♪』
イサトが歌い終わると、花梨は満面の笑みで拍手をした。
「イサト君上手だね!」
「そうか?」
イサトが照れ笑いを浮かべる。
「うん!それに・・・すごく嬉しい返事で、感激しちゃった。」
花梨が潤んだ瞳でイサトを見上げた。
イサトが微かに頬を染めて、自分に言い聞かせるように話し出した。
「俺さ、お前のこと泣かせたり、怒らせてばっかだし、自分の気持ちとか上手く言えねぇけど・・・お前に会ってから、こんな風に考えるようになったんだ。まだ考え中だけどさ。」
「考え中って?」
イサトがテーブルを見つめて、考えながら答える。
「俺、お前と違って夢とかねぇから、進路とか、あんま考えてなかったんだ。」
花梨が目を丸くする。
「親は、いい大学に入って、いい就職すればあとがラクだって言うけどさ・・・花梨、いい就職ってどこだ?」
「え・・・大企業、とか?」
「大企業だって今どんどん潰れてるだろ?そういうニュース見るとやる気なくすんだよな。いい就職が何なのかも分かんねぇし、どこに就職したってこれからどうなるか分かんねぇって思う。」
花梨は慌てて反論しようとしたが、イサトの言う事ももっともで、何も言えない。
「一生懸命勉強して大企業入ってもさ、そこが潰れちまったら元も子もねぇじゃん。そんだったら、適当にフリーターでもして、好きなギター弾いて暮らしてた方がよっぽどラクだって思ってた。」
花梨が悲しそうにイサトを見た。
「だけどさ、お前の夢とか聞いて、夢が叶うかどうか分からなくても頑張ってるお前見てたら、俺、自分が恥ずかしくなってきてさ。潰れるかどうかも分かんねぇ大企業の事でグダグダ言ってるの、かっこわりぃと思った。そんなんじゃ、お前を守れねぇって思った。そん時に、コンビニでこの歌がかかってるの聴いたんだ。」
イサトが顔を上げて花梨を見る。
「今を精一杯生きなきゃ、せっかく出会ったお前にわりぃって意味の歌詞が、すげぇしっくり来た。俺も、精一杯生きようと思う。何をするのが精一杯生きるってことなのか、けっこう難しいけどさ・・・とりあえず今の俺にできる精一杯は、ちゃんと進路決めて、大学行くコトだと思うから。」
「・・・うん。私もそう思う。」
花梨が嬉しそうに頷いた。
「今はその進路を考え中。決めたら一番にお前に言うから。待っててくれるか?」
「うん!」
花梨が元気良く頷いてイサトの腕に飛びついた。
イサトがギョッとして花梨を見下ろし、そのまま固まった。
「私、嬉しいよ。イサト君。」
花梨が甘い声で言ってイサトの肩に頭をつける。
イサトは耳まで赤くなって、ごくり、と唾を飲んだ。
花梨の柔らかい胸が、微かに腕に当たっている。
イサトの全神経が、徐々にそこへ集中しはじめていた。
腕をもう数センチ動かせば・・・
そうすれば、花梨の胸の感触をもっと強く味わうことができる。
どう動かせば自然に花梨の胸に触れられるだろうか、そんなことばかりぐるぐると考える。
イサトがもう一度、ごくり、と唾を飲んで、腕を動かそうとした瞬間、電話が鳴った。
「うわっ!」
イサトが飛び上がって花梨から1メートルほど離れた。
花梨が目を丸くしてそれを見る。
イサトはそのままギクシャクと立ち上がると、受話器を取った。
もう出ます、と短く答えて元に戻し、壁に両手をついてうなだれる。
「ビビった・・・」
それから、自分の邪な考えが花梨にばれていないか心配になり、恐る恐る振り返る。
キョトンとしている花梨の瞳を見て、イサトはホッと息をついた。
「・・・帰るか。」
戻ってきて脱いであった学ランを羽織る。
花梨もコートを羽織って、ボタンを留めた。
イサトは、テーブルの上のリモコンを持つと、ドアのそばで花梨を待った。
花梨が身支度を終えてイサトのそばに歩み寄っても、イサトはドアを開けずに花梨を見下ろしていた。
花梨が、外へ出ようと促すようにイサトのすぐそばまで歩み寄る。
それでも、イサトは外に出なかった。
すぐ近くに花梨が居る瞬間を、終わらせたくない。
あんなに恥ずかしかった二人きりの空間から、今は、出たくない、と思う。
花梨が、何も言わずにイサトを見上げる。
花梨にも、もっとイサトのそばに居たいという気持ちがあるのだ。
イサトは切なげな花梨の瞳に見上げられてドキリとした。
「・・・忘れ物ないか?」
誤魔化すように口先だけで言いながら、花梨を抱きしめてしまおうか、と迷う。
花梨は、イサトが上の空で言っている事に何となく気付いたが、律儀に部屋を振り返った。
微妙な雰囲気に、少し戸惑いながら答える。
「うん・・・大丈夫・・・」
花梨の瞳から解放されたことで、イサトの照れが薄れた。
部屋を振り返っている花梨に一歩近づく。
振り返っていた頭を元に戻した花梨は、目の前にイサトの肩があって慌てた。
すぐにその肩が視界から消えて、目の前が壁だけになる。
と同時に、鼻にイサトの肩がぶつかって、状況を理解し、心臓が跳ね上がった。
一瞬で血液が駆け巡り、全身の感覚が麻痺してから、順番に感覚が戻っていく。
イサトの腕が触れる背中。
イサトの身体に押し付けられて、初めて知る自分の胸の質量。
イサトの匂い。
そして、ぬくもり。
長い時間だったのか、一瞬だったのか、やっと全身の感覚が戻った頃、イサトが身体を離した。
イサトの顔を見上げることができず、火照る身体を持て余して俯く。
「・・・ゴメンな。」
頭の上からイサトの優しい声が降ってきて、顔を上げると、イサトはすでに背を向けていた。