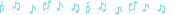
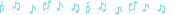
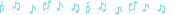
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

お兄さん
花梨が平安団地前のバス停を降りると、千歳が手を振りながら走ってくるのが見えた。
花梨もそちらへ走り出す。
話ができる距離まで近づくと、花梨が口を開いた。
「ゴメンネ、千歳、無理言って。」
「いいのよ。私も楽しみだったから。友達が家に来るなんて、小学校以来よ。」
千歳が花梨を促して歩き出す。
「そうなんだ?」
「だってウチ、狭いもの。お兄が居るって言うと友達も引くし。花梨がお兄を見たいって言うから呼べたのよ。」
「よかったあ。なんか迷惑だったかなあって、けっこう気にしてたんだよね。」
「なあに?あなたらしくないわよ。」
「そうかなあ?」
花梨がえへへ、と笑うと、悪戯っぽい顔をしていた千歳も微笑んだ。
同じ形の建物が続く敷地内へ入る。
建物と建物の間には、駐車場や小さな公園が設置されていた。
子供達が駆け回り、その母親と思われる人達が固まって、おしゃべりに花を咲かせている。
「この団地に来るの初めて。」
「あら、そう?・・・あれがイサトが住んでる棟よ。で、こっちが私の住んでる棟。」
建物沿いに少し高くなっている細い道を歩いてから、建物の階段を登り始める。
「家が近いって、そういう事だったんだ!」
「イサトが団地って知らなかったの?」
「うん。まだ知り合ってそんなに経ってないんだよね。」
「そんな風に見えなかったけど・・・ま、イサトはそういう奴よね。誰にも物怖じしないって言うか。すぐ仲良くなっちゃうでしょ?」
「そうそう。よく知ってるね。」
「お兄と仲がいいのよ。」
そう言いながら千歳が鍵を開けて重そうなドアを開けた。
「どうぞ、入って。」
千歳がドアを押さえて花梨を先に家に入れる。
「お邪魔します。」
花梨が靴を脱いで上がると、奥から千歳を年配にしたような女性が出てきた。
「いらっしゃい。」
「こんにちは。」
「うれしいわあ。うちの子にお客様が来るなんて、頼忠さん以来よ。ゆっくりしていってね。」
「頼忠さん?」
花梨が聞き覚えのある名前に、怪訝な顔をする。
「お兄のカテキョーよ。お母さん、内輪ネタなこと言わないで。それより、お兄は?」
千歳が玄関を入ってすぐのドアを開けながらそっけなく言葉を吐く。
いつもの事なのだろう、まったく気にしない様子で千歳の母親が奥を振り返った。
「ああ、タバコタイムよ。」
「もう、あれだけ虐げられてもやめられないのね。」
千歳が憮然とした声で言って部屋に入っていった。
花梨が興味津々で奥を見ると、リビングらしい部屋の向こうで窓がカラカラと開く。
ベランダからのっそりとリビングに降り立った人物を見て、花梨は目を見開いた。
「勝真さん・・・」
勝真がタバコの箱をポケットにしまいながらこちらを向いて、愕然とした顔をする。
「なっ・・・花梨じゃないか!・・・千歳の友達って花梨だったのか?!」
勝真の声を聞きつけて、千歳が目を丸くして部屋から出てくる。
「なあに、あなた達、知り合い?」
千歳と千歳の母親が、同時に同じ口調で言った。
花梨が帰り支度をして千歳の部屋から出ると、隣の部屋のドアが開いて勝真が顔を出した。
「なんだよ、一度帰るのか?」
「はい。」
「もう少しゆっくりして、店まで一緒に行かないか?」
「教科書とか重いから一度帰るつもりで楽譜持ってこなかったんです。」
「そっか。じゃあ、家までバイクで送ってやるよ。」
そう言って勝真は、ドアを開いたまま部屋の奥へ戻る。
床に雑誌と服が散らばる勝真の部屋が見えて、花梨はなんとなく気恥ずかしくなり頬を染めた。
「あ、ありがとうございます。」
「お兄、大事な花梨を乗せて事故んないでよ。」
部屋から出てきた千歳が憮然とした声を出した。
「当ったり前だろ。オンナを乗せて事故るかよ。」
鍵を持った勝真が言いながら部屋から出てくる。
「下品な言い方しないで。」
「へいへい。」
そう言って勝真は肩をすくめると靴を履く。
花梨はガラスの扉が閉まったリビングの方へ向くと、千歳の母親に聞こえるように挨拶した。
「お邪魔しましたー!」
千歳の母親がエプロン姿で扉の向こうに出てくると、にっこり笑って手を振った。
花梨が頭を下げてから玄関を降り、靴を履いて千歳に向き直る。
「じゃあね、花梨。気をつけて。」
「うん。バイバイ、千歳。」
「気をつけなくても、俺がついてるから大丈夫だ。」
勝真が胸を張る。
「お兄が一番危険なの!」
千歳が腰に手を当てて勝真を睨んだ。
勝真がうなだれながら玄関のドアを開ける。
兄妹のやり取りにクスクスと笑う花梨と一緒に外へ出た。
ドアが閉まって手を振る千歳が見えなくなるまで花梨はブンブンと手を振り続ける。
そんな花梨を優しい目で見ていた勝真が、完全にドアが閉まると口を開いた。
「しっかし、驚いたな。」
先に歩き始めた勝真の後ろで歩き出しながら、花梨が頷く。
「そうですね。あこがれのお兄さんが勝真さんだったなんて、びっくりです。」
あこがれ、という言葉が嬉しくて、勝真がにやりと笑った。
「やっと分かったぜ。」
「何がですか?」
「お前に会った事があるような気がした理由。」
「ああ!」
出会ってすぐに勝真がそんな事を言っていたのを思い出す。
「千歳の入学式の集合写真見て、お前に目をつけてたんだ。」
勝真の言葉に花梨は頬を染める。
どう言葉を返せばいいのか分からず、慌てて他の話題を探した。
「あの・・・えと・・・そう言えば、頼忠さんって、勝真さんの家庭教師だったんですか?」
「ん?ああ、そうだよ。」
「頼忠さんが先生なら、勉強もはかどったでしょう?」
「う・・・」
階段を降りて駐輪場へ歩きながら、勝真が言いにくそうに口ごもる。
「え?」
見上げる花梨の澄んだ瞳に観念したように勝真が話し出す。
「その頃は頼忠も今以上に融通のきかない奴だったし、俺もワルだったから、ケンカばっかしてた。」
「ええっ!想像できない!」
「そうか?・・・頼忠の奴さ、初日っから俺の腕見て『なんやそのイレズミ!それで学校行っとるんか?』とかキレてさ、俺もムカついたから『そんなミナミのヤクザみたいな言い方したって怖くねえよ!』って言い返したんだよな。そしたら、次の時から標準語になって、その上、竹刀持ってきやがった。」
花梨がくすりと笑って言う。
「関西弁はワザとじゃなくて、地だったんですね。けっこう傷ついたのかもしれませんよ?」
「そうかもな・・・言われてみれば頼忠はずいぶん変わった。」
勝真が少し申し訳なさそうな顔をした。
立ち止まると、ポケットから鍵を出す。
「でも、勝真さんも変わったんじゃないですか?」
「そうだな。ワルやって粋がってたって、あいつみたいに・・・よいしょ・・・本当に強い奴には勝てねえって分かったんだよ。」
言いながら大きなスクーターを道路に出した。
「強い?頼忠さんが?」
「ああ。竹刀持たせたら無敵だけどさ、素手でも俺は勝てねえよ。」
それは二人が拳で語り合ったことを示していた。
「へえ・・・」
「だから、粋がるのはやめた。タバコはやめられねえけどな。」
そう言ってシートの下からヘルメットを二つ出すと、赤い方を花梨に渡す。
「ありがとうございます・・・っくしゅん!」
渡されたヘルメットをかぶろうとした花梨が、突然くしゃみをした。
「どうした?」
「なんか、香水の匂いが強くてツンときちゃいました。もしかして、彼女さんのヘルメットですか?」
勝真は一瞬言葉に詰まったが、諦めたように続ける。
「・・・ああ、そうだ。香水臭くて被れないか?」
花梨は笑顔を作るとヘルメットを被った。
「いえ、もう大丈夫です。」
「すまない。」
勝真が辛そうな顔をして背を向け、バイクに跨るとヘルメットを被る。
花梨も微かな胸の痛みを堪えながらバイクに跨った。
遠慮がちに勝真のジャンパーをつかむ。
「お前なあ・・・ちゃんとつかまれ。」
勝真はそう言って背中に両手を回し、花梨の両手をつかむと無理やり自分の体の前に持ってくる。
花梨は勝真の背中に倒れこむような形になった。
タバコの匂いの混ざった勝真の体臭が、ヘルメットの中に充満する濃い香水の匂いをかき分けて花梨に届く。
勝真の背中が大きく動くと、バイクが走り出した。
花梨は後ろへ持っていかれるような感覚がして勝真につかまる腕に力を込める。
勝真の背中の暖かさが胸に伝わってきた。
さっきからチクチクと痛む心に、その暖かさが染みる。
花梨はそんな思いを振り払うと、勝真に聞こえないように小さく呟いた。
「なに期待してんの・・・私のバカ。」