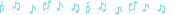
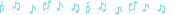
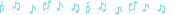
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

いーかげん
千歳はいつも、校門を出ると必ず携帯電話をチェックする。
クラスや予備校の友達とメールのやり取りをしているらしいのだが、花梨はメールよりも会って話をする方が好きなので、校門を出た途端に携帯を見るほど頻繁にメールが来るわけではない。
一応、千歳の真似をして携帯電話を取り出す。
珍しく、チカッと着信を示すLEDが光った。
「勝真さんだ!」
「え?お兄?合コンの誘いかしら・・・強引な事を言うようならハッキリ断らなくてはだめよ。」
千歳が携帯から顔を上げて眉根にしわを寄せる。
「はーい。」
花梨は苦笑しながら携帯電話を耳に当てた。
『よっ、花梨。部活終わったか。』
「はい。」
『今日、これから暇か?』
「え?これから?」
千歳が腕でバツ印を作るのを見て、花梨も少し悩んでから続ける。
「内容によりますけど・・・」
『なんだ?お前らしくない事言うな・・・あ、そうか、部活の帰りか・・・』
勝真が何かに気付いたらしく少し沈黙したが、再び気を取り直したような声が聞こえてきた。
『別に悪いことに誘おうっていうわけじゃない。お前、ダンスやってみる気ないか?』
「ダンス?」
『この間の悪魔踊りあっただろ?』
「・・・怖い名前つけないでください・・・小悪魔ちゃんです。」
『う・・・と、とにかくアレ良かったからさ、ダンスの基本を少し習ったらもっと良くなるんじゃないかと思ったんだよ。』
「え?そんなすぐに習えるんですか?」
『俺が行ってるフィットネスクラブで友人割引チケット貰ったんだ。今夜7時半から初心者用ジャズダンスのクラスがある。』
「行きます!」
『よし、決まりだ。今からバイクで迎えに行くから、駅前で待ってろ。着替えが要るだろうし、一度お前の家まで運んでやる。靴はこの間のランニングシューズでいいから。』
「お願いします!」
『じゃあな。』
ワクワクした顔で携帯電話を閉じた花梨を、千歳が意外そうに覗き込む。
「合コンの誘いではなかったようね。」
「うん!」
花梨が嬉しそうに頷いた。
「勝真さんも、ダンス踊るんですか?」
Tシャツにハーフパンツの姿で更衣室から出てきた花梨は、既に着替えを済ませて更衣室の前で待っていた勝真に無邪気に問う。
「え?俺も?・・・いや、それは勘弁してくれ・・・」
勝真が言いながら先に立って歩き出した。
後ろをついて歩きながら花梨が首を傾げる。
「どうして勘弁なんですか?」
「女ばっかで恥ずかしいんだよ。」
「へえ〜、勝真さんもそんなこと気にするんだあ。」
そう言ってくすくすと笑う花梨に勝真が挑戦的な顔で振り向いた。
「悪いか。」
花梨の頭をわしづかみにして髪の毛をくしゃくしゃとかき回す。
「やぁーっ!ごめんなさい、ごめんなさい!」
花梨が笑いながら肩をすくめた。
勝真もその様子にニヤニヤと笑みを浮かべたが、すぐに切なげな顔になって背を向ける。
花梨も笑顔を消し、勝真の背中を辛そうに見つめた。
「最初はストレッチからな。」
ストレッチマットに向かいながら、勝真は微かにため息をついた。
勝真の言葉を聞いて、花梨も先ほどの話を続ける。
「ダンスをしないってことは、勝真さんはいつも何をしてるんですか?」
「俺?・・・俺は、筋トレ。」
「へえ?」
「頼忠の真似して、何か武道をやろうと思ってさ・・・高校の時にラクそうだと思って弓道部に入ったんだ・・・。意外に集中力がつくから、今も続けてるんだけど、右だけ筋肉がついちまうのが難点なんだよな。」
前を歩く勝真のノースリーブから覗く腕は、確かに右だけ太かった。
「ホントだ!」
花梨が目を丸くする。
勝真は、シューズを脱いでストレッチマットに上がると、腰に手を当てて言った。
「だから、右腕以外の全身にも均等に筋肉つけようと思った。それだけ。さ、ここに座れ。」
花梨がキョトンと勝真を見る。
「へ?」
「俺がストレッチを教えてやるよ。」
勝真がニヤニヤしながら、花梨の目の前で両手をサワサワと動かす。
「勝真さんのエッチ!」
花梨が大声を出したので、周りでストレッチをしていた他の客がチラリと勝真を振り向いた。
「お、おい、冗談だって・・・頼むよ、花梨・・・」
勝真が情けない声を出し、憮然とした顔をした花梨がシューズを脱ぎマットに座る。
勝真はその後ろに回ると、花梨の背中を程よく押しながら、微かに微笑んだ。
勝真の言葉や態度に対する花梨の反応は、いつでも勝真を驚かせ、慌てさせる。
いつの間にか、その幼く可愛らしい反応に翻弄されている自分を快く思う勝真が居た。
「ん・・・」
身体が伸びる気持ちよさから花梨が声を漏らす。
その声に反応してしまった勝真が、慌てて自分を責める。
今朝、彼女の部屋から帰ってきたばかりなのに。
ベッドの中から自分を見送る彼女の疲れた瞳を思い出す。
帰り際に、飽きたのね、と言われた。
自分では気付かなかったが、最近の交わりが雑だったのだろうか。
勝真はためらいもなく別れのセリフを選び始める。
彼女はどちらが辛いだろうか。
飽きたと言われるのと、他に好きな女ができたと言われるのでは。
花梨の家の門前で勝真がバイクを停めると、花梨がバイクから降りた。
赤いヘルメットを外して、ぺこりと頭を下げる。
「今日は本当にありがとうございました。」
勝真もヘルメットを外すと、バイクから降りた。
シートの下を開けて花梨の荷物をとり出す。
「また行こうぜ。」
花梨から受け取ったヘルメットを収納しながら、勝真は何気なく言ったが、花梨からの返事はなかった。
勝真が花梨に荷物を渡そうと振り向くと、花梨は辛そうに顔を伏せていた。
「私・・・行けません。」
「ん?ダンスがキツかったか?」
勝真が花梨の荷物を持ったまま、花梨を気遣うような顔をする。
「いいえ・・・すごく楽しかったし、振り付けも参考になるし、また行きたいです。でも、次からは一人で行きます。」
「・・・俺が嫌いか?」
勝真が苦い顔になる。
花梨が首を振った。
「・・・彼女さんに悪いから・・・」
「そうか・・・そうだな・・・」
勝真が痛々しい顔で、花梨から目をそらした。
花梨が行けないと思う理由はそれだけではない。
花梨は、ダンス終了後に勝真の様子を見て、高鳴る心臓を抑えられなかった。
黙々とマシントレーニングを続ける勝真は、普段あまり見せないストイックな表情をしていた。
これ以上、勝真の新しい面を見せられて、ますます好きになってしまうのが怖い。
勝真はしばらく黙っていたが、急に花梨の荷物をバイクの上に置いて携帯電話を取り出すと、操作しはじめる。
「今から別れる。」
「な・・・だめですよ!」
花梨は驚いて勝真の腕に飛びつくと、通話ボタンを押そうとしていた親指を握る。
「何でだよ?」
「何でって・・・」
至近距離で見つめてくる勝真の瞳には、花梨が初めて見る真摯な光が宿っていた。
「お前の方が好きになっちまったんだからしょうがないだろ。」
花梨の身体がビクンと跳ねた。
遠い門灯の明かりでも、頬が染まっていくのが分かる。
勝真は黙ってしまった花梨と見つめ合ったまま、畳み掛けるように言う。
「お前は?」
「でも・・・」
「お前はどうなの?」
「だって・・・」
弱々しく首を振る花梨の瞳から涙がこぼれたのを見て、勝真の頭に血が上る。
いきなり花梨の頭をつかむと口付けた。
頭をつかまれた衝撃でとっさに目を閉じた花梨は、唇に柔らかいものが当たっているのを感じて不思議に思う。
少しずつ全身の感覚が戻り、まず勝真に頭を叩かれたのではないらしいことを理解する。
次に唇に当たっているものが何であるかの予感に身体が震える。
頭の後ろにあった勝真の手が顎の下に回り、ぬるぬるしたものが花梨の唇を割って入ろうとした。
予感が確信に変わり、花梨は慌てて飛び退く。
目の前で舌を引っ込める勝真の不敵な顔に怒りが込み上げて、とっさに手が出た。
頬の感触が残る掌を、痛さに振りながら勝真を睨みつける。
「そんないーかげんな気持ちで好きだなんて・・・彼女さんがかわいそうです!」
バイクの上から自分の荷物をひったくると、振り返りもせず玄関へ走り出す。
残された勝真は、花梨に叩かれた頬に手を当てたまま、しばらく呆然と突っ立っていた。