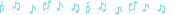
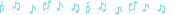
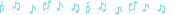
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

夕日
体育館の舞台下に設置されたベニヤ板の雛壇には、パイプ椅子が扇形に並べられていた。
雛壇の下には客席よろしくパイプ椅子が並べられている。
勝真は体育館入り口に設置された受付で小さな紙に刷られた案内をもらうと、ビデオやカメラを構える父兄にまぎれて後ろのほうの席に座った。
小さな花束を、そっと隣の椅子に乗せる。
ブザーが鳴り、体育館の電気が消えた。
幕が開いて、吹奏楽部員が舞台袖から列を作って出てくると、雛壇に降り立つ。
右袖からトランペットを持った花梨が出てくるのを見つける。
緊張に青ざめているのを見て、勝真は苦笑した。
左袖からホルンを持った千歳が出てくる。
こちらは中学生の時から何度も舞台を踏んでいるので、堂々としたものだ。
チューニングが始まった。
人数が多いせいなのか、いつも機械と泰継任せのチューニングをしている勝真が聞いても合っていないように思える。
泰継はこの場に居られないんじゃないか、と苦笑を深くした。
花梨に目を移すと、トランペットを掲げて一生懸命音を出す様子が、ひたむきで可愛い。
勝真は、ただ切なげに花梨を見つめていた。
あの一件があってから、勝真は花梨に避けられていた。
電話をかけても出てくれないし、練習でも殆ど目を合わせてくれない。
当然だろう、と勝真も思っている。
しかし、あれは一時の気の迷いや、花梨が言うようないい加減な気持ちでしたキスではない。
本気だった。
花梨の涙を見て本能的に身体が動いた。
そんな事は初めてだった。
ま・・・舌を入れたくなっちまったのはご愛嬌・・・と勝真が一人で頭をかく。
あの時の花梨の態度で、8割方、花梨の気持ちもこちらへ向いているのは分かった。
あとは花梨に自分の気持ちを分かってもらうまでだ。
それには、何としても花梨と話をする必要がある。
花梨に惚れている素振りを見せる他のメンバーの邪魔が入ると面倒だ。
練習以外で花梨に接触して捕まえるチャンスは、この文化祭しかない。
千歳が中学最後の文化祭の日に花束を抱えて帰ってきたことを思い出し、駅前の花屋で花束を買った。
勝真は最初、千歳が持っていたような一抱えもある花束にしようと思って花屋に入ったのだが、色とりどりの花に囲まれて大いに戸惑い、結局、店頭のミニブーケを買うことしかできなかった。
キザな男のプロポーズじゃあるまいし、小さい花梨にはこの位が丁度いいんだ、と腕組みをして頷く。
後ろに座っていた女子中学生の二人組が勝真を指差してクスクスと笑った。
クラシックのみの第一部が終わり、休憩の間に部員達は舞台の袖を通って女子更衣室へ移動していた。
次はジャズやポップスで構成される第二部なので、部費で作ったパーカーに着替えるのだ。
千歳が前を歩いていた花梨の肩を叩く。
「まだ調子悪いみたいね。大丈夫?」
「うん・・・」
「この前から何度も言ってるけど、限界が来たら早めに休みなさいよ。」
「ごめんね・・・」
「私に謝ることじゃないわ。」
千歳は、そう言って微笑んだが、花梨は悲しげに笑っただけで、再び黙ってしまった。
花梨は千歳に心配を掛けていることに対して、申し訳なく思っていた。
勝真との一件のせいで悩んでいるとは、千歳には言えない。
花梨が勝真にファーストキスを奪われたと知ったら、怒り狂って勝真を家から追い出してしまいかねないからだ。
花梨は、そんな目に遭わせるほど勝真が悪いとは思っていなかった。
あのあと、部屋に戻ってから、冷静になるにつれ、勝真の唇の感触ばかりが思い出された。
強引だったけれど、花梨のファーストキスを奪ったのは、まぎれもなく心から好きな男性だ。
あれから何度も電話がかかってくるし、練習中も勝真の視線を感じていた。
しかし、心のモヤモヤが晴れるまで、勝真とは話したくなかった。
だが、そのモヤモヤの正体が花梨にもはっきりと分からない状態では、晴れるはずもない。
アンコールの曲が終わり、体育館の明かりが点いた。
ザワザワと笑いさざめきながら立ち上がる父兄の中で、勝真も立ち上がり、雛壇へ向かって歩き出す。
いったん舞台袖に引っ込んだ部員達が再び出てきて譜面台を片付けはじめた。
演奏を見に来た友達と写真を撮っている部員も居る。
トランペットを腕にかけ、雛壇の一番高い段で譜面台をたたむ花梨に、勝真が雛壇の下から声をかけた。
「花梨!」
花梨が顔を上げる。
声をかけたのが勝真と知って愕然とした顔をすると、慌てて舞台袖に隠れた。
周りに居た女子生徒の何人かが花梨を追って袖に入る。
「花梨ちゃん、何?あの人!」
「チョーかっこいいじゃん!彼氏?」
舞台袖からキャーキャーと騒ぐ女子生徒の声が聞こえてきた。
聞こえてるよ、と勝真が呆れた顔をする。
少し前までの勝真ならどうだったか分からないが、今となっては花梨以外の女の存在はウザイだけだ。
仕方ない、取次ぎを頼むしかなさそうだ、と千歳を探す。
勝真は内心ビクビクしていたのだが、花梨が何も話していないらしく、今朝までの千歳の様子に変化は見られなかった。
千歳は、指揮台の向こう側で金髪の女性に話しかけられていた。
名刺を渡されて戸惑った顔を上げる。
女性はにっこりと色気たっぷりの笑みを残し、そのまま去っていった。
それを見送ってから、勝真が千歳に声をかける。
「千歳。」
「あ、お兄?なんでこんな所に居るの?」
「見に来たんだよ。今の誰だ?」
「オニーレコードのシリンとか言う人よ。」
「ふーん、天下のオニーが何だって?」
「私のことが気に入ったとか何とか。」
「すごいんじゃないか、それ。」
「かもね。」
さして興味もなさそうに千歳が名刺をポケットに仕舞う。
勝真も、今はそれどころではない。
「それより、花梨を呼んできてくれないか?」
千歳が不思議そうに勝真を見つめる。
ぎこちなく目をそらした勝真が、小さな花束を持っているのを見て、千歳は薄笑いを浮かべた。
「ふーん、なるほどね・・・」
そう言い残すと、雛壇を上がって舞台袖に入っていく。
千歳が舞台袖に入ると、花梨が泣きそうな顔で部員に囲まれていた。
「彼氏じゃないなら紹介してよ。」
「独り占めなんてズルイじゃん。」
花梨につめよる部員達に、千歳が後ろから落ち着いた声を出す。
「先輩方、あれは私の兄です。女性関係にだらしなくて困ってますの。千人斬りの一人に数えられたいのでしたら、喜んで斡旋いたしますわ。」
花梨に詰め寄る部員達が絶句して千歳を振り向いた。
千歳は、せんにん・・・と呟いて青くなる花梨の腕を引いて舞台袖から出ると、耳打ちしながら雛壇を降りる。
「ウソも方便よ。あのお兄に、そんな甲斐性あるわけないでしょ。それよりあなた・・・お兄と何かあったのね。」
花梨が申し訳なさそうに頷いた。
「お兄もここのところ、ため息ばかりついてたのよね・・・花梨、親友に秘密を作ったお仕置きよ。一人で悩んでないで、きちんと話し合いなさい。」
千歳が少し厳しい声で言って、花梨を勝真の前まで連れて行く。
気まずそうに目をそらす花梨の胸に、勝真が花束を押し付けた。
「花梨、お前に話がしたい。」
花梨が弱々しく花束を受け取る。
「千歳、コイツ拉致ってもいいか?」
「6時から打ち上げだから、それまでに駅前へ返して頂戴。」
千歳が花梨の腕にかかったトランペットを取り上げながら、事務的に言った。
「了解。」
勝真はそう言うと、慌てて千歳からトランペットを取り返そうとする花梨を軽々と抱き上げる。
「きゃ・・・ち、ちとせぇ〜・・・」
花梨の助けを求める声に、千歳は勝真を睨んで低い声を出した。
「花梨にエッチなことしないでよ。」
「・・・分かった。」
勝真が渋々頷いて背を向ける。
歩いていく勝真の肩越しに不安そうな瞳を覗かせる花梨を見て、千歳の頭にドナドナが流れた。
思わずクスッと吹き出して小さく手を振る。
ふと、視線を感じて周りを見回した。
体育館に居る者のほとんどが勝真を見ている。
「お兄・・・カッコつけすぎ。」
千歳は呆れた声で呟いたが、すぐに嬉しそうに微笑んだ。
何かを諦めたような態度ばかりだった兄が、今、かつてない強引さで親友を攫って行く。
勝真がバイクを止めたのは、山の中腹にある駐車スペースだった。
平安市内の子供たちが遠足に行く程度の小さい山は、人や車が通ることもあまりない。
花梨が白いヘルメットを取ると、右側の山間に夕日が沈もうとしていた。
眼下には平安市が広がっている。
「夕日でも見ながら、落ち着いて聞いてくれないか。」
言いながら、勝真が風下でタバコに火をつける。
「勝真さん、これ、ありがとうございます・・・」
花梨がヘルメットを勝真に渡そうとすると、勝真がタバコを持っていない方の手をシッシッと振った。
「コラ、近寄るな。煙を吸ったら大事な喉をやられるぞ。」
花梨は大人しくヘルメットを持ったまま離れ、石でできた簡易ベンチに腰掛ける。
「それと、そのヘルメットはお前専用だから返さなくていい。」
悲しげな顔になった花梨が黙ってヘルメットを撫でた。
バイクに乗る時に勝真から渡されたのは、香水くさい赤のヘルメットではなく、新品の白いヘルメットだった。
その時に花梨はなんとなくその意味を理解したが、悲しくなった。
あの赤いヘルメットは、捨てられてしまったのだろうか。
だとしたら、勝真は、彼女も、ヘルメットのように簡単に捨ててしまったのだろうか。
「俺・・・」
バイクに寄りかかって、携帯灰皿に灰を落としながら、勝真が口を開いた。
「初めて女と付き合ったのは中2の時だった。両親に期待かけられてたのに随心の中等部に入れなくて、自分が嫌になってさ・・・いわゆる不良グループってやつに入ってから1年ぐらい経った頃だったかな。」
花梨が俯いたまま眉を寄せた。
勝真は携帯灰皿を見つめながら淡々と語る。
「女連れだとカッコイイからっていう理由だけでグループの中の女と付き合って、そのまま興味本位でセックスして、半年もしないうちに別れた。それからは、ほとんど同じことの繰り返し。頼忠のお陰でワルやめて、なんとか平安高に入ったけど、女に対する考え方は、あんまり変わんなかった。頼忠はソッチの方疎いみたいで、俺の女関係については、赤くなって『だらしがないことをするな。』としか言わなかったんだよな。」
いつの間にか花梨は青ざめてヘルメットを強く抱きしめていた。
勝真がタバコを吸うとため息と共に煙を吐き出す。
「すまない、花梨。嫌な話聞かせて。お前が言うとおりだったんだよ。今までいーかげんな気持ちで女と付き合ってきたことを、俺はお前にひっぱたかれて、はっきり知ったんだ。」
花梨が堪えきれないという風に、ヘルメットへ額をつけた。
「でもな、今までの女に謝るのもおかしい気がするんだ。俺は確かに、そのいーかげんな気持ちってやつを恋だ愛だと思ってそいつらを抱いてた。」
花梨がゆっくりと顔を上げる。
勝真は何かを思い起こすように沈む夕日を見つめていた。
「お前に出会うまで、本当に好きだという気持ちがどういうものか、知らなかっただけなんだ。」
そう言って、花梨を振り向く。
今日初めて、二人の視線が交わった。
「分かってくれ、花梨。俺は、今までも真剣に恋をしてきたってことを。」
花梨が涙を堪えて微かに頷く。
「それと、お前が初めて本気で好きになった女だということも。」
もう一度頷いた花梨の瞳から涙が零れ落ちた。
勝真は慌ててタバコの火を消すと、革ジャンと、Gパンのポケットを探る。
Gパンのポケットからくしゃくしゃになったハンカチが出てくると、諦めたように再びポケットに入れた。
花梨の隣へベンチを跨いだ形で座り、両腕で抱き寄せると、唇で涙を掬い取る。
「・・・タバコくさい・・・」
花梨が頬を染めて照れ隠しの言葉を呟いた。
「お前なあ、こんな時に千歳みたいなこと言うなよ。」
そう言いながらも、勝真は身体を離して、親指で花梨の涙を掬う。
夕日に照らされた花梨の泣き顔を見て、勝真の心を甘い痺れが支配した。
そう。
この痺れは、花梨が教えてくれた感情。
「・・・泣き虫だな。」
勝真が言葉とは裏腹なうっとりした声で呟いた。
優しく花梨の前髪を掌ですくう。
泣き止んだ花梨が、くすん、と鼻をすすると、勝真を見つめた。
「勝真さん、告白してください。」
「おい・・・俺の言ってる意味が分かんなかったのか?」
「ちゃんとしてください。私、告白されたことないんです。」
潤んだ瞳で詰め寄られ、勝真は気圧されて頷く。
「わ、わかった。告白すればいいんだな。」
立ち上がると、バイクのシートを開けて、入れておいた花束を取り出す。
それを見て、花梨が嬉しそうに胸に手を当てながら立ち上がった。
「私、男の人にお花もらったの、初めてなんです。」
勝真も優しく微笑む。
「俺だって、花を買うのなんか初めてだったんだぞ。」
そう言って、花梨の前に立った。
全身で感激を表す花梨を見つめて、勝真は花梨の手を取る。
花束を握らせて、その手を自分の掌で包み込んだ。
「花梨・・・」
勝真は次の言葉を続けようとしたが、じっと見つめてくる花梨の瞳に射抜かれたように思考を止める。
耐えられなくなってその瞳から目をそらす。
「その・・・」
言いながら視線を戻すと、勇気を振り絞って言葉を続ける。
「つまりだな・・・」
心臓が高鳴り、再び思考が止まる。
嬉しそうだった花梨の瞳が、不思議そうに見開かれた。
勝真が片手で顔を覆う。
「だめだ・・・」
今まで星の数ほど囁いてきた愛の言葉が、花梨にだけ言えないというのは、どう考えてもおかしい。
「待てよ・・・もう一回・・・」
一人で焦っている勝真に、花梨は笑いを堪えるような顔になった。
それを見つめて、勝真はもう一度最初からやり直す。
「花梨、俺は、お前を・・・」
そのまま固まってしまった勝真を見て、花梨は堪えきれず吹き出した。
勝真は困り果てて、縋るように花梨を抱きよせる。
「すまない・・・俺、どうかしてる、言えないなんて・・・」
花梨は花束がつぶれないように勝真の首に腕を回すと、勝真の肩に額をつけて嬉しそうに言った。
「もう十分です。」
顔を上げると、勇気を出して勝真の耳に囁く。
「私も、勝真さんのこと・・・大好きです。」
花梨の背中に回っていた勝真の腕に力がこもる。
思い切り抱きしめられて、花梨が苦し気に息を吐いた。
「あ・・・苦しかったか?」
勝真が申し訳なさそうに身体を離す。
花梨がふう、と息をついてから、恥ずかしそうに言った。
「ちょっと苦しいけど、でも、嬉しいです。好きって気持ちが伝わってくる感じがしました。」
それを聞いて、勝真がもう一度花梨を強く抱きしめる。
「もっと・・・俺の気持ちを感じてくれ・・・」
切なげな勝真の声が耳もとで聞こえて、花梨の背筋が痺れる。
「はい・・・」
小さく答えると、花梨は、勝真の暖かい胸の中で幸せを噛み締めた。
勝真が潔く非を認める人物であったこと。
彼が過去を後悔しなかったこと。
自分に全てを打ち明けてくれたこと。
そして、自分を本気で想ってくれていること。
全てが、嬉しい。
過去も含めて彼を好きになりたい。
後悔しない恋がしたい。
「あ、そうだ・・・勝真さん・・・」
苦しげに呼びかける花梨の声を聞いて、勝真が腕の力を緩める。
「もうひとつお願いがあります。」
「なんだ?」
勝真が身体を離して花梨を見下ろす。
「やり直してください。」
「なにを?」
勝真が目を丸くする。
勝真を見上げていた花梨は、目をそらして勝真の胸の辺りを見つめると、頬を染めて呟く。
「私のファーストキス・・・」
勝真がはっとする気配が伝わってきた。
「そうだな。花梨、すまなかった。」
花梨は首を振って顔を上げると、申し訳なさそうな勝真の瞳を見つめてから、静かに目を閉じた。
頬を染めて震えながらキスを待つ花梨を見て、勝真の心に初めての気持ちが押し寄せる。
心を満たしていく敬虔な感情を味わいながら、勝真は小さな唇に優しく口付けた。
そんなキスをしたことがない勝真は、照れくさくなり、すぐに唇を離す。
花梨が勝真の胸に顔を埋めて呟いた。
「ありがとうございます・・・次からは勝真さんの好きなようにしていいですから・・・」
その言葉に、勝真の顔がひく、と引きつった。
「お前なあ・・・珍しく俺がエロ度ゼロだったのに・・・」
勝真の言葉の意味が分からず花梨が不思議そうに顔を上げる。
次の瞬間、花梨の唇は、勝真の唇に再び塞がれていた。
一旦離れた勝真の唇が花梨の唇をついばんで、それを薄く開かせる。
すぐに勝真の舌が花梨の唇を割って入った。
花梨は、息苦しさに耐えながら、必死でそれを受け止める。
勝真の手が花梨の後頭部を撫で、髪を乱す。
「ん・・・」
その感触にゾクリとした花梨が思わず声を漏らした。
甘い声に気を良くした勝真が花梨のパーカーの裾をたくし上げる。
中へと侵入した勝真の手が、花梨のウエストを撫でながら胸へと這い上がった。
「んんっ?!」
花梨は花束を持っていない方の手で力いっぱい勝真を押しのけると、飛び退いた。
「んもう!勝真さんってホントにエッチなんだから!」
息を荒げてパーカーの裾を引っ張ると勝真を睨む。
敬虔な感情はどこへやら、勝真はいつものニヤニヤ顔で花梨を見ていた。
「好きにしていいって言っただろ?・・・あ、近くにいい所があるんだ。続きしようぜ。」
いきなり身を翻した花梨は、駐車スペースの端まで走って行ってしまった。
「お、おい、花梨・・・何も取って喰おうってわけじゃないんだからさ・・・」
遠くで花梨が勝真を睨む。
「だって続きって言った!」
「続きはするけどさ・・・」
「同じコトなの!」
勝真は深くため息をついて、ベンチに座ると独りごちる。
「全然違うんだぞ・・・俺は優しいのに・・・」
警戒しながら戻ってきた花梨が、遠慮がちに口を開く。
「それに・・・一応、性病の検査してください・・・」
「・・・分かった・・・」
勝真がガックリとうなだれた。