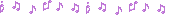
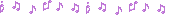
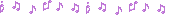
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

私にしか
「あの・・・花梨さん、ご相談があるのですが、よろしいでしょうか?」
頼忠の車に荷物が全て積み込まれたのを見て、泉水が花梨に声をかけた。
「はい、なんでしょう?」
帰り支度を終えてカバンを肩にかけた花梨が笑顔で答える。
「先にジャズの編曲を終わらせましたので、明日からフュージョンの編曲に入るのですが、花梨さんにも何か楽器を演奏していただけたらと思いまして・・・」
「はい!私もやってみたいです!」
満面の笑顔で頷く花梨に泉水がほっとしたように微笑む。
「ありがとうございます。では、演奏経験がある楽器と経験年数を教えていただけませんか?」
「はい。トランペット半年と、ピアノが、えーと・・・6年です。」
泉水が大きなブリーフケースからシステム手帳を取り出すと、メモのページに書き留めた。
花梨が黙ってそれを見ていると、頼忠の車のエンジンがかかる。
もう行かなければ、と花梨が思ったのと同時に、頼忠の車は発進してしまった。
「あれ?」
いつものように送ってもらえると思っていた花梨は、思わず声を上げた。
泉水が驚いたように言う。
「もしかして、お聞きではないのですか?」
「え?何がですか?」
「今日は、私が花梨さんをお送りする事になっています。」
「そうだったんですか?」
花梨が目を丸くする。
可愛い女性のように見える泉水と一緒では、かえって狙われるのではないか、という考えが、ちらりと花梨の頭を掠める。
「申し訳ありません。私のような者では、役不足と思いますが・・・」
「い、い、いえ、そういう訳ではないです。」
慌ててぶんぶんと首を振って否定したが、泉水は悲しそうな顔のままだ。
「おい、帰ろうぜ。」
勝真がそう言って駅に向かって歩き出す。
「そ、そうですね。泉水さん、帰りながら話しませんか?」
花梨が最大級に明るい声で言って泉水を促すと、泉水も頷いた。
「では、私達はここで。」
幸鷹が反対方向に向かって歩き出し、泰継が店の前に置いてあった自転車を跨ぐ。
「お疲れ様でした!」
花梨がぺこりと頭を下げた。
「でもさ、頼忠のヤツ、なんで泉水なんだよ?」
花梨が歩き出すと、イサトも歩き出しながら不満そうに口をとがらせる。
「イサト!」
彰紋が慌てて小声でイサトを制した。
泉水が泣きそうな顔で俯く。
「も、申し訳ありません。」
「あ、いや・・・その・・・そういう意味じゃなくってさ・・・平安神社なら、俺ん家の方が近いんだよ。」
「花梨の家は平安神社の近くなのか?」
「この前、頼忠がそう言ってたぜ。」
「じゃあ、俺達が送って行った方が近いじゃないか。」
「だろ?頼忠のやつ、俺ん家、知らないっけ?」
「いや。この前の打ち上げでお前が潰れた時に車で送ってる。」
「そうだよな?・・・俺は覚えてねぇけど。」
「それに、俺の家には通ってたワケだし。」
「そうだよなあ?」
「やっぱり、泉水さんは従兄弟ですし、頼みやすいんじゃないですか?」
「え?従兄弟?」
ずっと黙って聞いていた花梨が彰紋の言葉に声を上げた。
泉水が穏やかに答える。
「はい。頼忠さんのお父様と、私の父は兄弟なのです。」
「だから、名字が一緒なんですね。」
「はい。」
「ということは、時朝さんも血縁なんですか?」
先日、和仁から名刺をもらった時に思ったことを口に出す。
「はい。年は離れていますが、時朝さんも従兄弟です。」
「そうだったんですか。」
「僕も、泉水さんとは従兄弟なんですよ。」
「えっ?じゃあ、彰紋君の名字も源なの?」
「いいえ。泉水さんのお母様が、僕の父と兄妹なんです。」
「へえ〜。space‐timeって血縁が多いんだねぇ。」
「ま、血縁をつてにメンバーを集めたようなもんらしいからな。」
勝真が自嘲的に言った。
「あ、僕はここで。」
駅が近くなり、彰紋が手を振りながら私鉄の改札口へ歩いていく。
「お疲れさま!」
花梨も手を振った。
会話が途切れたので、そのまま黙って歩く。
駅のロータリーにはバスが何台か待機していて、平安神社の方面へ行くバスも停まっていた。
花梨達がそちらの方へ歩き出すと、後ろからついて来ていた翡翠が口を開く。
「ではね。姫君、気をつけて帰るんだよ。」
「はい。ありがとうございます。」
花梨が頭を下げるのを見届けて、翡翠は駅前にある店の方へ歩いて行った。
平安団地前のバス停で、イサトと勝真はバスを降りた。
一緒にたくさんの乗客が降りていったので、立っていた花梨と泉水は空いた席に座る。
花梨を窓側に座らせてから、泉水が大きなブリーフケースを抱えるようにして座った。
「大きなケースですね。何が入っているんですか?」
花梨が興味深そうにブリーフケースを見つめると、泉水が微笑んでケースを開ける。
中には大量の楽譜が大きさ順に揃えて入れてあった。
「わっ!すごい量の楽譜!これ、全部space‐timeでやる曲ですか?」
驚く花梨に泉水が微笑みながら首を振る。
「いいえ。学校で使う楽譜も入っています。」
「やっぱり泉水さんは音楽関係の学校なんですね。」
「はい。南天音楽大学に通っています。」
「えっ、南天音大?私の志望校です!」
「そうでしたか。では今度、定期演奏会の招待券を手に入れておきますよ。」
「やったぁ!ありがとうございます!」
「声楽科の演奏会でよろしいですか?」
「はい。でも、音楽教育科と、どちらにしようか迷っているんです。」
「では、両方を聞き比べると良いですね。」
「できればそうしたいです。泉水さんは器楽科のフルート専攻でしょ?」
「どうしてお分かりになったのですか?」
「だって、泉水さんのフルート、すごく上手です!」
「そうでしょうか・・・」
突然、泉水は暗い顔になった。
花梨が驚いて泉水を見る。
なぜ泉水がそんな風に思うのか理解できなかったからだ。
泉水が何か言おうとして迷っているようだったので、花梨はそれを待った。
「泰継さんのように高度な技術と才能を持つ方こそが演奏家になるべきだと思うのです。」
「そんな・・・泉水さんのフルートだって、立派な技術ですよ!」
「いいえ。何人もの学生の中で、数少ないオーケストラの募集枠に入れるのは一握りです。私のような中途半端な技術では・・・」
「・・・・・・」
花梨は何も言えなかった。
音楽の世界に身を置いている者として、泉水の言っていることが真実なのは想像がつく。
花梨自身、努力で越えられない才能という壁があることも知っていた。
しかし、それでも自分が歌を歌い続けているのは何故か。
そこまで考えたところで、平安神社のバス停に着いた。
二人でバスを降りる。
「泉水さん、ここでいいですよ。」
「いえ。頼忠さんから、バスを降りてからが危ないと何度も言われましたので。」
「すみません。」
泉水は微かに微笑んで首を振ると、自然に花梨の手をとって歩き出した。
温かい手が花梨の心も温める。
泉水さんはこんな力も持っているのに、と花梨は切ない顔で泉水を見上げた。
「あ・・・ご迷惑でしょうか?」
泉水が手を引っ込める。
「いいえ。泉水さんの手って、すごくホッとします。」
「ありがとうございます。」
安心したように微笑んで、泉水がさっきよりも強く花梨の手を握った。
「泉水さん・・・私も、歌で生きていこうと思っています。」
「花梨さんなら、大丈夫ですよ。」
「いいえ・・・私よりもっと上手い人、たくさん居ると思います。」
「・・・・・・」
泉水は否定しない。
「だからこそ、私は、私にしかできない事を見つけようと思っています。」
「花梨さんにしかできない事・・・ですか?」
「はい。童謡を歌わせるなら花梨じゃないとね、とか、子供と一緒に歌わせるなら花梨だよねって言われるような歌手になりたいんです。」
「・・・・・・」
「泉水さんにも、泉水さんにしかできないこと、いっぱいあると思います。」
「私にも・・・?」
「楽譜が書けるフルート奏者!源泉水!」
急に明るい声で花梨がテレビの司会者のように言う。
「花梨さん・・・」
泉水が歩みを止めたので、花梨も立ち止まり、泉水の両手を取って胸の前まで持ち上げる。
「泰継さんもきっと、泉水さんのこと、すごく頼りにしてますよ。だって、ナチュラルの高速シンセサイザーでしたっけ?・・・あれ、泰継さんが弾くのもすごいですけど、聴き取って楽譜に起こす泉水さんもすごいです。その技術を信頼しているからこそ、泰継さんは何のためらいもなく弾くって言ったんですよ。」
花梨を見つめる泉水の目から涙が溢れる。
「ありがとうございます・・・」
花梨が優しく微笑んで背伸びをすると俯いて涙をこぼす泉水の頭を撫でた。
すると、いきなり腰が引き寄せられ、泉水に抱きしめられてしまった。
「はぅ・・・」
真っ赤になって身じろぎをした花梨だったが、泉水がしゃくりあげたのを聞くと、目を閉じて泉水の背中をあやすように叩いた。