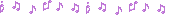
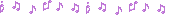
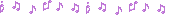
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

悲しい悪意
泉水と花梨は南天音大のキャンパス内を歩いていた。
「今日の演奏会は奥の講堂にある大ホールで行われるのですよ。」
泉水がセカンドバッグから招待券を取り出しながら花梨に微笑みかける。
「大学内にホールがあるなんて、音大ってすごいですね!」
キョロキョロと周りを見回していた花梨が、ワクワクした顔で泉水を見上げた。
「そ、そうですね・・・」
泉水は慌てて目をそらすと頬を染める。
花梨はそんな泉水に気付かず、木々の向こうに見えてきた講堂へ嬉しそうな視線を移した。
今日の花梨は、いつもとはうってかわった清楚な出で立ちだった。
女の子というのは、服装でこうまで変わるものなのだろうか、それとも自分が花梨に恋をしているせいなのだろうか、と泉水は戸惑う。
特に、耳元に揺れる小さな真珠のイヤリングと、誘うような唇に目が奪われてしまう。
泉水は、花梨の横顔をこっそりと見つめた。
泉水から声楽科の定期演奏会に誘われた花梨は、声楽と聞いて、クラシックコンサートに見合うように花梨なりのお洒落をしてきていた。
化粧こそしていないが、ピンク系のグロスだけ唇に塗っている。
やっぱり、グロスだけじゃ子供っぽかったかなあ、でもお化粧すると顔が白くなっちゃって変なんだよね、と周りを見回して微かにため息をつく。
舞台衣装でドレスを着慣れている音大生が、多少派手な格好だがそれに見合う化粧と態度で歩いていく。
その中の一人がキョロキョロしている花梨を見て、クス、と笑った。
ガーン、と花梨がショックを受ける。
笑った女性は泉水に視線を移すと、眉を上げた。
「あら、泉水ちゃんじゃない。」
「あ・・・こんにちは。」
声をかけられた泉水が遠慮がちに微笑む。
花梨は隠れるように泉水の後ろに回ると、小さく会釈した。
「聞いたわよ。招待券の抽選会に来てたんですって?」
泉水の隣を歩きながら、その女性は親しげに話し出す。
「・・・はい。」
泉水が花梨を気遣いながら頷く。
「恵先生に頼めばすぐに手に入るじゃない。」
「・・・そのような不公平な事はしたくありませんので・・・」
泉水が暗い顔になった。
「まったく、そんなんじゃプロの世界でやってけないわよ。」
女性は呆れたように言い放つと、心配そうに泉水を見上げる花梨を見て続ける。
「あなたもウチに入りたいなら、もっと派手な格好してた方が得するわよ。じゃあね、泉水ちゃん。」
そう言って微笑むと去っていった。
「すみません、花梨さん・・・お気に触りましたでしょう?」
泉水が申し訳なさそうに花梨を見る。
「いいえ、泉水さんこそ、何か嫌なことを言われたんじゃないですか?」
気遣う花梨に、泉水が諦めたような顔をして首を振った。
「いつものことです。私の母がこの大学でフルートの講師をしているので、よくそういったことを言われます。でも、彼女の言うことももっともなのです。花梨さんのためなら母の力を使ってでも良い席を取るべきだったかも知れません。」
「そんな、私は見に来れるだけで十分嬉しいですから。不公平な事をして手に入れた招待券じゃ、私も申し訳なくなっちゃう。でも・・・あの人、嫌な感じはしませんでした。」
「はい。彼女は悪い方ではありません。花梨さんの服装のことについても、実は理にかなった意見なのです。芸術は教授の心証によって評価が左右されますから、教授の目に留まる、という意味で派手な格好をする方が得をするとおっしゃっているのですよ。」
「そうなんですか・・・派手な格好か・・・」
花梨がしょんぼりと自分の服装を見回す。
「あの・・・花梨さんのご都合を考えずに私の勝手を言わせていただけるのであれば・・・」
泉水が少し躊躇ったので、花梨が不思議そうに泉水を見上げる。
「・・・花梨さんにはそのままで居て欲しいです。今日の花梨さんは・・・その・・・とてもお美しいですよ。」
泉水が言いながら頬を染めて花梨の手を取る。
花梨もその手を握り返しながら俯いて頬を染めた。
二人が手を繋いだまま、ぎこちない雰囲気を漂わせてホールに入ると、ゴスロリ風の黒いドレスを着た女の子が近づいてきた。
「泉水様、こんにちは。」
そう言うと、泉水を覗き込むように首を傾げる。
茶色く長い髪がつやつやと光を放ちながら、ふわりと揺れた。
「あ・・・姫乃さん、こんにちは。」
泉水が慌てて花梨の手を放す。
姫乃と呼ばれた少女は、少し憮然とした顔をして、上目遣いで泉水を見た。
「お連れの方は、泉水様の彼女?」
「い、いえ・・・」
泉水が慌てて首を振るのを見て、少女が嬉しそうに微笑む。
花梨の胸が痛んだ。
この子も泉水さんの事が好きなんだ、と暗い顔になる。
ずいぶん大人っぽいが、服装から見ても、音大生ではなさそうだ。
「じゃあ、恵先生の愛弟子とか・・・?」
「いえ、花梨さんは声楽を目指していらっしゃいます。」
「ふーん、花梨さんていうんだ・・・。」
少女が花梨を興味深そうに覗き込んだ。
花梨がどぎまぎしながらぺこりと頭を下げる。
「私は姫乃。よろしくね。」
姫乃は小首を傾げて微笑むと、黒いレースの手袋をした手を差し出した。
花梨も慌てて手を出すと、握手をする。
軽く握るだけで、姫乃はすぐに手を放した。
「では、泉水様、ごきげんよう。」
そう言うと、背伸びをして泉水の頬にキスをする。
花梨が目を丸くして固まった。
「ひ、姫乃さん・・・」
泉水が心底困った声で言うと、姫乃はクスクスと笑いながら去っていった。
困った顔のまま、泉水は固まっている花梨に向き直る。
「あの・・・花梨さん・・・姫乃さんは母のフルート教室の生徒で、私とは何の関係もありません・・・信じていただけますでしょうか・・・」
花梨は、はっと気付くと、慌ててコクコクと頷いた。
「カルミナ・ブラーナが全曲聞けるなんて、夢にも思いませんでした!」
興奮した様子で、花梨が泉水を見上げる。
花梨の手をしっかりと握った泉水も嬉しそうに花梨を見た。
「花梨さんに喜んでいただけて、私も嬉しいです。」
「ありがとうございます!泉水さん!」
二人が満面の笑みでホールを出ると、花梨の横から人がぶつかってきた。
「ひゃあっ!」
胸のあたりを冷たいものが大量に伝っていく感覚に、花梨が悲鳴を上げる。
「まあ・・・どうしましょう。私ってばドジねえ。」
ぶつかってきたのは姫乃だった。
手には紙コップを持っている。
そして、花梨のブラウスには大きな茶色い染みができていた。
胸元から紅茶の香りが立ち上る。
花梨はようやく状況を飲み込んだ。
「こ、こちらこそごめんなさい。私も泉水さんばっかり見てて周りを気にしてなかったから。」
ショルダーバックからハンカチを出してブラウスを拭きながら花梨が言う。
何気なく発した花梨のその言葉に、泉水が頬を染め、姫乃が一瞬だけ鋭い視線を花梨に送った。
泉水が姫乃の様子に気付き、唇を引き結ぶ。
花梨にぶつかった角度から見ても、紅茶がこんなに花梨の身体にかかるのは有り得ない。
姫乃の悪意を察知した泉水が、悲し気な顔になった。
「本当にごめんなさいね。花梨さん。一緒に医務室へ行きましょう。風邪をひいてしまうといけないから、そこで服を脱いで布団に包まって待っていて下されば、私、お着替えを買ってきます。」
花梨はその提案に飛びつく。
「あ、ありがとうございます。」
「泉水様、あとはお任せください。」
艶然とした笑みを浮かべて、姫乃は花梨を連れて行こうとした。
しかし、ほっとした顔でついていこうとする花梨の手を、泉水は放さなかった。
「姫乃さん・・・お気持ちはありがたいのですが・・・花梨さんのお世話は、私にさせてください。」
柔らかく、しかしきっぱりと言って、泉水は姫乃を見つめる。
悲しそうに自分を見つめる泉水の瞳が、憐れみを含んでいるのを見て、姫乃の顔がカッと赤くなった。
渦巻く感情を押し殺して残念そうな顔を作ると、花梨に向き直る。
「では・・・今回は遠慮しておきます。本当にごめんなさいね。」
首を傾げながら泉水の様子を見ていた花梨も、姫乃に向き直る。
「ううん、気にしないで。ありがとう、姫乃さん。」
姫乃は、心からの感謝を表す花梨の表情に、完全な敗北を味わいながら背を向けた。
泉水はほっと息をつくと、セカンドバッグからハンカチを取り出して、花梨のブラウスを拭こうとする。
しかし、花梨が再びハンカチで拭き始めた箇所を見て、頬を染めた。
大量に紅茶をかぶったせいで、ブラウスが花梨の素肌に貼りついている。
紅茶の色素で薄く染まった花梨のブラウスから、水色の下着が透けて見えていた。
柔らかそうな胸を覆うレースのデザインまではっきりと目にしてしまい、泉水は息を飲む。
どうして良いか分からず目を泳がせると、二人をじろじろと見ながら通り過ぎていく中年女性と目が合った。
ホールを出る人々が、好奇の視線をチラリと二人に向けながら通り過ぎていた。
泉水は慌ててカーディガンを脱ぐと、花梨の肩に掛けて袖を花梨の胸の前で結ぶ。
誰にも見せたくない。
泉水の中に強い意志が湧き上がる。
「あ・・・ありがとうございます。泉水さん。」
花梨が泉水のカーディガンをかき寄せると縮こまる。
「このままでは風邪をひいてしまいますね。タクシーでお家までお送りしましょう。」
そう言うと、泉水は花梨の肩を抱いて優しく引き寄せた。
花梨が頬を染めたのにも気付かずに、前を向いて歩き出す。
誰にも譲れない意志が自分の中に湧き上がるのをかみ締めながら、泉水はまっすぐに門を目指した。
・・・花梨さんをお守りするのは、この私です。