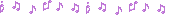
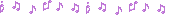
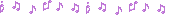
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

お父さん
演奏終了直後の楽屋は、疲労と興奮と達成感に満ちた演奏者達の熱気で溢れていた。
「やあ、泉水君。」
「ご無沙汰しております。」
「お久しぶりね。」
「素晴らしい演奏でした。」
花梨の手を引いた泉水が通りかかると、楽器の手入れをする楽団員達が口々に声をかける。
それに一言ずつ丁寧な返事と会釈を返しながら、泉水は最奥へと向かっていた。
花梨は黙って手を引かれ、泉水に合わせて会釈をしながら、不安顔でブラウスの襟元を正す。
泉水に誘われコンサートに来たは良いが、まさか楽屋に連れて行かれるとは思っていなかったのだ。
泉水と旧知であることが容易に伺える団員達が、興味深そうに、または面白そうに花梨を見る。
・・・子供っぽいって、思われてるのかな・・・
南天音大のコンサートの時に泉水が褒めてくれた花梨なりのお洒落。
だが、先ほどまで素晴らしい演奏を聴かせてくれた大人達を前にすると、彼らの前に立つには相応しくない格好のような気になる。
それほどに、彼らは演奏家であることに自信と誇りを持っているように見えた。
中でも。
「おっ、来たかぁ。」
楽屋の最奥で大きく脚を開いて長椅子に腰を下ろし、空になったペットボトルを弄んでいた男が顔を上げる。
外した蝶ネクタイを首にぶら下げたままだらしなく寛いでいる割に、団員全ての自信と誇りを束ねるような圧倒的な雰囲気を持つ初老の男。
あまりクラシック界には詳しくない花梨でも名前ぐらいは聞いたことがあるその指揮者の前で、泉水は歩みを止めた。
「毎年ご招待頂き、ありがとうございます。今年は母の都合が付かず、失礼させて頂きました。」
深々と頭を下げる。
花梨も慌てて頭を下げながら、やけに落ち着いた泉水の態度に驚いていた。
気圧されるような雰囲気に負けず、泉水はspace-timeのメンバーに接する時と同じようにこの著名な指揮者と接している。
芸能人だからといって変に媚びたり恐縮したりして接するのは逆に失礼なのだと、花梨は泉水の態度を見て初めて知る。
それをごく自然に体得している泉水はきっと、幼い頃から両親に連れられ著名人と接触してきたのだろう。
「あー、お礼なら後で団長にでも言っといて。」
ともすると冷たく感じるような声で言って、指揮者は汗に濡れた白髪交じりの髪をかき上げた。
それから、初めて気付いたというように花梨を見据えて、急にニヤリと笑う。
「・・・なーるほど、やっぱりそうか。」
どういう意味か分からないが、挨拶もなしに失礼な態度だ。
だが、花梨はどうしても、この指揮者を嫌だと思えない。
「あの・・・高倉花梨さんです。」
緊張した様子で言う泉水の言葉を、ん、と聞き流して、指揮者はいきなりペットボトルを花梨の鼻先に突き付けた。
それはまるで指揮棒でソロを促すような動き。
けれど、きっと彼はもう細長い物を指揮棒のようにしか扱えないのだろうと思わせる、必然的な動き。
「どうだった?」
笑みを浮かべたまま、視線だけは獲物を狙う獣のように、花梨を刺す。
「え・・・」
「今日の演奏。まさか寝てたわけじゃないでしょ?」
わざわざ気に障るような言い方をして、指揮者は意地の悪い笑みを見せた。
必要のないケンカを売られていることに首を傾げながら、花梨は口を開く。
「えっと・・・私、今日初めて第九を最初から最後まで聞いたんです。」
「ふ〜ん。」
「第九ってあの合唱だけだと思ってたから、こんなに長いって知らなくて、驚きました。」
「そう。」
頷きながら、指揮者は花梨に突き付けていたペットボトルを下ろした。
その頷きに混じった笑みからはもう、意地悪さは消えている。
「でも、初めて聴いた私から見ても、この楽団の皆さんはすごく自信を持っている感じがして・・・第九って、たくさんのオーケストラが何度も演奏して、テレビでも流れるくらい有名で・・・私だったら上手な人と比べられるのが怖くなっちゃうような曲を、自信を持って演奏できるって良いな、と思いました。」
「うん・・・で、合唱はどう思った?」
「あ、それは私もテレビとかで聴いたことがあるんで違いが分かりました。宴会みたいでした。」
「宴会?!」
余裕の笑みで話を聞いていた指揮者が目を丸くする。
「あ・・・すみません。」
「いや、どういう意味か、聞かせて欲しいな。」
指揮者が興味深そうに身を乗り出して、急に不安になった花梨は泉水を見上げた。
泉水は落ち着いた様子で微笑んでいて、黙ったまま続きを促すように頷く。
「えっ・・・と・・・お酒を飲んで楽しい気分になった人がカラオケで大合唱するみたいに良い雰囲気で・・・」
「正解。」
いきなり花梨の言葉を遮って、指揮者は再びペットボトルを素早い動作で花梨に突き付けた。
先ほどとは一変して楽しそうなニヤケ顔になった指揮者は、花梨にペットボトルを突き付けたまま泉水を見やる。
「正直な良い子だね。耳もいい。感覚も面白い。」
泉水はホッとしたように息を吐いて、大きく頷いた。
「はい。花梨さんはとても純粋で、素晴らしい音楽感覚をお持ちの方です。また、素直な性格をそのまま表すような透き通る歌声もお持ちです。」
指揮者はアッハハと心底楽しそうに笑ってペットボトルで自らの頭をコンコンと叩きながら言う。
「ベタ惚れだ。」
それから指揮者はペットボトルを一定のリズムで左の掌に小さく打ち付け始めた。
空になったボトルが軽い音を立ててテンポを刻む。
それは花梨には、先ほどまで聴いていた第4楽章のテンポに聞こえた。
アレグロ。
楽しげに速く。
きっと彼の頭の中にはあの楽しそうな歓喜の合唱が響いているのだろうと思わせる表情で、指揮者はやっと花梨を人と認めたように話し始めた。
「この前ね、泉水君から手紙が来たんだ。3年次から創作コースに進むことにしたって書いてあったから驚いたよ。俺はどっちかっていうと泉水君には父親のあとを継いで指揮者になって欲しかったんだが・・・」
言いながら指揮者が泉水に優しい視線を送る。
「いいえ、私には大勢の演奏者を導くようなことなど出来ません。」
慌てて首を振る泉水の反応も彼の予想通りだったらしく、指揮者は穏やかな顔のまま再び花梨を向いて続ける。
「・・・この調子だろ?・・・ま、趣味の域を超えられないフルートよりはまだ創作の道の方が泉水君には合ってると俺も思うがね。どちらにしても、見かけによらず頑固者の彼を何が変えたのか、俺はと〜っても興味があったんだよ。もしかしたらとは思ってたんだが、やっぱり親子だなあ〜。」
独りで悦に入ってクスクスと笑う指揮者の言う意味が分からず、花梨は泉水を見上げる。
泉水もその話は初めて聞いたようで、戸惑った顔を花梨に返した。
ひとしきり笑うと、指揮者は、はあ、と満足そうな息を吐きながら壁に寄りかかり、泉水を眩しそうに見上げて語り始めた。
「君の性格はお父さん譲りだ。才能があるにも関わらず頑なにそれを認めようとしない。君のお父さんも全くもって勿体ない奴だった。駆け出しの指揮者は常任として雇われるまで色々な楽団の胸を借りて修行しなければならない。だが君のお父さんは指揮者として未熟だからと言って、団員の演奏を変えようとしなかったんだ。そんな指揮者が評価されるわけがない。常任に仕込まれた団員の癖を変えずにコンサートを終えるわけだから、代役としては完璧だったがね。」
指揮者は言葉を切って、今度は花梨の方を向いて口を開いた。
「彼を変えたのが恵ちゃんなんだ。泉水君の、お母さんだよ。」
息を飲んだ花梨の反応に小さく笑顔を返して、指揮者は再び泉水の方を向く。
「ミカドの頑固ジジイが・・・ああ、君にとっては良いお爺ちゃんだったかも知れないが・・・ずいぶんうるさかったみたいだよ。指揮者なんて収入の安定しない商売の男に娘はやれないってね。まあ分からなくもない。楽器屋なんてやってれば成功しない音楽家がどんな生活をしているか嫌というほど見せられるだろうしな。それで君のお父さんは考えた。恵ちゃんと胸を張って結婚できるように、頑固ジジイが認めるような収入の安定した指揮者になれば良いってね。それからは早かったよ。人が変わったように団員の演奏に口を出すようになった。もともと才能のある奴だったから、この楽団の常任になるまで1年もかからなかったと思う。」
それから目を閉じて指揮者は小さく、勿体ねえよなあホント、と呟いた。
それが泉水の父が急逝したことに対しての言葉なのは、花梨にもすぐに分かった。
しばらく黙祷を捧げるように目を閉じたまま黙っていた指揮者だったが、急に目を開くと花梨に向かって自嘲的に笑う。
「男ってのはね、独りじゃな〜んにもできないんだ。女を守れるような男に成長させるのは、結局は女でね。いつの時代も男は女にオトコにしてもらうんだよ。ココロもカラダもさ・・・そうだろ、泉水君?」
悪戯っぽく指揮者が泉水に話を振ると、泉水は、かあっと赤くなって消え入るような声で言った。
「・・・その・・・か・・・カラダの方は・・・まだなので・・・分かり兼ねます・・・」
弾かれたように指揮者が爆笑して、目尻に浮かぶ涙を拭いながら言う。
「バカ正直な申告ありがとう。オクテなところも父親そっくりだ。」
それからしばらく、指揮者はヒーヒーと泣き声に似た声を上げながら、止まらない笑い涙を何度も拭っていた。
『父と会って頂けませんか。』
そう言って泉水が花梨を連れて来たのは、平安市を見下ろす山の中腹にあるまだ新しい霊園だった。
美しく手入れされた花壇や噴水を通り抜けてガーデンアーチをくぐると、真新しい墓が整然と並んでいる。
そこは墓地と言うより、庭園と言う方が相応しい場所だった。
年の瀬が近い夕方、広い霊園には誰も居ない。
指揮者の話を聞いてから黙りがちだった泉水は、水場で桶に水を汲んでから、やっと口を開いた。
「私の父は、第九のコンサートから帰る途中に事故で亡くなりました。毎年命日に近い休日には母と墓参りをするのですが、こうして第九を聴きに行った後には、なんとなく父に会いたくなるのです・・・」
泉水がコンサートに招待される理由や指揮者の思い、全てをやっと理解して、花梨は言葉を失う。
あの楽団はきっと、第九を毎年恒例として演奏しているのだろう。
もしかしたら、泉水の父が常任指揮者をしていた頃からの恒例なのかも知れない。
だから、泉水や恵を招待して、泉水の父と旧知の指揮者を招いて。
事情を知る者には、とても深い意味のある、歓喜の歌。
「・・・今日は特に、あんな話を聞いた後で・・・勝手なお願いで申し訳ないとは思ったのですが、どうしても父に花梨さんを紹介したくなったのです。」
許しを請うように見つめてくる泉水に、花梨は黙ったまま、静かに深く頷いた。
かける言葉が見つからない。
ただ、泉水に寄り添うことぐらいしか、今の花梨にはできない。
そっと泉水の腕に手をかけると、泉水は柔らかく微笑んで、腕を組みやすいよう軽く肘を曲げた。
優しく腕を組んで、ゆっくりと歩く。
庭園風に赤いレンガが敷かれた道は、バージンロードのようで。
源家之墓と書かれた墓の前で歩みを止めても、二人は腕を離す気になれなかった。
つい昨日か一昨日に来たばかりらしく、墓に供えられた花はまだ美しい姿を留めている。
桶を傍らに置いて、泉水が口を開いた。
「お父さん、花梨さんです・・・私に編曲の道を指し示し、お父さんの血に気付かせてくださった方です・・・私もお父さんのように、この方のために強くなります。編曲家として成功し、花梨さんと堂々と結婚できるような・・・立派な男になります。」
あまりにストレートな誓いを傍らで聞いて、花梨が頬を染める。
家族の思いを示すように丁寧に整えられた墓は、何の言葉も返さないけれど。
静けさに促されて、花梨も口を開く。
「あの・・・初めまして、高倉花梨です。私はただ、泉水さんを尊敬してるだけで・・・それを伝えただけなんです。でも、それで泉水さんが自分の本当にやりたいことを見つけられたなら、それを泉水さんのお父さんが喜んでくれるなら・・・すごく嬉しいです。だから、泉水さんが私のために強くなるって言うなら、私も、もっといっぱい泉水さんを尊敬する気持ちを伝えるようにします。」
「ありがとうございます・・・」
低い声と共に、ふわり、と引き寄せられて、花梨は優しい温もりに包まれた。
見晴らしの良い高台に吹き付ける冬の風が遮られ、とても温かい。
抱き締めると言うには優しすぎる力加減で、泉水は花梨を包んでいた。
そっと髪を撫でられる感触。
花梨がうっとりと目を閉じる。
あまり男を感じさせない泉水の優しい所作は、花梨に照れや恥ずかしさを忘れさせる。
ずっとこうしていたい、と思うような、長く柔らかい抱擁。
ふと、泉水が身じろぐ気配がした。
「・・・あの・・・」
頭の上から降ってきた声に顔を上げようとすると、急に強い力で頭を泉水の胸に押さえ付けられた。
「す、すみません、顔を見ないで頂けると有難いのですが・・・その・・・」
押さえ付けられた胸から、喉を通さない泉水の声が頭に直接響いて、なんだかドキドキしてしまう。
そのまま泉水は花梨の頭を押さえ付けて、しばらく、えー、その、あの、と繰り返してから、小さな声で言った。
「・・・こんな墓前で申し訳ないのですが・・・その・・・キスを・・・すみません・・・不躾なお願いで恐縮なのですけど・・・花梨さんさえ宜しければ・・・」
かあっ、と花梨が赤くなる。
何も言えないまま、こくこくと小さく何度も頷くと、頭を押さえ付けていた泉水の手が外れた。
上目遣いで見上げれば、あらぬ方向を見ている泉水の顔が驚くほど真っ赤で。
余計に恥ずかしくなった花梨が、ぎゅっと目を閉じる。
心臓をバクバクさせながらしばらく待っていると、ふいに顔の前の冷気が遮られ、唇に柔らかいものが触れた。
だが、一瞬だけで、その温もりはすぐに離れてしまい、すぐに強い力で抱き締められる。
それは、泉水を男と意識させるに十分な激しさで。
なのに、花梨は先ほどの優しい抱擁よりもその心地良さに酔いしれてしまう。
「・・・誓いの・・・キスですね・・・」
泉水に身体を預けてうっとりと言うと、泉水がはっと息を飲む気配がした。
「確かに、花梨さんの言う通りですね・・・そう思えば、墓前でこのような行為をすることに、あまり罪悪感を覚えずに済みます。」
花梨がクスリと笑う。
ドキドキしていてそれどころではなかったが、言われてみれば泉水の父にジッと見られているような気持ちになる。
「花梨さん・・・」
呼ばれて顔を上げると、泉水の真摯な表情があった。
それが、ゆっくりと近づく。
二度目のキスだと花梨が悟って瞳を閉じると同時に、泉水の唇が降りてきた。
唇を離さないまま、泉水は花梨の身体を強く抱き締め直す。
それから、小さく花梨の唇を啄んだ。
ゾク、と花梨の背筋に甘い電流が走る。
そっと唇が離れて、瞳を開けば、泉水の真摯な表情は少し上気しているように見えた。
花梨を強く抱き締めたまま、泉水が熱に浮かされたように低く囁く。
「・・・どうか・・・私を立派な男にして下さい・・・」
先ほどの指揮者の言葉が脳裏をかすめて、花梨の心臓が跳ねる。
真っ赤になって絶句してしまった花梨の様子に気付いた泉水は、慌てて花梨から離れた。
「あ・・・そ、そのような意味ではなく、もちろん、編曲家としての意味で・・・すみません・・・!」
捲し立てながら誤魔化すように桶から柄杓を取り出し、墓に水をかけ始める。
しかし、再び慌てた様子で泉水は花梨を振り向いた。
「あ・・・!ですが、あの、誤解しないで頂きたいのは、か、カラダの方ももちろん花梨さんにお願いしたく・・・」
そこまで言って、泉水は絶句する花梨の視線に耐えられないというように再び墓の方を向き、水をかけながら続ける。
「・・・いえ、その、今すぐという訳ではなく・・・あ、も、もちろん私の方は今すぐでも構わないのですが・・・花梨さんのお心が決まり次第と、そう肝に銘じておりますので・・・ああっ、お父さん、このような時はどう言えば愛する方を不快にせずに済むのでしょう・・・?!」
柄杓を持ったまま頭を抱える泉水の様子に、花梨は小さく笑んで、後ろから泉水に抱き付いた。
泉水がビシッと音を立てるようにして固まる。
「・・・ちゃんと分かりましたから大丈夫です。いつか、心が決まったら言います。」
固まった背中に頬を付けて言うと、泉水はホッとしたように息を吐いて、小さな声で言った。
「・・・お、お願いします・・・」