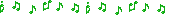
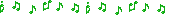
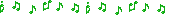
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

I love you
土曜の昼下がり、駅前のカフェバーは待ち合わせや遅いお昼を摂る客でほとんど満席になっていた。
「繁盛するのは良いことだが・・・君達を眺めている暇がないのは残念だよ。」
翡翠がコーヒー豆を補充しながら周りのアルバイト一人ひとりに流し目を送る。
美人ぞろいのウエイトレス達は、忙しく手を動かしながらもそれぞれが翡翠の目に留まるべく自己最高のほほ笑みを返したが、花梨は頬を染めて目をそらしてしまった。
そんな花梨に翡翠が声をかけようとすると、入り口から客が入ってきた。
花梨は天の助けと慌てて出て行く。
「いらっしゃいませ!ようこそオレンジブロッサム・・・あ、幸鷹さん!」
アルトサックスのハードケースとクリアーケースを持ち、きょろきょろしながら店内に入ってきた幸鷹だったが、フェミニンなエプロンドレスといういでたちをした花梨に出迎えられて、うろたえたように右手を握って口許に当てた。
「おや、珍しいお客さんだね。」
花梨の声を聞いて、翡翠も出てきた。
花梨はそれを見ると、空いた席を探しに店の奥へ引っ込んだ。
「君も、花梨の可愛い制服姿を眺めに来たのかい?」
「あ、あなたという人は・・・私はそんな邪な思いは・・・。」
言いながらも、幸鷹は赤くなって口ごもる。
「ない、とは言えないようだね。」
「・・・今日は、花梨さんに英語の発音を教える約束をしているのです。」
「ほう。」
翡翠の目が面白そうに見開かれた。
幸鷹がそれを見て声を低くする。
「邪魔をしないでくださいよ。」
「私がそんな無粋なことをすると思うかい?」
翡翠はにやりと笑うと手をひらひらと振ってバックヤードへ戻っていった。
幸鷹が大きくため息をつく。
しばらくすると、花梨がトレイに汚れた皿やカップを載せて戻ってきた。
「お待たせしました。」
急いで片付けて戻ってきてくれたのだろう、上気した顔で見上げられて、幸鷹は言葉に詰まった。
花梨はそんな幸鷹に気付かず、急いで空いた席に案内する。
幸鷹に働いている姿を見られて、妙に照れくさくなってしまったのだ。
後ろについて歩く幸鷹が気遣うように口を開いた。
「すみません忙しい時に・・・予定より早く調べものが終わってしまったので。」
終わらせたというのが正直なところだが、そうは言わない。
花梨も、慌てている自分に気付いて自嘲的な笑顔になった。
「いいえ。ちょっとびっくりしちゃっただけですから。」
「コーヒーを飲んで待っています。」
「はい。いま、メニューを持ってきます。」
花梨は、幸鷹が座るのを見届けて席を離れた。
すぐに怪訝な顔でメニューを持ってくる。
「あの・・・約束の3時まであと1時間もありますけど、いいんですか?」
「はい。読みたい本がありますので。」
幸鷹がにっこりと笑ってクリアーケースを見せる。
表紙に英語が印刷された分厚い本が透けて見えた。
花梨はそれを見て、尊敬の気持ちが現れると共に、じわり、と胸の奥に暖かいものが広がるのを感じる。
「分かりました。じゃあ、ゆっくりしていてくださいね。」
「本当にすみません、遅くなっちゃって。」
「いいえ。」
花梨が私服に着替えて幸鷹の向かいに座ったのは4時過ぎだった。
通りかかったウエイトレスに端末を借りると、自分で追加注文を入力する。
「幸鷹さんは、コーヒーのお替りいかがですか?お詫びにおごりますよ。」
「じゃあ、お言葉に甘えることにします。」
嬉しそうに頷いて幸鷹の分も入力し、ウエイトレスに小さく詫びながら端末を返すと、花梨はどっと椅子の背にもたれかかった。
「はあ。疲れたあ。」
「お疲れ様でした。」
幸鷹が、読んでいた本にメモ用紙を挟んで閉じながら微笑む。
「今日は、なぜかする事が多くて。」
「ええ、ずっと忙しそうでしたね。」
花梨は、まるでずっと見ていたかのような幸鷹の言葉にギクリとしながら、仕事中の自分を思い出す。
どうしても幸鷹にばかり目が行ってしまって困っていたのだ。
右手でボールペンをくるくると回しながら真剣に本へと視線を落とし、時々手元の用紙へ何かをメモする幸鷹の横顔は、優しい笑顔ばかり目にしていた花梨が初めて見る男性的な一面をもっていた。
花梨が幸鷹を見てばかりいれば、当然目が合う。
その度に、花梨は恥ずかしくなってバックヤードに引っ込んでしまっていた。
幸鷹は、花梨が可愛い制服で働く姿を多く眺められたのでそれほど気にしてはいなかったが、1時間の残業は長すぎではないかとも思い、ふと、あることに気付いて、花梨に聞いてみることにした。
「もしかして、翡翠さんに頼まれたのでは?」
確かに、花梨がバックヤードへ引っ込むと、待っていたかのように翡翠が様々な用事を言いつけてきた。
「うーん、言われてみれば、そうかな?」
「やっぱり。」
幸鷹はがっくりと肩を落とした。
「なんで分かったんですか?」
「長い付き合いですから。」
あきらめたように遠い目をする幸鷹。
花梨はその言葉を良い意味に捉えたらしく、しきりに感心した。
「長い付き合いかあ。いい言葉ですね。翡翠さんはいい人ですもんね。」
「ありがとう、姫君。」
頭上から声がした。
驚いた二人が見上げると、翡翠がトレイを持ってにこにこと微笑んでいた。
幸鷹のカップを新しいものに取り替え、花梨が注文したカプチーノと、注文していないレアチーズケーキを優雅な動作で置く。
「姫君の大好物、残業のお詫びだよ。」
「あ、ありがとうございます!」
「それと、カプチーノは砂糖半分入れてから泡立てておいたから。姫君はいつも砂糖半分だろう?」
「はい!すみません!」
感激して頷く花梨に、翡翠は満足そうに微笑むと、幸鷹をちらりと一瞥して去っていった。
「やっぱり翡翠さんって、いい人だなあ。たまにセクハラだけど。」
花梨がいそいそとケーキにフォークを入れながら呟く。
それを聞いて、憮然としていた幸鷹の目が据わった。
ふ、と笑顔を作る。
「そうだ・・・今日はあまり時間がなくなってしまいましたから、明日、お時間があれば、私の部屋へ来ませんか?」
「えっ?でも、お家の方に申し訳ないですよ。」
ケーキを頬張りながら、花梨が上目遣いで幸鷹を見る。
幸鷹は、無邪気なその瞳に罪悪感を覚えたが、翡翠を出し抜きたいという気持ちの方が勝ってしまった。
「私の部屋は、勉強に集中できるよう離れになっているので、家族に迷惑はかかりませんよ。」
「そうなんですか?でも、幸鷹さんにも悪いですし。」
「いいえ。それに、よく考えてみたら、発音の練習はこういう場所や図書館ではやりにくいですよね。」
「確かにそうですね・・・。」
花梨は考え込みながら両手でカップを持ち上げると、カプチーノを一口飲んだ。
花梨の小さな唇をきめ細かな泡が縁取るのを見て、幸鷹の中に拭き取ってあげたいという甘い気持ちが広がる。
そんな幸鷹の心のうちには気付かず、ペーパータオルで口を拭きながら花梨が頷いた。
「じゃあ、お邪魔することにします。」
優しい笑みをたたえて幸鷹も頷く。
「では、発音は明日にして、今日は練習に行くまでの間、歌詞を訳しましょう。歌詞の意味を知った方が、貴女の歌は数倍良くなるはずです。」
「はい!」
花梨は自分の歌の性質をよく理解してくれている幸鷹の言葉が嬉しくて、元気よく返事をすると、カバンから歌詞がプリントされた紙を出した。
「trueには真実、の他に誠実という意味もありますから、誠実でいて下さい、ということでしょうね。あと、ここは前と同じで、最後は言うまでもないですね。」
「愛してる、ですよね。」
くすっと、花梨がはにかんで笑うと続ける。
「なんだか、アイラブユーだと大丈夫なのに、アイシテルだと照れくさいです。」
花梨の表情に目を奪われながらも、幸鷹は真面目に答えた。
「英語は日常使う言葉でない分、現実味が薄れるのかもしれませんね。」
「幸鷹さんは、どう感じますか?」
「私ですか?・・・う〜ん、I love you、愛してる・・・」
眼鏡の位置を直しながらぶつぶつと両方を呟いて比べる様子に、花梨は、幸鷹が両方とも日常使う言葉と感じている事を現実的に感じ、再び尊敬の気持ちが湧き上がった。
「I love you、愛してる・・・」
幸鷹は、花梨を目の前にしてそう呟いていること自体が照れくさくなって、ちらりと花梨を見た。
キラキラとした尊敬の眼差しにぶつかって面食らう。
そして、気付いた。
「そうか。」
「どっちですか?」
「今は、アイシテルの方が照れくさいです。」
「今は?」
「はい。英語を話す恋人が居たときは、アイラブユーの方が照れくさかったかもしれません。」
「え?恋人?」
花梨はすうっと胸の奥が冷たくなるのを感じた。
そんなことは考えもしなかったが、頭が良くて優しげな幸鷹がモテないはずがない、と、今更気付く。
「はい。やはり、愛の言葉は相手が居ないと成り立たないものですから、自然と相手の言語に合わせてしまいます。」
「そうですか・・・」
上の空で答えながら、花梨は胸の奥がますます冷えて、痛みさえも感じ始めたのに気付いていた。
ふと現在の幸鷹に対しても、そんな思いが至る。
「じゃあ、今は日本人の恋人が居るって事ですか?」
「いえ、今は居ません。花梨さんを目の前にしているので、アイシテルの方が照れくさいのですよ。」
冷たくなっていた花梨の胸の奥にボッと火がついたような感覚がした。
心臓が跳ねたせいだ。
「え、えっと・・・」
何かを期待している自分が居る。
花梨はそう考えると、顔が火照るのを止められなくなってしまった。
幸鷹は、真っ赤になった花梨を見て、自分の言った台詞が突如恥ずかしくなり、冷めてしまったコーヒーを飲み干す。
「では、次の曲を訳しましょう。」
「は、はい。」
花梨は火照った顔で、慌ててプリントをめくった。