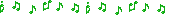
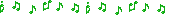
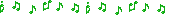
メニューへはブラウザの“戻る”ボタンでお戻り下さい。

your lips
「すごいご家族ですね。幸鷹さんの勉強のためだけに離れを作るなんて。」
花梨は、駅まで迎えに来た幸鷹と一緒に幸鷹の家へ向かっていた。
「15歳で留学から帰って来た私を、どう扱っていいか分からなかったというのが、本音だと思いますよ。おかげでサックスの練習はし放題ですが。」
少し寂しそうに笑う幸鷹を見て、花梨は聞き役に徹することにした。
自分から辛い話を切り出す時というのは、聞いて欲しい時だ。
「15歳で?じゃあ、他にもいろいろと辛い事があったんじゃないですか?」
幸鷹は促されるまま、帰国子女としての苦労や、天才少年と騒ぎ立てられた経験を話した。
相槌を打ちながら話を聞く花梨の真摯な瞳を見ていると、不思議と幸鷹はもっと自分のことを聞いて欲しい、気持ちを共有して欲しい、と思う。
花梨を案内しながら家に着くまで話し続けた幸鷹は、門を開けながらはっと気付いて後ろの花梨を振り向いた。
「すみません、花梨さん。私のことばかり話して。」
「いいえ。幸鷹さんのこと、いろいろ知ることができて良かったです。」
「・・・ありがとうございます。」
後悔の念が、やわらかく溶かされていく。
幸鷹は、庭を横切ってプレハブでできた離れに向かいながら、なぜこんなに自分のことばかりを話してしまったのかを分析していた。
そして、花梨が自然に話を促してくれていたことに気付き、花梨に対する気持ちを新たにする。
「そういえば、今まで、誰も私の立場を辛かっただろう、なんていう人は居ませんでした。」
「そうだったんですか?」
「悩みを告白しても、謙遜だとか、羨ましい悩みだとか言われることばかりで。」
部屋の鍵を開けながら、幸鷹が言うと、意外に花梨は冷たく言い放った。
「ああ、そうかもしれませんね。社交辞令なら、そう言うしかないですよ。」
その言葉は花梨が本音で幸鷹に接しているという証だった。
「社交辞令ですか。なるほど。」
幸鷹は感嘆の声で言いながら、ドアを開けた。
開いたドアの前に立つと、左手を広げ花梨を中へ促す。
「どうぞ。」
そんなちょっとした仕草が外国映画に出てくる恋人役のように見えてしまう幸鷹に、花梨は思わず見とれてしまった。
はっと我に返る。
「おっ、おじゃまします!」
幸鷹の横を花梨がそそくさと通り過ぎて靴を脱ぐ。
ドアを閉めた幸鷹が花梨の背中に声をかけた。
「そこの座布団に座ってください。」
花梨は、床においてある小さなテーブルの前の座布団に腰を下ろした。
幸鷹がドアの横に設置された小さなシンクでヤカンに水を入れながら、花梨に優しく言葉をかける。
「飲み物は、紅茶とコーヒー、どちらがいいですか?」
「じゃあ、紅茶にします。ありがとうございます。」
そう答えて、花梨は周りを見回す。
広いデスクの上には辞書や書類が積み上げられ、隣のパソコンデスクにも英語や日本語の付箋がたくさん貼ってあった。
幸鷹の日常を表すそれらを見て、花梨の心には尊敬の念が湧き上がっていた。
真面目な顔になり、カバンから歌詞の印刷されたプリントを出すと、テーブルの上に広げ、ブツブツと歌詞を呟き始めた。
幸鷹が、紅茶の入ったマグカップをテーブルに置いて花梨の向かいに座ると、歌詞を呟いていた花梨が顔を上げた。
「よろしくお願いします!」
勢い込んで頭を下げる花梨を見て、幸鷹は苦笑した。
「そんなに固くならないでください。まずは気楽に、最初から読んでみてください。」
「はい・・・Fly・・・」
花梨がたどたどしく最後まで読み終える。
「そうですね。歌になってしまえば、そんなに気にならないと思いますが、それっぽく聴かせるために、今日はティーエイチの発音とヴイの発音だけ完璧にしましょう。昨日お話したアイラブユーも、アイラヴユーにした方が雰囲気が出ますからね。」
「はい!」
花梨が嬉しそうに返事をする。自分の歌が良くなるためなら何でも頑張れる、という表情に、幸鷹は感心しながら頷いた。
「まずはティーエイチの発音です。よく見てくださいね。」
幸鷹が自分の唇を指差す。
口を開けて歯の間に舌を挟むようにしてから息を漏らす。
花梨にしげしげと見つめられて落ち着かなかったが、真面目な幸鷹は花梨が上達するため、と耐えた。
「では、やってみてください。」
ふむ、と神妙に頷いて、花梨が真似をする。
今度は幸鷹が花梨の唇を見つめる番だ。
小さな唇からのぞく舌が一生懸命うごめく様子に、幸鷹はよからぬことを連想してしまい、頬を染めた。
ごまかすように咳払いをする。
「あの、舌をもうちょっと出してください。」
「え?こうですか?」
「・・・っ、それでは出しすぎです。」
花梨はなかなか上手にできず、幸鷹を刺激するような舌の動きばかり繰り返していた。
「ちょっと待ってください。」
耐えられずに幸鷹はそこを離れシンクへ行く。
意を決してコップで水を一気に飲んでから、石鹸で手を洗うと戻ってきた。
「失礼します。」
花梨の隣へ座ると、微かにコロンの香りがした。
幸鷹は、その香りに誘われるように左手を花梨の頬にあて、右手を顎に添えて花梨の唇を開く。
「あ、あの・・・」
花梨が赤くなって裏返った声を上げた。
目の前に幸鷹の整った顔が近づく。
眼鏡の奥から真剣な瞳が花梨を見つめていた。
顎に添えられていた右手が離れ、人差し指が花梨の前歯の裏をなぞった。
「歯のこの辺りに、舌を付けてください。」
「ふぁい・・・」
恥ずかしさのあまり、花梨は涙目で言われたとおりにする。
「もう少し、この辺です。」
今度は幸鷹の指が舌をなぞる。
「ん・・・っ!」
突然慣れない味がしたため、驚いた花梨は眉根を寄せて口を閉じてしまった。
一瞬、幸鷹の人差し指をしゃぶるような状態になってから、花梨の唇が離れる。
「ご、ごめんなさい!驚いちゃって・・・」
幸鷹は、そのままの姿勢で固まっていた。
「あの・・・幸鷹さん?」
「はっ、はい、す、すみません。私は何てひどいことを。」
想像が暴走してしまった罪悪感から、真っ赤な顔でぺこぺこと謝る幸鷹を見て、花梨は、幸鷹も恥ずかしいのを我慢して一生懸命教えようとしてくれたのだろうと理解した。
「いえ、ありがとうございます。ひどいことなんかじゃないですよ。」
「あ・・・それは・・・す、すみません。」
幸鷹はうなだれた。
想像上の花梨に対しての言葉だとは口が裂けても言えない。
「本当に、気にしないでください。なんとなく分かったかも。こうですよね?」
花梨は幸鷹の一生懸命に応えようと、触れられた歯と舌を付けて、息を漏らす。
「あ、はい。そうです。」
律儀な幸鷹はそそられてしまうのを分かっていながらも至近距離で花梨の唇を見守る。
触れたい気持ちが膨らんでいく。
「で、では、続けてヴイの発音もやってしまいましょう。」
「はい。」
「こうです。」
下唇を軽く噛んで息を漏らす。
「こうですか?」
ふっくらとした花梨の下唇が、ぷるんと震えた。
花梨の発音はだいたい合っていたが、幸鷹は触れたいという衝動を抑えられなくなっていた。
「そうですね。もう一度、いいですか?」
返事も待たずに左手を花梨の頬に添える。
「は、はい。」
花梨も恥ずかしい気持ちを我慢してぎゅっと目を閉じると、唇を開いた。
「このあたりです。」
幸鷹の指が花梨の下唇をなぞった。
人差し指からふわふわとした感触が伝わる。
花梨の唇から顔全体に目を移すと、頬を染めて震えながら目を閉じている表情は、さながらキスを待っている初心な少女のようだった。
思わず、幸鷹は左手を花梨の頬に添えたまま、黙ってそれを見つめる。
黙ってしまった幸鷹に違和感を覚えた花梨が、恐る恐る目を開けた。
幸鷹がはっと我に返って左手を下ろす。
「えっと・・・これでいいですか?」
花梨は戸惑いながらも正しく発音して見せる。
「はい。そうです・・・」
頷きながら、幸鷹も戸惑っていた。
自分は花梨の気持ちも確認しないまま彼女に何をしようとしていたのか、と自問する。
幸鷹は微かにため息をついて花梨から離れ、もと居た場所へ座ると、笑顔を作った。
「では、もう一度、この歌詞を通して読んでみてください。」
「はい。」
花梨は、幸鷹が、物理的な距離と同じ分だけ、心の距離をとってしまったような気がした。
理由は分からなかったが、それを寂しく感じ、幸鷹に感謝の気持ちだけでも伝えようと思う。
プリントを見て頷くと、腹式呼吸で息を吸った。
幸鷹は、花梨が歌詞を読むのではなく、歌いだしたのを聞いて少し驚いた。
心を込めて歌う花梨の気持ちが伝わって、暖かい思いが幸鷹の胸を満たす。
「あなたは・・・本当に素晴らしい女性ですよ。」
歌い終わった花梨に、幸鷹は心からの言葉を送った。
「私の気持ち、伝わりましたか?」
「はい。とっても。この最後の歌詞だと受け取ってもよろしいのですよね?」
「え?」
幸鷹が花梨のプリントに書いてある最後の歌詞を指で指した。
そこには花梨の字で『愛してる』とメモしてあった。
「私にはそう伝わってきました。」
「ふえっ?・・・あれ?・・・えーと・・・」
そこまでは思っていなかった花梨だが、否定するのも違う気がして、言葉を探す。
「冗談ですよ。」
今はね、という言葉を飲み込んで、幸鷹は花梨のプリントをめくった。
「では、先ほどの二つの発音に気をつけて、この歌も聴かせて下さい。」
「あ、はい。」
ほっとすると同時に現れた残念な気持ちを振り払って、花梨は歌い始めた。