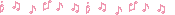
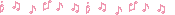
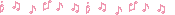
プロローグ 1
音楽教室の掲示板には、伝言メモがいくつか貼ってある。
オフィシャルキャラクターの挿絵があるそれは、たいてい子供の字で『リリーは子供を3匹うまれました。もらてください。』
『メロトノムあげます』などと書いてある。
子供好きな花梨は、この掲示板で子供たちの字や、メッセージを見るのが好きだった。
「リリーは、犬なのかな?」
「ぷっ。メロトノムだって。」
誤字脱字が可愛く思わず吹き出す。
そして。
ひとつのメモに目を留める。
「ボーカル募集・・・?」
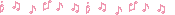
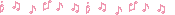
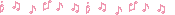
次の火曜日、花梨は部活が終わると、楽器店"in the time"へ向かった。
駅から少し歩いた細長い貸しビルの一階に小さな店舗を見つけると、意を決して中へ入る。
店内に所狭しと並べられている楽器。
その中で、首のあたりまで髪が伸びた青年が一人、不機嫌そうにギターを布で拭いていた。
「あの・・・」
ジロリと音がしたかと思う。
もちろん、その青年が花梨に目を向けた際のことだ。
「何か用か。」
花梨は青年の偉そうな物言いに少なからず驚いたが、顔に出さないよう努めて訊ねた。
「あの、space‐timeっていうバンドの方ですか?」
「いや。奴らはスタジオに居る。」
「あ、そうですか・・・。」
店員とは思えない態度に、花梨はスタジオの場所を聞いていいものかどうか迷った。
すると、青年はギターを静かにスタンドへ立てかけ、腰を上げた。
「スタジオの場所は分かるか?」
「い、いえ。」
「その様子ではそうだろうな。ついて来い。」
そう言うと、青年は店の外へ出ていってしまった。
花梨が慌てて後を追いかけると、青年は店舗のすぐ横にある狭い階段からビルの2階へ上がっていた。
微かにギターの音が聞こえてくる。
青年が一見事務所のようなドアを開けると、すぐ正面と右側に再び黒いドアが現れた。
ドアには楽器メーカーのステッカーがベタベタと貼ってある。
ギターの音は右側の黒いドアから聞こえていた。
音楽教室の防音ドアと同じようだが、てこのようなドアノブを回す青年の様子を見ると数倍重そうだ。
ドアが開くと、つんざくようなギターの音が耳に飛び込んで来て、花梨は肩をすくめた。
青年が入っていくと音が止む。
「なんだ和仁か。そこにあったでけぇアンプならPAルームにどかしたぞ。」
部屋の中から声がした。
「まだお前だけか。」
「ああ。7時前だしな。」
「お前たちに用があるそうだ。」
「へっ?」
花梨が、おずおずと部屋の中に入った。
ガランとした室内で、同年代の少年がギターを抱えて座っていた。
花梨を見て驚いたように瞳が見開かれる。
「私も今日は一人なので長時間店を空けられない。あとは任せたぞ。」
「お、おう。」
和仁と呼ばれた青年は、返事も待たずにドアの前に居た花梨をよけて出て行こうとした。
「あ、あのっ、ありがとうございました!」
花梨の言葉に驚いた様子で振り向く。
「いや。」
和仁が首を振って微笑んだ。
花梨は、別人と思える程のあどけない笑顔に驚いてしまい、ドアが完全に閉まるまで、そのままつっ立っていた。
「なんの用?」
うしろから声をかけられ、花梨ははっとした。
振り向くと、少年の怪訝そうな瞳にぶつかる。
「あの、これを見たんです。」
花梨は定期入れの中に入れてあったメモを取り出して少年に歩み寄ると、少年がそれを覗き込んだ。
「ボーカル募集?・・・ああ、なんだその事かぁ。」
「もう誰か決まってしまいましたか?」
「そんなことねぇよ。来たのは、お前が初めてだし。」
「そうですか。」
「参ったなあ。来たらどうしろとか言われてねぇんだよなあ。わりぃけど、俺もあんまり詳しく分かんなくて。そこの椅子にでも座って待っててくんねぇ?」
「はい。」
少年が申し訳なさそうにしているので、花梨はアルバイトで培った営業スマイルを返すことにした。
少年も、安心したように笑顔になる。
花梨はドアの近くに置いてあった椅子に腰を下ろした。
「俺はイサトってんだ。お前は?」
「高倉花梨です。」
「その制服、平安高だよな?」
「そうです。」
「俺も平安高。お前何年?」
「1年生です。」
「俺は2−D。知り合い居る?」
「えっと、多分、吹奏楽部の先輩が・・・。」
「おまえ吹奏楽部なの?先輩ってオンナ?」
花梨が頷く。
「オンナはあんまり親しくねぇから分かんねぇや。ごめん。」
「いえ・・・。」
花梨は首を振ったが、イサトは申し訳なさそうな顔のままだ。
気まずい沈黙が流れそうになるのをイサトが必死で遮る。
「あ、そ、そうだ。俺のギターでも、聴いててくれよ。ちょうど新しい曲の練習してたんだ。」
花梨を飽きさせないように一生懸命なイサトの優しさに気付いて、花梨の心の奥がぽっと温かくなった。
ふっと微笑む。
先ほどの営業スマイルとは別の、本当の微笑みにイサトは目を奪われた。
慌てて目をそらし足元のアンプのスイッチを押す。
電源が入ったままだったそれは、バツンと音を出して沈黙した。
「いっけねぇ、電源入れたままだった。」
わたわたと電源を入れなおすイサトの様子に、花梨は声を立てて笑った。
それを見たイサトも、頭に手をやって恥ずかしそうに、へへっと笑った。
エレキギターの音をすぐそばで聞くのが初めてだった花梨は、その音に辟易としていた。
先ほどからイサトは同じフレーズばかりを弾いている。
左手を弦の上で素早く動かし、速いメロディーを奏でようとしているのだが、左手がもつれて途中でテンポが落ちる。
花梨には十分超人的な速さに思えたが、イサトはもう少し速く弾きたいようだった。
やっと耳が慣れてきた頃、ドアが開いて、イサトとは違う制服の高校生が入ってきた。
「よう、彰紋。」
「こんばんは。イサト。わっ?」
彰紋と呼ばれた少年は、ドア付近にちょこんと座っている花梨に気付くと驚いて飛びのいた。
花梨は急に止んだギターの音に耳がキーンと鳴っていて、彰紋とイサトの会話がよく聞こえない。
とりあえず、立ち上がって礼儀正しくお辞儀をする。
「えっと・・・イサトの彼女さん・・・ですか?」
「えっ?」
彰紋が、遠慮がちに小さな声で訊ねた。
まだ耳が鳴っていてよく聞こえない花梨が聞き返す。
すぐにイサトの叫び声が聞こえてきた。
「ちっ、ちげーよ!バカなこと言うな!!」
耳まで真っ赤になって否定するイサトの様子に、花梨も、恋人に誤解されたのだと気付く。
「高倉花梨といいます。ボーカル募集と聞いて来たんです。」
「ああっ、ボーカル来てくれたんだ、うれしいなぁ。イサトの彼女なんて失礼なことを言ってごめんなさい。僕のことは彰紋って呼んでくださいね。」
「はいっ。」
心から嬉しそうな彰紋の様子に、花梨も嬉しくなって元気よく返事を返した。
「俺の彼女だと失礼ってどういうコトだよ。」
イサトがまだ頬を火照らせたままでそっぽを向いて口をとがらせている。
花梨と目を見合わせた彰紋は、肩をすくめて笑った。
「どうぞお座りください。皆が揃うまで・・・」
彰紋の言葉の途中でドアが開く。
長い髪の青年が穏やかな微笑みを浮かべて入ってきた。
花梨を見て驚きに目を見開き、戸惑った表情になる。
「あ、あの・・・」
「泉水さん、こんばんは。ボーカル募集で来て下さった高倉花梨さんですよ。」
困ったように言葉を探す青年に、彰紋が嬉しそうにまくし立て、花梨がぺこりと頭を下げた。
「そうでしたか。」
泉水はほっと息をつく。
「花梨さんですね。よろしくおねがいします。私は源泉水といいます。」
再び穏やかな笑みを浮かべて花梨に頭を下げた。
花梨はその笑顔に不思議と全てを受け入れてもらったかのような安堵を覚えて言葉を返す。
「よろしくおねがいします。」
「もうすぐ7時ですし、すぐに皆さんもいらっしゃると思います。私達は楽器の音出しをしなくてはいけませんので、もうしばらくお待ちくださいね。」
「はい。」
花梨が返事をして椅子に座るのを見届けてから、彰紋と泉水は壁際の机に荷物を置いて、楽器を取り出し始めた。
二人ともハードケースを手にしている。
イサトはまた同じフレーズの練習を始めた。
再び耳を独占するギターの音の中で、花梨は楽器を取り出す二人に注目していた。
ボーカル募集の言葉とイサトの雰囲気から、花梨は勝手にロックバンドだと思っていた。
しかし、彼らが手にするハードケースは、吹奏楽部で見慣れているタイプのものだ。
ほどなく、彰紋はトランペットを、泉水はフルートとソプラノサックスを取り出した。
花梨は混乱した。
この楽器編成で、ボーカルが必要な音楽ジャンルが思い当たらない。
花梨は高校に入って始めたばかりの吹奏楽の知識や、今まで音楽教室で学んできた知識を総動員して考え込んだ。
考え込んでいた花梨が、サザンオールスターズを思い浮かべたところで再びドアが開く。
「皆さん、こんばんは。」
眼鏡をかけた青年が入ってきた。
ドアを開けたまま再び引っ込む。
ドアの陰に居た花梨には気付かなかったようだ。
隣の部屋から「せえの」と掛け声がして、何かを運んでくる。
見ると、2台のキーボードがスタンドへ段違いに載せてあった。
眼鏡をかけた青年は花梨に気付かずどんどん奥へとキーボードを運んでいく。
もう片方を持って後から入ってきた青年は、すぐに花梨に気付いたが、話しかけるでもなく、キーボードを運ぶ歩みを止めるでもなく、ただ珍しいものを見るように顔を向けたままだった。
遠慮なく見つめられて花梨はドギマギする。
キーボードを置くと、眼鏡の青年がやっともう片方の青年の視線に気付き花梨に目を向けた。
「おや、お客様ですか?」
「ええ。ボーカル募集で来て下さった高倉花梨さんですよ。」
先ほどと同じように、彰紋が嬉しそうに口を開いた。
「伝言メモを見てくれたのだな。」
もう片方の青年が花梨の手に握られた紙片を見て微かに笑う。
「私は藤原幸鷹と申します。代表として、事務的なことやメンバーの意見の取りまとめは全て私が行っています。」
眼鏡の青年が真面目すぎる自己紹介をした。
が、優しい笑みが言葉の冷たさを補い、人当たりの良さを思わせる。
「私は泰継だ。音楽教室にメモを貼ったのは私だ。」
先ほどの微笑を引っ込めてもう片方の青年が口を開いた。
愛想という言葉とは無縁らしい。
花梨の目に、キャラクターの挿絵があるメモ用紙に無表情で文字を書き、子供ばかりのメモが並ぶ掲示板に無表情でメモを貼る彼の姿が浮かんだ。
こみ上げる笑いが抑えられない。
「何を笑う。」
「いえ、すみません。」
「俺は分かるぜ。花梨の気持ち。」
イサトがニヤニヤしながら口を挟む。
「な・・・」
何がおかしい、と泰継がイサトに問いかけようとすると、勢い良くドアが開いた。
「悪いな。少し遅れた。」
謝りながら入ってきた青年は、花梨を見て何か引っかかったような顔をする。
「あれ?お前・・・誰だっけ?」
「えっ?」
「どっかで会っただろ?」
「いえ、多分初めてお会いすると思うんですけど・・・。忘れてたらごめんなさい・・・。」
「勝真、ナンパにしては古すぎんぞ。」
イサトが勝真を軽く睨む。
「それもそうだな。」
勝真と呼ばれた青年は、イサトに向かってニヤリと笑った。
ナンパのつもりでないことぐらい、花梨にも分かる。
困ってしまった花梨に気まずい思いをさせないための芝居だ。
息の合った二人の優しさに、花梨は感謝した。
「で?」
勝真が幸鷹を見て説明を求める。
「ボーカル候補の方です。」
「あ、なーる。俺は勝真。よろしくな。」
「よろしくおねがいします。」
元気良く返事をする花梨に、勝真は気さくな笑顔を返した。
しかし、すぐに何かに気付いて幸鷹を振り返る。
「幸鷹、候補って事は他にも居るのか?」
「いえ、最初のお一人ですが・・・」
幸鷹は言いよどんだ。
眼鏡を上げると、意を決して口を開く。
「失礼を承知で申し上げると、私達のレベルに見合った歌唱力かどうか、一度聞かせていただきたいと思いまして。」
花梨が顔を強張らせた。
青年達の優しさに触れて浮かれていた心がスッと冷める。
「ええっ?」
「マジかよ?」
彰紋とイサトが驚愕した声を出し、泉水が眉をひそめて胸に手を当てた。
「俺達だってたいして上手くねぇだろ?そんなことする必要あんのかよ?」
イサトが思わず立ち上がる。
「確かに上手くはありませんが、いいかげんな気持ちでやってはいないでしょう?」
幸鷹が穏やかにイサトへ言葉を返す。
「下手なボーカルを迎えて、不満に思いながら演奏したくはない。」
泰継が歯に絹を着せぬ言い方をしたので、彰紋はぎゅっと目を閉じ、泉水は胸に当てていた手でシャツを握り締めた。
「でもよ・・・」
イサトが口ごもりながら花梨を伺う。
「そうだな。うちに入りたくなくなっちまうんじゃないか?」
勝真もそう言いながら花梨を見た。
他の皆もそれぞれの表情で花梨を振り返る。
「あ、あの、私なら、大丈夫です。皆さんがお気に召すかどうか、思う存分テストしてください。」
しどろもどろに答える花梨の様子に、勝真が苦笑し、イサトはため息をつきながら腰を下ろした。
彰紋と泉水がほっとした顔を見合わせ、泰継が静かに頷く。
「すみません。理解していただいて、ありがとうございます。」
幸鷹が申し訳なさそうに言って、微笑んだ。
「では、あとの二人が来るまで私達はしばらく個人練習をします。全員揃ったら・・・」
話の途中でドアが開いた。
「やあ、遅れてすまないね。」
花梨は、入ってきた人物を見るや否や、大声を上げた。