

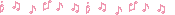
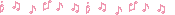
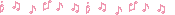


プロローグ 2
「て、店長?!」
「おや、高倉くんじゃないか。どうしてここに?」
「あ、あの、ボーカル募集の貼り紙を見て・・・。」
「なるほど。世間は狭いねえ。」
店長と呼ばれた人物がにこにこと笑う。
「翡翠の店のバイトか。」
泰継が静かに言った。
「そのとおり。」
翡翠は、笑みを消さずに答えながら肩に担いでいた大きなバッグを下ろすと、長い髪をかき上げて泰継を振り返った。
「可愛い子だろう?私のアルバイト採用には、こだわりがあるからね。」
「こだわりとやらは分からんが、確かにルックスは問題ないな。」
「ルックス・・・」
彰紋が呆然とつぶやき、
「こりゃまた古いな。」
イサトが右手を額に当てて天を仰いだ。
「ルックスは合格点だそうだよ。良かったね、姫君。」
翡翠は、彰紋たちの反応を楽しむようにそのままの言葉を用いて花梨に言葉をかけた。
「は、はい・・・ありがとうございます。店長。」
花梨は困った顔をしていた。
面と向かって外見を褒められても、どう返して良いか分からない。
「おやおや、店長はやめてくれないか。趣味の時間にまで仕事を持ち込みたくないのでね。翡翠と呼んでおくれ。」
「えっ・・・でも・・・。」
「いい機会じゃないか。プライベートでも君とお近づきになりたいのだよ。」
「は、はあ・・・。」
いつの間にか、翡翠は花梨の目の前まで迫ってきていた。
固まって成り行きを見つめる他のメンバーは完全無視で、そっと花梨の肩に手を置き瞳を覗き込む。
花梨がうつむいて頬を染めた。
「翡翠さん、花梨さんがお困りですよ。」
幸鷹が、こめかみに手を当てて二人の世界を壊した。
翡翠がからからと笑い出す。
「見たかい?この姫君は、心も可愛いだろう?私のこだわりはルックスだけじゃないんだよ。」
翡翠は、そう言いながら花梨から離れ、自分の大きなバッグを開け始めた。
開放された花梨はそそくさと椅子に座り、火照った頬を掌で覆ったり、ぱたぱたと手で仰いだりして、一生懸命冷まそうとしていた。
その仕草の可愛さに、翡翠以外の全員が思わず見とれる。
一瞬静まり返った部屋に、壁に掛けられた内線電話から呼び出し音が鳴った。
全員がはっと我に返り、座っていたイサトが楽器を置いて立ち上がった。
一番入り口の近くに居た勝真がドアを開けようとし、花梨と目が合う。
「少し待っていてくれ。」
優しく告げると出て行った。
電話機の近くにいた泉水が受話器を取り、短く返事をしてすぐに切る。
その間にも全員が急いでバラバラと出て行ってしまった。
最後に出て行こうとした泉水が、腰を浮かそうとした花梨に笑いかけた。
「心配ありません。頼忠さんがいらっしゃったのです。機材を運んでくる間、お待ちくださいね。」
そう告げると、ドアを開けたまま出て行った。
スタジオに一人残された花梨は、どっと緊張が緩んでため息をついた。
皆いい人みたいで良かった、と微笑む。
すぐに、歌唱力のテストがあることを思い出し、メンバーの前で何を歌おうか考え始めた。
しばらくすると、最初に出て行った勝真が、両手で抱えるように筒状の物を持って入ってきた。
一番奥に設置してあるキーボードのそばに置いて、カバーをはずす。
胴の部分が濃紺に塗られたドラムだ。
その間にも、それぞれが手に何かを持って入って来た。
どんどんカバーをはずしたり、ケースを開けたりして組み立て始める。
最後に、泉水が大きな円盤状のバッグを肩から下げて入ってきて、華奢な身体にも関わらず、重いドアを無駄のない動作で閉めた。
花梨がまだ知らない頼忠という人物は見当たらない。
それぞれが自分の運んできた部品を分かるところまで組み立て終わると、バラバラに置いた状態でドラムセットから離れ、自分の楽器の用意を始めた。
全員が音を出し始め、室内が音で満たされていく。
再びドアが開いて、知らない青年が入ってきた。
座っている花梨に気付くと、そばに跪いて口を開く。
「・・・!」
音の洪水の中で何か言おうとしている。
だが、花梨には聞こえない。
口許に耳を近づけると、青年は頬を染めて少し躊躇したが、精一杯の声を張り上げた。
「源頼忠と申します!」
「高倉花梨です!」
花梨も精一杯の声を出して答える。
「詳しくは先ほどお聞きしました!ご挨拶が遅くなって申し訳ありません!」
途中で楽器の音が止んだので、頼忠の『ありません!』という声だけがスタジオ内に響き渡った。
頼忠が恥ずかしそうに口許を手で覆う。
幸鷹が二人のそばに立っていた。
「あらためまして、私たちが、space‐timeです。」
幸鷹が微笑んだ。
頼忠以外の全員が、それぞれの手に楽器を持って花梨を見る。
彼らの真剣さが迫力となって花梨の身体にピリピリと伝わってきた。
「あらためてご紹介します。そこにいるのが、ドラムス担当の頼忠です。それから、翡翠はパーカッション担当。奥から、泰継がキーボード、勝真がベース、イサトがギターを担当しています。手前に居る3人はメロディーを担当しています。彰紋がトランペット、泉水がフルートとソプラノサックスを曲によって使い分けます。そして私がアルトサックス担当です。」
幸鷹は、ひと通り紹介を終えると、メンバーの方に向き直った。
「今日は特別に8時で練習を切り上げて、近くのカラオケボックスにでも行きませんか?花梨さんの歌を聞かせてもらいながら、歓迎パーティーを兼ねて食事をするのはいかがでしょう?」
「いいですね。」
彰紋がにっこりと頷いた。
泉水も静かに微笑む。
「やったぜ!俺、腹減った!」
イサトがお腹に手をあてると、泰継もつられて自分のお腹を見た。
「最初から歓迎パーティーを予定に入れてるところが幸鷹だよな。」
勝真がからかう振りをして、悪役を買って出た幸鷹の本来の気持ちを花梨に示した。
「異論はないよ。」
翡翠が笑みを浮かべ、頼忠も黙って頷いた。
幸鷹が花梨を振り向く。
「花梨さんのご都合は?」
「はいっ、大丈夫です!」
花梨は嬉しさのあまり即答した。
が、すぐにはっとする。
花梨の家は駅から遠い。
バスは22時8分が最終のはずだった。
「もちろん夜遅くなるようでしたら、責任持ってお送りしますよ。頼忠さん、遠方の場合には車を出せますか?」
「お任せください。」
花梨が頼忠に向かって申し訳なさそうな顔をするのを見て、幸鷹は自分の言葉が的を射ていた事を確信した。
「では、カラオケボックスを予約してきます。」
幸鷹が外に出ると、頼忠は花梨に会釈をして立ち上がり、ドラムセットへ向かった。
他のメンバーが再び音を出し始め、頼忠はバラバラに置いてある部品の位置を、自分の身体にあわせて調整している。
翡翠はバッグから出した数々の楽器を長机の上に並べ、泰継はキーボードの前に座って目を閉じていた。
ほどなくドラムセットから音が出て、無秩序な音の洪水が迫力を増した。
戻ってきた幸鷹が、アルトサックスを首にかけ、スタジオ中央の譜面台の前に立って右手を上げた。
急に音の洪水がうねりを止め、花梨の耳がキーンと鳴る。
「十八番のメガリスを花梨さんに聴いてもらいましょうか。」
楽譜のファイルをめくりながら幸鷹が言うと、全員がそれぞれ見易いようにファイルされた楽譜を取り出す。
先に楽譜を広げ終えた幸鷹が顔を上げた。
「では、花梨さん、しばらく私達の演奏を楽しんで下さい。」
幸鷹がそう言い終わると、泰継がキーボードで1つの音を弾いた。
打楽器以外の全員が、同じ音を出す。
時折、手を離して弦や管の調整をしている。
チューニングだ。
泰継がキーボードから手を離すと、全員の音が止んだ。
「イサト、低い。泉水、お前も少し低い。」
泰継が無表情で指摘する。
イサトが首をすくめながらピックを口にくわえて弦を調整し、泉水が申し訳なさそうな顔をして管を調整した。
泰継が再びキーボードを弾き、全員が再び同じ音を出す。
泰継は、しばらく目を閉じて耳を澄ませていたが、微かに笑んで手を離した。
音が止む。
泰継が無言で頷くと、頼忠が手に持ったスティックを3回打ち鳴らした。
いきなり泉水と彰紋がユニゾンで駆け上がるようなメロディーを叩き出す。
幸鷹が悲鳴のようなソロを吹き、勝真がベースを叩くようにして割れた音を出す。
最初からハイテンションな曲だ。
速いテンポにも関わらず、頼忠は眉一つ動かさずに手足を動かし続け、泰継が上下の鍵盤を超人的な技巧で叩き、翡翠とイサトが特殊なリズムパターンを正確に刻む。
ライブを聴きに行ったことがない花梨は圧倒された。
CDとは違って身体中に響いてくる大音量。
目の前で真剣に演奏する姿。
初めて体験する感動に、思わず涙ぐんでいた。
曲の最後に入り、全員が眉間にしわを寄せて最後の音を激しくかき鳴らすと、幸鷹がアルトサックスを吹きながらゆっくりと上下させる。
そのモーションを合図に全員が音を止めた。
花梨は立ち上がって満面の笑みで拍手を送る。
細められた瞳が潤んでいる。
「すごいです!カッコイイです!」
花梨が興奮してまくし立てた。
が、メンバーのほとんどから反応がなかった。
「・・・あれ?」
よく見ると、全員が脱力していた。
勝真が椅子に座り込む。
「悪いな花梨。いつもはここまで疲れないんだが。」
「すみません。どうやら私が走ってしまったようです。」
「オリジナルと同じテンポだ、頼忠。問題ない。」
「プロと同じ速さかよ?どーりでキツイわけだぜ。」
「僕もけっこう走っちゃいました。ごめんなさい。」
「はぁ・・・」
「泉水さん・・・大丈夫ですか?・・・私も少し・・・酸欠気味です。」
「せっかく姫君が褒めてくださったのに、情けない所を見せてしまったね。」
翡翠の言葉に、心配気に眉を寄せてメンバーを見ていた花梨の顔が笑顔になる。
「いいえ、皆さん、とってもかっこよかったです。本当に、感動しました。」
「それはよかった。しかし、どうやら姫君に良い所を見せようと張り切り過ぎたようだ。ねぇ、彰紋、そうじゃないかい?」
翡翠の言葉に、花梨が目を丸くして彰紋を見た。
彰紋が頬を染めて花梨の視線を避けるように翡翠を振り返る。
「や、やめてください、翡翠さん・・・。」
彰紋の可愛らしい抗議に、翡翠が嬉しそうに笑みを返す。
「いや、怒らないでおくれ。幸鷹、酸欠は直ったかい?」
急に話を振られた幸鷹は、彰紋と同じ目に遭わされるのかと思い、ビクッと肩を震わせた。
「は、はい。なんとか。」
幸鷹の様子に気付いた翡翠はそれ以上の事は言わなかった。
幸鷹が誤魔化すように咳払いをする。
「で、では皆さん、どこかやり直したい場所はありますか?」
泉水が楽譜を見ながら遠慮がちに切り出す。
「あの、私のフルートと皆さんがユニゾンになる部分をもう一度、ゆっくりさらっていただけませんか?」
「そうだな。そこは私も気になった。」
泰継が頷くと、泉水が安心したように続けた。
「ソプラノサックスとの持ち替えも練習したいので、前後もお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。」
「泉水は完璧主義だよな。」
勝真が感嘆の声で言ってベースを持ち直すと、椅子から立ち上がった。