
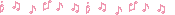
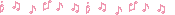
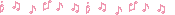


プロローグ 4
テーブルに所狭しと並んだ食べ物が半分に減った頃、彰紋が遠慮がちに口を開いた。
「あの、僕、花梨さんのバラード聴きたいです。」
「そうだな。俺も、もう少し花梨の歌を聴きたいと思ってたんだ。」
勝真がそう言って3杯目のビールを飲み干す。
「知っている歌なら、多分歌えると思います。」
「やった!じゃあ、こちらで入力しますから、ダメだったら言ってくださいね。」
彰紋がすでに手許に用意していた曲目リストをめくった。
手早くリモコンを操作すると、数年前に大ヒットした曲が流れ始める。
「ウタダなら、大丈夫ですよね。」
花梨は笑顔で頷くと、再び舞台の上に立った。
先ほどの明るい笑顔とは対照的な、切ない顔で視線を落とし恋の終わりを歌い出す。
全員が、失った恋や、言えなかった恋、一度は覚えのある切ない感情を呼び覚まされ、胸の奥がツンとした。
サビに入ると、花梨は涙がこぼれそうな表情で彰紋を見つめ、左手は何かをつかむように握られる。
それを見て泉水などは思わず涙ぐんでしまった。
歌い終わっても、花梨は余韻に浸るように後奏が終わるまで俯いて立ち尽くした。
完全に音がなくなると、静かに顔を上げる。
翡翠の拍手で、全員がはっと我に返って手を叩いた。
泉水がハンカチを出して目頭を押さえる。
「ありがとうございました。」
目を潤ませて花梨に礼を言った彰紋の膝から、勝真が曲目リストを奪い取った。
「次は俺だ。」
「あっ、ずりぃぞ勝真!その次は俺だかんな。」
花梨はそんな彼らの反応が嬉しく、ますます気合を入れて歌った。
ユーロビートは鋭く歯切れよく、激しいロックは叫ぶように、歌いこなす。
しかし、デュエット曲をリクエストして一緒に歌っていた翡翠が花梨の肩を抱くと、努めて色っぽく翡翠を見つめていた瞳がそらされ、歌も棒読みのようになってしまった。
「翡翠さん、それはセクハラですよ。」
幸鷹が抗議したが、花梨の恥らう様子が可愛いので、どうしてももう少し見たいと思ってしまう。
他のメンバーも翡翠を責めず、頬を染めて固まりながら歌う花梨を、チラチラと見ていた。
それを分かっているのかいないのか、翡翠は嬉しそうに花梨をからかいながら最後まで歌い終えてしまった。
釈然としない幸鷹だったが、手はしっかりとリモコンを操作している。
誰でも知っている英語の歌がリクエストされた。
火照った頬を両手で覆いながら画面を見た花梨は、ガックリとうなだれてしまった。
「ご、ごめんなさい。英語は、発音に自信がないんです。」
「そうでしたか。かまいませんよ。あなたらしく歌ってくだされば良いのです。」
少しぎこちなかったが、花梨は何とか最後まで歌い終えた。
幸鷹が満足そうに頷く。
「英語の歌を歌うことはありますか?」
花梨が幸鷹を上目遣いで見ると、微笑んでいた幸鷹の顔が少しだけ引き締まった。
「そうですね。ジャズを中心にやっていこうと思っていますので、英語は多くなると思います。」
一歩あとずさり、頭を抱えてしまった花梨を、泉水が優しく慰める。
「幸鷹さんはアメリカへ留学した経験をお持ちですし、発音を教えていただいたらいかがですか?」
「ええ、もし、花梨さんがお嫌でなければ、一緒に発音の練習をしましょう。」
幸鷹は、そう言いながらリモコンを泉水へ渡した。
「はい!お願いします!」
「他の勉強も教えてもらえよ。俺も赤点取りそうなときは世話になってるんだ。」
イサトが胸を張った。
すかさず勝真がその胸を拳で軽く突く。
「いてっ」
「自慢げに言うな。」
花梨が吹き出す。
笑っているうちに再び前奏が流れ始めた。
泉水が選んだのは最近流行っている沖縄民謡の発声を取り入れた歌だった。
民謡の発声はできない花梨だったが、独自の解釈で抑揚をつけて歌いこなす。
目を閉じて聴き入る泉水の隣では、リモコンの操作をしたことがない泰継が、彰紋に入力を頼んでいた。
「ピーターラビット?本当にこれでいいんですか?」
「そうだ。」
「分かりました。」
首を傾げながらも彰紋が番号を入力する。
花梨は歌い終わると、続けて出てきた画面に、飛び上がって喜んだ。
「きゃあっ、ピーターラビットの歌だ!懐かしい!泰継さんですね?」
「そうだ。知っているであろう?」
「はい!久しぶりに歌えて嬉しいです!」
花梨はその歌だけ、喋る時と同じ子供っぽい声で元気に歌った。
花梨が歌い終わると、泰継は嬉しそうに花梨へ語りかける。
「やはり歌はこれに限るな。」
「いい歌ですよね!」
音楽教室の児童クラスで歌われるその歌は、NHKの教育番組などでは流れたりするのだが、他の者は知っているはずもなく、ただ呆然と泰継が彼らに初めて見せる満面の笑顔を見ていた。
「なんだ、なぜ皆私を見る。」
「えっ?あ、そ、そうだ、頼忠さんがまだリクエストしていませんね。」
その場をごまかすように彰紋がリモコンを頼忠に渡すと、頼忠は困ったように前髪をかきあげた。
「そうですね・・・。」
「そうか。頼忠はインストしか聞かないからな。」
4杯目のジョッキを空けてご満悦の勝真がそう言うと、頼忠が持っているリモコンを取り上げて何やら入力する。
「インストって何ですか?」
「インストゥルメンタルの略です。今日、私たちが練習していたような、歌のないBGM風の音楽を総称して言います。」
幸鷹が花梨に説明すると、花梨は驚いたように頼忠を見た。
「じゃあ、頼忠さんは歌をあまり聞かないんですか。」
「はい。」
申し訳なさそうに頼忠が頷いた。
「気にすんなよ、頼忠。俺が代わりにリクエストしといたからな。」
勝真がニヤニヤとだらしなく笑いながらリモコンを置くと、独特の前奏が流れてきた。
「演歌かよ!やっぱ勝真ってバカだよな!」
イサトが腹を抱えて笑う。
ウケ狙いと察した花梨が演歌歌手のように舞台の上でゆっくりとお辞儀をした。
「さすが花梨。ノリがいいぜ。」
すっかりできあがっている勝真に褒められ、花梨も調子に乗る。
歌いながら演歌歌手の真似をして眉根にしわを寄せ、左手の拳を力強く振った。
勝真とイサトが爆笑する。
「花梨さん、ノリ良すぎです・・・」
彰紋が両手で顔を覆っていやいやと首を振った。
カラオケボックスを出ると、時計は十時半を回っていた。
「奢っていただいてすみませんでした。」
花梨が頭を下げると、幸鷹が首を振る。
「今日は、あなたの歓迎パーティーですから。こちらこそ、ゆっくり食事をさせてあげられず、申し訳なかったと思っています。」
「そんな・・・私、皆さんに歌を聞いてもらえて嬉しかったです。」
「私たちも同じ気持ちです。夢のような時間でした。」
泉水がそう言いながら花梨に歩み寄ると、両手で花梨の手を握り、微笑んだ。
泉水が醸し出す無害な雰囲気と、女友達のような自然さに、花梨も微笑んで手を握り返す。
「次は土曜日だな。」
そんな二人を見て憮然とした泰継が幸鷹に話しかける。
泉水が我に返ると頬を染めてそっと手を離した。
幸鷹が泉水を横目で見ながら答える。
「は、はい。そうでした。花梨さん、私たちは火曜日と土曜日の7時に例のスタジオで集まって練習していますので、都合のつく日はいらしてください。」
「はい。分かりました。」
花梨の返事を聞き終わらないうちに、幸鷹がふと地面を見つめ、急いで顔を上げた。
「そうだ、次回は、花梨さんに歌っていただけるような曲目を増やすためミーティングにしませんか?」
ぐるりとメンバーを見回す。
「そうですね。」
彰紋が答え、他のメンバーも頷いた。
「俺、練習もしてぇから、ギターは持ってく。家だと思いっきり音出せねぇからさ。」
イサトが遠慮がちに口を挟んだ。
「分かりました。では、少し時間を取ることにしましょう。」
幸鷹がイサトに答えてから、花梨を心配げに見た。
先ほどから花梨がちらちらと翡翠を見ているのだ。
翡翠がその様子を見て口を開いた。
「そうか、確か姫君は土曜日の夜シフトに入っているね。」
「はい。」
残念そうに花梨が頷く。
「では、調整してみよう。姫君とお近づきになる時間を自ら削るのは無粋だからね。」
翡翠がそう言いながら花梨に近づいてきたので、先ほどのデュエットを思い出してしまった花梨は頬を染めた。
「あ、ありがとうございます。」
「おや、どうしたのかな?そんな顔をされると帰したくなくなってしまうよ。」
「えっ、あの・・・」
「おい頼忠、花梨が危ないから早く送ってやれ。」
「そうだな。」
煙草をくわえた勝真が煙たそうな顔であごをしゃくると、頼忠がポロシャツの胸ポケットから車のキーを取り出した。
翡翠が苦笑を浮かべて、近づいてきた頼忠を振り返る。
「では、花梨さん、車を取って来ますので、もうしばらくお待ちください。」
「はい。もうバスがなくて。すみません。」
花梨の返事を聞くと、すぐに頼忠は駆け出した。
「何も走ることはないけどな。」
勝真が携帯灰皿に灰を落としながら呟く。
花梨が幸鷹に向き直った。
「あの、練習に行かれない場合のために、携帯電話の番号をお聞きしても良いですか?」
「分かりました。欠席連絡は義務制にしていませんが、事前にご連絡いただけると助かります。」
幸鷹が携帯電話を出す。
花梨も自分の携帯電話を出すと、幸鷹に教えられた番号をプッシュした。
すぐに幸鷹の携帯電話から着信音が鳴る。
幸鷹が驚いて画面を見ると、知らない番号が表示されていた。
「それが私の番号です。」
花梨が呼び出しを停止してから言うと、幸鷹が嬉しそうに笑った。
「分かりました。」
それを見てイサトがズボンのポケットから携帯電話を出す。
「花梨、俺にも番号教えろよ。」
「あっ、僕にも教えてください。メルアドも。」
彰紋も慌ててカバンを開けた。
「うん。いいよ。」
花梨はイサトと彰紋に電話番号とメールアドレスを教えて、自分も教えてもらった番号とアドレスを登録した。
イサトはズボンのポケットに左手を入れ、真剣な顔で登録に集中している。
その間に彰紋がメールを一通打ち終えていた。花梨の携帯が短く鳴る。
「あっ、彰紋君だ。打つの早いねぇ!」
「そんなことないですよ。」
「あっれぇ?おかしいな?」
イサトはまだ登録に苦戦している。
花梨はそれを見て微笑むと他のメンバーの方を見た。
「勝真さん達は、携帯持ってないんですか?」
「あ?いや、持ってるよ。」
「せっかくですから番号教えてください。」
「いいぜ。」
「そうですね。」
勝真と泉水が携帯電話を取り出した。
「私は持っていない。必要ないのでな。」
泰継が興味なさそうに言うのと同時に、頼忠のミニバンがハザードランプを点して目の前に止まった。
頼忠が運転席から降りて、花梨に近づく。
「あ、頼忠さん、すみません。今行きます。」
携帯電話に二人の電話番号を登録しながら花梨は頼忠の方を向いた。
「大丈夫ですよ。お待ちしていますから。」
「ありがとうございます。頼忠さんも、あとで携帯電話の番号教えてくださいね。」
「え?・・・は、はい。」
頼忠は戸惑った顔をしたが、花梨は携帯電話の画面を見ていたので気付かなかった。
ほどなく、二人分のメールアドレスまで登録し終えた花梨が、申し訳なさそうに頼忠を見上げた。
「すみません、お待たせしました。」
「いいえ。」
頼忠は真面目な顔で首を振ると、後ろを向いて助手席のドアを開けた。
「皆さん、本当に今日はありがとうございました!」
花梨が深々と頭を下げてから車に乗り込んだ。
頼忠がドアを閉めて運転席に回る。
花梨がゴソゴソとパワーウインドウのボタンを探し、助手席の窓を開けた。
全員が花梨を見て手を振る。
「またな。」
「学校で会おうぜ!」
「ごきげんよう。」
「お気をつけて。」
「はい!皆さん、おやすみなさい!」
花梨が手を振るのを見届けてから頼忠が静かに車を出した。
皆が見えなくなると、花梨が窓を閉めて前を向く。
頼忠が口を開いた。
「では、ナビをお願いします。」
「はい。平安神社の近くなので、まずは平安神社に向かってください。」
シートベルトを締めながら、花梨は分かりやすい指示を出した。
「わかりました。」
カーステレオから微かに音楽が流れてくる。
黙って運転を続ける頼忠に、花梨は少し話かけてみることにした。
「あの、この音楽は、今日皆さんが演奏していたのと同じで、歌がないんですね。」
「はい。」
困ったように短く返事をして頼忠は再び黙ってしまった。
先ほど、インストしか聞かないことを気に病んでいた頼忠を思い出し、慌てて次の質問を探す。
「あの、さっき、幸鷹さんがジャズを中心にって言ってましたけど、これもジャズに入るんですか?」
「そうですね。厳密に言うと違いますが、ジャズの流れを汲んでいます。」
「へえ。私、ジャズの事ぜんぜん分からないんです。バンドで演奏している音楽のことも、いろいろ教えてください。」
花梨が勢い込んで言うと、頼忠は、少し驚いたような微笑を浮かべて頷いた。
「はい。では・・・何からお話すれば良いでしょうか。」
「じゃあ、この音楽のこと、教えてください。」
花梨がカーステレオを指差す。
「そうですね。通常、ジャズは電源を使わないアコースティックギターやウッドベース、ピアノ、それから部品の少ないドラムセットを使用して、管楽器と合わせることが多いです。」
「はい。そういうのは吹奏楽でやったことがあります。」
「今流れているのは、それにロックの要素を融合させて現代風アレンジを施した、フュージョンというジャンルの音楽です。」
「だから、イサト君と勝真さんはロックバンドみたいなんですね。」
「そうです。space‐timeはもともとジャズバンドだったのですが、一年前にイサトと彰紋が入ってきてから、フュージョンバンドのコピーを中心にやるようになりました。」
「そうだったんですか・・・。でも、それじゃあ、私は?」
「せっかく大人数でやっているのだし、いろいろな音楽をやってみたい、という思いは全員にありましたので、ボーカルがあるジャズをやらないか、という彰紋の提案に賛成したのです。」
「へえ。」
「ただ、ライブでは、歌のある曲とない曲、両方演奏することになると思います。花梨さんが暇にならないように、泉水がアレンジして楽譜を起こすと思いますよ。」
「じゃあ、私もフュージョンをたくさん聴かなくちゃ!」
嬉しそうに言う花梨に、頼忠がふわりと微笑む。
「では、手始めにこのCDをお貸ししますよ。」
初めて見る頼忠の笑顔が意外に優しげで甘いことに驚いてしまった花梨は、慌ててこくこくと頷くと、高鳴る心臓をおさめるため、黙ってカーステレオの音楽を聴くことにした。
「あ、そこを曲がってください。」
平安神社の近くまで来たので、花梨が指示を出す。
いくつか路地を曲がって、花梨の家の前に車が停まると、頼忠はシートベルトを外して、カーステレオを操作した。
ゆっくりと吐き出されたCDをジャケットにしまう。
「ジャズやフュージョンのCDは他にもたくさんありますので、次回また別のものをお貸しします。」
CDを花梨に渡しながら、頼忠が微笑む。
「ありがとうございます。」
花梨は、優しい微笑みに再びドキリとしてしまったが、頼忠が運転している時には言えなかったことを切り出すことにした。
「あの、頼忠さん、もし良かったら、携帯電話の番号、教えてください。」
頼忠が、少し困ったような表情になった。
「はい・・・ですが、私は仕事で呼び出される事があるので持つようにしているだけで、彰紋のように機能を使いこなしたりはしていないのですよ。」
「それなら大丈夫です。メル友になりたいとかじゃなくて、番号を知っていると便利な時があるから教えて欲しいだけなんです。頼忠さんも、緊急の連絡があった時のために、私の番号を知っておいてください。」
「分かりました。」
頼忠は頷いて、ドリンクホルダーに無造作に入れてあった携帯電話を取り出した。
お互いに電話番号を教えあって携帯電話を閉じると、花梨がシートベルトを外しているうちに、頼忠が車を降りて助手席を開ける。
「なんか、お姫様みたいです。」
そんなことを言いながら花梨が降りると、頼忠が真面目な顔で言った。
「ご両親にとっては、お姫様そのものだと思いますので、遅くなったお詫びのご挨拶をさせてください。」
「そ、そんな、大丈夫ですよ。うちは門限とかないし。」
「いいえ、今後もライブなどで遅くなることがあると思います。そういった時に快く送り出していただくためにも、ご両親に安心していただきたいのです。」
「はい・・・。」
頷きながらも、花梨は嫌な予感がした。
案の定、花梨の母親は頼忠を見た途端、花梨に美形の彼氏ができたと小躍りした。
慌てて出てきた父親や小学生の弟までもが品定めを始めてしまう始末で、ようやく誤解が解けた頼忠は、謝る花梨に見送られながら、真っ赤な顔をして帰って行ったのだった。