

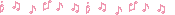
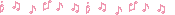
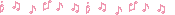


プロローグ 3
駐車場から出てきたミニバンは、楽器店の前でハザードランプをつけて止まった。
運転席から降りた頼忠が車の後ろに回ってトランクを開け、全員が協力して手早く頼忠のドラムセットを積み込む。
「では、私は先に行って受付を済ませておきます。」
幸鷹が花梨たちにそう告げて助手席に乗り込むと、和仁が店から出てきた。
頼忠が和仁に会釈をしてから運転席に乗り込む。
幸鷹も和仁に気付くと助手席の窓を開けた。
「急に予定を変更してすみませんでした。」
「いや、明日はレコーディング予約が入っているからな。スタジオが早く空けば時朝がゆっくり準備できる。」
和仁がそう言って右手を上げると、頼忠が静かに車を出した。
「じゃ、俺達も行くか。和仁、また土曜日な。」
カラオケボックスの場所を知っている勝真が、先頭に立って歩き出した。
花梨も和仁に会釈をしてから、はぐれないようにすぐ後ろを歩く。
あとから他のメンバーも口々に和仁へ挨拶をしてついてきた。
花梨は歩きながら親に電話をかけて遅くなる旨を伝えると、パチンと携帯電話をたたんだ。
「あの、花梨さん、少しお話してもよろしいですか?」
いつのまにか泉水が花梨の隣に並んで歩いていた。
「はい、どうぞ。」
花梨が、遠慮がちな泉水を気遣い、携帯電話をカバンにしまいながら努めて元気に続きを促す。
「ありがとうございます。あの・・・今日、私達の練習をご覧になって、何か気付いた事があれば、教えていただきたいのです。」
「気付いたこと、ですか?」
「はい。些細なことで構いません。自分達では気付けない落ち度がたくさんあると思うのですよ。」
「落ち度だなんて・・・。」
悲しい顔になった花梨に、泉水が慌てる。
「あ、も、申し訳ありません、お気に触りましたでしょうか?」
今度は花梨が慌てる。
「いいえ、とても素敵な演奏だったので、落ち度があるなんて思えなくて。」
「ありがとうございます。花梨さんはお優しいのですね。でも、やはり良い演奏をするためには、常に自分の至らない部分を探さなくてはいけないのです。」
優しく微笑みながら紡がれる泉水の言葉は、しなやかな強さを秘めている。
花梨は尊敬の眼差しで泉水を見つめた。
「泉水さんは努力家なんですね。」
感嘆の声で言われ、泉水は戸惑った表情を見せた。
頬が染まる。
「あ、あの・・・。」
泉水が困ってしまったようなので、花梨は話題を変えた。
視線を勝真の背中へ戻す。
「気付いたことかぁ・・・私は楽器を演奏した経験が少ないから、技術について言えることはないんですけど・・・なんか、皆さん真剣すぎて、あまり楽しそうに見えないかなぁ。うん、そうそう。もっと踊ったり笑ったりしながら演奏したら、楽しそうかも。」
「踊ったり、笑ったり・・・ですか?」
泉水が気の抜けた声を出し、前を歩く勝真の肩が震えた。
どうやら笑っているようだ。
花梨は説明不足であることに気付いて続ける。
「はい。歌なんかは特にそうなんですけど、直立不動で歌う人って下手そうに見えるし、いくら本人が楽しいと思っていても、見てる人にはつまらなそうに見えるんです。だから、私はいつも先生に楽しそうな表情や身振りで歌いなさいって言われます。」
「なるほど。演奏している姿でも音楽を表現しなければならない、という意味ですね。」
「はい!」
泉水は花梨が元気良く頷く様子に目を細めた。
「確かに、私たちはテクニックを重視しすぎている部分があるかもしれません。」
「そうだな。」
勝真が顔だけ振り向いて、肩越しに言葉を続ける。
「うちで客とコミュニケーションをとるのはイサトぐらいだもんな。」
「俺がどうしたって?」
花梨のうしろで彰紋と話していたイサトが首をつっこんだ。
「お前がよく『ライブで客と盛り上がりたい』って言ってるだろ?花梨が同じ事を言ってるんだよ。」
「マジで?!」
「そうですね。そういう事につながると思います。」
花梨が振り向いてイサトに頷いた。
嬉しそうに花梨を見ていたイサトが眉をしかめる。
「お前さ、敬語やめてくんねぇ?少なくとも俺と彰紋には一個上とか気にしないでタメ口きけよ。」
「えっ・・・でも彰紋君は、私にも敬語で話してくれてますから。」
「こいつはタラちゃんと一緒で日常会話が敬語なの!そういう家に育ったの!」
「イサトの言うとおりですから、気にしないでください。」
「じゃあ・・・ひゃっ!」
前を見ていなかった花梨は、急に立ち止まった勝真の背中にぶつかってしまった。
すぐにぶつかった反動で離れる。
「お?」
勝真が体の半分だけ振り向く。
「ご、ごめんなさい・・・」
花梨は、ぶつかった方の頬を押さえて縮こまった。
「なんだ、前見て歩けよ。ずいぶん積極的だと思っただろ。」
ニヤニヤしながら言う勝真の言葉に、花梨は抱きついてしまったかと、先ほどの状況を思い出す。
すぐに勝真の冗談だと気付いたが、自分の頬からTシャツ越しに感じた勝真の引き締まった背中や、微かに香る香水、そして勝真本人の匂いがよみがえってしまった。
花梨の顔がみるみる赤くなる。
「す、すみません!」
勝真が驚いた顔になった。
「おい、冗談だよ。」
「本当に可愛い姫君だねえ。勝真、ここかい?」
翡翠が口を挟む。
「ああ、そうだ。」
勝真が花梨を気遣いながら答えた。
1階はバーになっている。
泰継がエレベーターホールを見つけると、入っていって上ボタンを押した。
「な、悪かった。」
勝真は膝に手を当ててかがみ、両手で頬を覆っている花梨を覗き込んだ。
赤くなった顔を見られたくない花梨は、俯いてこくこくと頭を縦に振る。
エレベーターが着き、皆が乗り込んだ。
「参ったな。ほら乗るぞ。」
左手で花梨の背中をそっと押し、右手で頭をかきながら、勝真が最後に乗り込んだ。
花梨は、勝真をあまり困らせてはいけないと思い、エレベーターが動き出すと顔を上げた。
「もう大丈夫です。すみません。」
まだ赤い顔の花梨に見上げられ、勝真は、大丈夫じゃないだろ、と思ったが、その嘘が気遣いであることに気付いて安心した顔をつくった。
「いや、大丈夫ならいいんだ。」
「勝真がいつもの調子でからかうからだぞ。花梨を合コンに来るコジャレた女と一緒にすんなよ。」
イサトが眉をしかめて言った。
「ほう。」
翡翠が意味ありげに感嘆の声を上げたところでエレベーターが止まった。
ドアが開くと幸鷹が受付の前で待っていた。
広い部屋に全員が座ると、幸鷹が頼忠を連れて入ってきた。
入り口の近くに座っていた花梨の隣へ腰を下ろす。
「俺、ウーロン茶!」
イサトが言い放つと、彰紋がリモコンを操作して注文し始めた。
「俺は生。」
「いいねえ勝真。私もそれにしよう。」
「幸鷹と泰継も付き合えよ。」
「そうですね。明日がありますので、少しだけ。」
「私は素面で花梨の歌を聴きたいのでやめておく。ウーロン茶でいい。」
「じゃあ俺が飲む!」
「イサトは先日の打ち上げで酷い目にあったであろう?」
「それに、今日は僕たち制服だから、やめた方がいいですよ。」
「ちぇっ。」
「花梨さんは何にしますか?」
「じゃあ、グレープフルーツジュースにします。」
「あ、あの、私もそれでお願いします。」
「頼忠さんは?」
「ウーロン茶でお願いします。」
彰紋が気を利かせて枝豆とフライドポテトも選択し、リモコンのボタンを押すと、ピピッとテレビの下から音が鳴り、注文が完了した。
「さて・・・」
幸鷹が口を開くと、全員が花梨を見た。
花梨は思わず背筋を伸ばす。
「あの、どうか、緊張なさらないでください。」
「そうだ。緊張しては実力が出せないだろう。」
泉水と泰継が正反対のベクトルで花梨に緊張させまいとした。
幸鷹も頷いて言う。
「そうですね。まずは緊張をほぐすためにも、花梨さんが一番得意な曲を選んで歌ってください。それから、私たちにリクエストさせていただけませんか?」
「はい。」
花梨が意を決した顔で、曲目リストの冊子を手に取ってページをめくった。
彰紋が、持っていたリモコンを花梨の方へ置く。
花梨はすぐに、リモコンを操作して番号を入力する。
前奏とともにパッと現れた画面を見て全員が絶句した。
「あやや・・・」
呆然と勝真が呟く。
その間に、花梨はマイクを持って自ら立ち上がると、一段高い舞台へ上がった。
「舞台に上がる奴、初めて見た・・・」
今度はイサトが呆然と呟く。
花梨は、先ほどの緊張した顔とは別人のような笑顔で歌いだした。
誰でも歌声は話し声と違うものだが、花梨の場合は特に違いが大きく、子供のような話し声からは想像がつかないような大人びた声だった。
「いい声だねえ。」
翡翠が目を細めてうんうんと頷いた。
花梨はそんな翡翠を見ると、嬉しそうに語りかけるような目で翡翠を見つめ歌った。
答えるように翡翠も優しく笑顔を返す。
その場に居た全員が、微かに羨ましさを覚えて花梨を見た。
すると花梨は、他のメンバーとも順番に目を合わせながら歌った。
笑顔で歌う花梨と目が合うと、誰もが思わず笑顔になっていた。
何故かは分からないが、全員が、心の奥をそっと包まれ優しく抱きしめられるような不思議な感情を覚えるのだ。
2番の途中で飲み物が運ばれてきたが、花梨は構わず歌い続けた。
花梨は出て行こうとした店員にまで愛敬をふりまき、歌いながらバイバイと手を振る。
店員も笑顔になって出て行った。
歌い終わった花梨がマイクを置くと、後奏が終わらないうちに全員が拍手を送る。
花梨は再び別人に戻ったように、はにかんだ顔をして座った。
「幸鷹さん、合格ですよね!」
彰紋が興奮気味に身を乗り出す。
「ええ。私は他の歌を聴くまでもないと思いました。他の皆さんは、いかがですか?」
幸鷹も微笑みながら全員を見まわした。
「問題ない。」
「俺は最初から花梨がいいと思ってたし。」
「姫君はマイクを持つだけで男を狂わすことができるね。」
「良いと思います。」
「癒し系ってやつだな。」
「素晴らしかったです、花梨さん。先ほどおっしゃっていたのは、こういう事なのですね。」
口々に褒められ、花梨はますます恥ずかしそうに身をすくめた。
「花梨さん、あらためて、よろしくおねがいします。」
全員の反応を見てから彰紋が言うと、幸鷹がビールを持ち上げて掲げた。
全員がそれを見て飲み物を掲げる。
「では、新しいメンバーを歓迎して乾杯!」
「乾杯!」